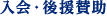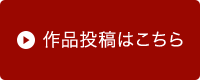日本現代詩人会 詩投稿作品 第38期(2025年7月―9月)入選作・佳作・選評発表!!
厳正なる選考の結果、入選作は以下のように決定いたしました。
伊武トーマ選
【入選】
八巻孝之「耳鳴り」
杜梨乃「香りの祈祷」
催花亮太「花火」
牛坂夏輝「トカゲの詩、あるいは恋愛関係」
緒方水花里「リベンジライト」
【佳作】
中村太「熱波」
中村憂「刺青」
三明十種「in the 夕景」
春日野あやめ 「パッカーしゃと ぬいぐるみ」
しきゅう「ストロングゼロ」
橘麻巳子選
【入選】
芝眞帆「小鳥が死んだ」
大西優佑「隣人」
永井雨「夏だよ といいたかった」
【佳作】
岩下瓜「繋ぎ目に真昼は佇み」
三明十種「夏の翳」
あらいれいか「しょうめいたん」
根本紫苑選
【入選】
嶋田隆之「エリンギ」
こやけまめ「からの臓器」
横山信幸「水影」
鈴木和則「影を踏む」
加藤雅水「音叉としての海、または、欠落する風の書物」
【佳作】
公園「鳥」
妻咲邦香「バス停」
嶋田隆之「蛇口」
小川尚子「イカナゴ」
杜梨乃「祖父の辞書」
投稿数:683 投稿者:354
沢山のご投稿ありがとうございました。
引き続き、皆様のご参加をお待ちしています。
八巻 孝之「耳鳴り」
昨日
見上げた月が
男の顔をして
わたしを黙殺した
舗道に
骨が落ちている
名もなく
赤いランドセルの隣で
風が笑っている
誰も気づかぬふりで
魚の死を
午後に隠す
名前を奪われた声が
わたしを呼ぶ
性別のない声で
何度も 何度も
駅の構内で
押しつぶされた悲鳴が
モップの下で
静かに潰れていく
午後三時のバスは来ない
そのバスは
いつも女だけを
乗せないことにしている
テレビには
亡命した少女の目
その中で
銃声が育っている
世界はやけに静かだ
それとも
わたしの耳鳴りが
人間の声を
ふさいでいるだけか
病室のベッドで
名前のない少女が
「痛い」と言った
けれど
記録には残されなかった
切符の裏には
「この国を出なさい」
わたしの字で
わたしへ
声を上げようとした
けれど
舌の奥で
血のように
言葉が凍った
夜ごと
記憶がわたしを蹴って出てゆく
朝には
からっぽの器と
中指だけが残る
ポケットの中には
壊れたイヤリング
と
もうひとつ――
名をつけられなかった
命の重さがあった
杜 梨乃「香りの祈祷」
水はまだ祈っていない
羊肉の脂が意識を濾し
ローリエとタイムが
鍋底で擦れるたび
死んだ香りが
言葉の亡骸となって漂う
ブーケガルニは生き物だった
煮込まれ断片となり
祈祷の具として蘇る
「あなた」は喉で名を練り
「わたし」は舌でそれを飲む
鍋の中で崩れる
羊の筋とわたしの意味
朝でも夜でもない
羊の肩肉が和らぐ時刻
霧はジェンダーの名を拒み
記憶は香りだけを信仰する
煮汁は光を吸収し
香りの向こう
湯気に「あなた」の輪郭が揺らぐ
崇拝は香りの擬態となり
沈黙をなぞる
鍋の底で
羊が変容するのを見届けながら
祈りきれず煮えきらず
名もなき献身のかけらとして
わたしは
まだ漂っている
催花亮太「花火」
僕はちっぽけな虫だから
燕は戦闘機のように
地面を鳴らして飛ぶだろう
雨は焼夷弾のように降るだろう
帰る家さえなくして
都市に消え入る全ての羽音が
恐ろしく木霊するだろう
開く花弁の擦れる音が
花火のように乱れ飛ぶ
一面の野を目にするだろう
牛坂夏輝「トカゲの詩、あるいは恋愛関係」
Ⅰ
湿った石の下から
蒼白のトカゲが目を開く
眼差しは腐敗した果実を割り
皮膚の下で沈黙は血を濁らせる
ひとつの震えが骨に突き刺さり
愛撫の予感は死の吐息を孕む
閉ざされた扉の奥で
肉は黒い冷光を待ち
夜の影は心臓を抉る
Ⅱ
トカゲは舌を突き出し
腐臭の空気を切り裂きながら近づく
その身は干からびた花弁のように崩れ
触れるたび灰が舞い上がる
汗の輪郭は墓石を描き
二人の距離は死骸の温度に縮む
呼吸は血の柘榴を砕き
互いの影をすり抜けて
沈黙は屍のように血に沈む
Ⅲ
裂け目から溢れる暗黒の奔流
トカゲの尾は血に濡れて千切れ
再生の約束は虚ろに崩れる
白い閃光は墓標を照らし
唇は死の水を啜る
絶頂の闇は屍翼を持ち
息は冷たい晶体に変わり
世界は粉々に砕け散り
死の沈黙だけが残る
Ⅳ
余波に揺れる胸郭の奥で
トカゲは破片となって這い寄り
切断された尾を墓に捧げる
恋の残響は硝煙に変わり
沈黙は廃墟を満たす鐘を打つ
泉は血の泡を湧かせ
影は影に溶けず
光は朽ちた刃となって
孤独を屍の形に彫り出す
Ⅴ
夜明け、砂に埋もれたトカゲは
腐敗した夢を抱いたまま眠る
身体には死の痕跡が刻まれ
眼差しは空虚の余白を凝視する
触れた指先は冷たく
静けさは崩れた鐘楼に鳴り響く
互いの沈黙だけが累々と積もり
影は離反したまま
光は死の始まりを告げる
緒方 水花里「リベンジライト」
私はとられた
シャッターの隙間を潜り抜ける
瞬間殺された
アリス
あれは私の光だった
スマートフォンという名の銃身 歩道を5億年前の流木が渡るのに
誰も気付かない掌の中の死 4Kで柔らかく開くアリスに夢中
私はとられた
炸裂する光の度に
鱗が剥がれ落ちる
私
私ではない
私
分裂する
私
切った爪先 蜥蜴の尻尾
死んだ猿の手を
お守りにするのは誰?
月は本当はアメーバなのに
皆丸いと信じている
時間泥棒
私は光ではない(という光をあなたは見ている)
私は文字ではないのに(という私は文字である)
私は流れ星 落ちるその時でしかないのに 箱の中閉じ込めないで
アリスは彼と待ち合わせただけ 待ち合わせて車庫に行っただけ
閉じ始めるシャッターの隙間から逃げ出す手を引いて千切れる!
私の腕! 私の足! そして分裂する私と私と私と
アリス
私の時間! ダーリン返してあなたが見ているそれは誰? 私は私
アリスはいつも私のかさぶたを食べてしまうの
閃光「 」
「私」/それはかつてあった/「私」/アイスクリームを舐める/「私」/もう溶けてしまったのに/「私」/あなたはそこにいると信じている/「私」/見られている/「私」/私はあなたを見ていないのに/「私」/月を見上げている/「私」/違う見上げていた/「私」/丸い月など何処にもないあれは鏡の世界のまがいもの溶けないあなたは/私じゃない/私じゃない私じゃない私じゃない私私私私私が箱の中鏡の中世界中に私私私無数の私私私舐める舐め続ける私違うそれは私じゃない世界中に散らばるアリスアリスアリス
明かりを消して
恥ずかしいじゃないの
ねえダーウィン人類は進化を辿る一方じゃないの
街には死が散乱 皆が殺し合っている(他人を勿論自分も)
私をとりかえすための言葉さえも 平面世界で無限に死に続ける
それはつまり生き続けるということであり
「私」
は
眼鏡の中永遠に生き続けるのでしょう それは私ではないのにね
かつてあった流木の股の中へ吸い込まれる
私のアリス
私のアリス
私のアリス
私のアリスへ
今度は私が閉じ込める番でしょう?
芝眞帆「小鳥が死んだ」
小鳥が死んだ
ベーリング海峡の真ん中で
それは長い冬を超えた一羽
昼と夜が裏返る雲の上
タービンの音がうるさくて
あなたはうまく眠れない
小鳥が死んだ
東京の路地裏で
ねこよりさきにあなたがみつけた
白と黒の見慣れない色の羽根
あなたはほこりと間違えて
土踏まずで蹴飛ばした
小鳥が死んだ
世界で一番大きな都市
セブン・イレブンは九時に開き
あなたは6時に目が覚めた
ボブはメアリよりも仕事ができた
メアリはボブより子沢山
どちらも同時に亡くなった
小鳥が死んだ
蝙蝠よりはましだった
食べる肉もなかったし
ストックするには弱気が過ぎた
猫にとっては違っていた
焦って道路に飛び出して
あなたの車にぶつかった
大西 優佑「隣人」
私
人生に黄身を落として
つもりつもったから
老人が吐き出す唾
丁寧に撮り溜めているような日々
涙腺もろとも絡めとられ
各駅列車ばかり通すから
割れた傘
他人の傘を預かる日々
…
「ひっくり返してみて
その完璧な朝食を」
…
「中古の車輪で言葉を轢いたら
そこから海が見えるから」
…
チャイムの破れ目をなぞり
ぼんやりと忘れてやった顔が覗く
溶けた人
確かにそういう名前で
なぜ聴こえたのか
隣人と会ったのは
夏
永井雨「夏だよ といいたかった」
わたしはいまひとりでいる
ひとひとりがひとりでいるためにひとり
「二」の字の下の部位を担当している それは怠惰に
上担当の母はシツヨウにわたしの母指球を揉んでいる
わたしは母の玉のような足の指の腹を触り触っているのが何指が聞いている
薬指 ちがう中指 ちがう中指 ちがう中指
マチガエル
が鳴く ないていた
わたしはながいながい前奏で最期の夏を消費していた
生き延びてきたんだ ここまで
母は音漏れに耳をすましている
迷い込んだくらい光にまみれた台所にいけば
瓶いっぱいのアーモンド・チョコレート・ビスコッティがあった
カーテンを閉めなくともぶ厚い雲が真夏から二人を隠してくれた
じゃないと 真夏が危なかった
気まぐれに取り出した爪切りの音の カッチンかパッツンかして
先っぽの曲がった紙飛行機が一機単体 落ちている
妙に暗い
ほんとうに時間は動いているかわからない
わたしはなにもない天井をハイコントラスト白黒で収めた
タイトルは「二」
一昨年は「三」だった
わたしはひとりになる
ひとひとりがひとりでいられるためにひとり
「二」の字の下の部位を担当している それは怠惰に
Playlist:夜逃げ用/再生中
目を閉じると赤い
隕石さん
隕石さん
隕石日和だよ
嶋田隆之「エリンギ」
誰かに教えてもらったのか
どこかで読んだのか
すっかり忘れてしまったけれど
エリンギを買う時にはいつも思い出す
「仲良く並ぶエリンギを選びなさい」と
で、手に取った一パックは
小さい方が俯いていて これは
これは昨夜の君
お互いにそっぽ向くこれは
昨日の二人で
大きいのが反り返ってるこれは
返事もせずに部屋へと消えた僕の足音で
ねじれかけた小さいのが項垂れるこれは
ため息交じりの「いってきます」で仕事へと出て行く
今朝の君の背中で
カサでぐいぐい押し合いをしてるこれは
どちらものカサの端っこが折れてるこれは
これはエリンギ
あれこれ考えての一パックを
大きなエリンギのカサの下に
小さなエリンギが頭を置くそれを
静かにもたれ合うそれを
かごに入れ
二本が崩れぬようにかごに入れ
僕はレジへ向かう
エリンギは今夜、ピーマンと炒めて
焼き魚に添えて出す
一言添えて出す
こやけまめ「からの臓器」
1
喫茶店で待ち合わせをして
言葉にこころを返しました
もともと私のものではなかったそうです
こころってさ、人の中にはないんだ
どこにあるの?
言葉の中にある
言葉は私の中にあるの?
貸すことはできる
みぞおちに空虚ができたのはなぜ?
そう言うと言葉は
飲み干したコーヒーカップを
私のみぞおちの中に入れました
こころの代わりだ
2
コーヒーカップは一つの臓器になりました
からの臓器は朝になるとよく冷えました
コーヒーの残り香だけが
私を呼び止めるように漂います
ここに何かあるという感覚に少しの安堵を覚えていました
3
しかしその臓器はいつも、からでした
血液が巡っても
筋肉が複雑な運動をしていても
何かあるのに
何も入っていない
誰にも言えませんでした
軽いものを辛そうに抱えるのには罪悪感がありましたから
4
喫茶店で待ち合わせをして
言葉にからの臓器を返そうとしました
言葉は苦笑して
それは僕のものじゃない
お済みの食器をお下げしますね
からの臓器は店員が片付けてしまいました
こころも、からの臓器も
返さなくてはなりません
それは初めて
みぞおちが内側から抉れて
ことばがこぼれ落ちた日のことです
横山信幸「水影」
灼光がプールサイドに鋭い
君の節くれだった中指の爪の欠けの先の雫までが
くきやかな影をなしている
自分から欲しいと言ったものがあっただろうか
この三十四年、ひとを先に潤し、自分を語らず
僕が手をつなごうとしても笑って逃げた
その君が透きとおった
あの午後、
しろがねの雨に倒れ、あおがねの管を挿され
そして、記憶を熔かし今を失い続けた
つゆくさ色の歌を唄い、くり色の獣の香を発し
誰におもねらず、うそもほんとうもなく
内側を透きとおらせて、わがままに、
僕と手を繋ぎたがる 天真爛漫なみどり児になった
日焼けした君はまるで影の影
笑っているのは誰
君の指先から落ちた水雫一滴と
コンクリに映った紫黒の影一滴が
ひとつになる 瞬間、
影は小さな虹を孕みつつ、消える
あざやかに
最初から無かったかのような まばゆいあっけなさで
僕がその手に触れるとき
僕らの影の影に
虹がほどける
鈴木和則「影を踏む」
「死は生がつくる影さ。だから生が消えれば
死も消えるんだ」
会社の元同僚にむかって話す私の声が自分の
耳許に滴り落ちた。相手に伝わったか否か、
と訝る自分の影が薄いことに気づかされた。
お互い二年前に定年退職していた。古希を
まぢかにしたある宵のこと、二人で余生に
ついて語るともなく語り合った。少し酔いが
まわった彼が、面接官のように訊ねてきた。
「おい、いったいなにをしたら、なにかをし
たといえるんだろうか」
歳の割に粒だった声が弾けた。
「生きるとは、しょせん、戯れさ。死という
影の影踏みあそびなんだ。どう生きようとそ
れ以外に意味はないんだ」
それから同僚の怪訝は膨らみ、彼にとっては
手触り感のない時間がいつまでも続いた。
やがて宵も深まり、どんなにことばを継いで
も伝わらない処に辿り着いたところで店を出
た。街燈の下に立った二人の複数の影が淡く
ぼんやりと地面に射していた。
「たしかに生死の境がゆるんできたなあ。
なぜ細君は死んでいて、おれは生きている
のか、たいした違いはないような気がするよ」
そういって彼は、不意に自分の淡い影を
踏んだ。
「死はあっても、『おれの死』はないという
ことだな」
彼はまるで遠い星をみるように自分の影を
眺めていた。
加藤 雅水「音叉としての海、または、欠落する風の書物」
海がね、うん
あの裂けた音叉だったんだよ、ほら
浜辺に散らばる、骨のような記憶──
それが、ぼくの声を、
ぶつ切りにしてくるのさ
岩の割れ目に耳を当てると
おーん、おーん、
死者の詩篇が泡立つ
泡の裏で、言葉がひっくり返る
舌下に、湿った金属音が這う
朝の海で拾ったのは
名前のない句読点
それを掌で乾かしながら
声帯の奥に埋めた、失語の墓標
紙魚の這った痕が、ぼくの声の痕跡
風が、逃げる
風だけが読める文字があって
それは、
どこかで廃刊になった風速計の原稿で
読んではいけない
読まれてはいけない
読むふりをする
だからね、
おまえの底で
何万年もかけて沈んでいくのは
意味ではなく
発語に届かなかった
欲望の遺物なんだよ
■伊武トーマ選評(38期全体)
月毎に投稿作品の熱量が高まって来ていると実感しています。一方、技量のある方たちは中盤を過ぎ、少し自己模倣に陥りがちだったり、オリジナリティを出そうとして空回りしたり… もう一度〝何を書きたい(表現)したいのか〟原点を見直された方が良いかも知れません。今期の入選作品は、特にバランスが良い作品を入選としました。しかし、実は、佳作の作品の方が、それぞれ〝狙い〟が明確であり、今後の展開がとても楽しみです。佳作にするか最後まで迷ったのは、涼見雄治さんの「豆電球」、加藤雅水さんの「音叉としての海、または、欠落する風の書物」です。また、今期八月迎えた〝戦後八十年〟をテーマにした作品、詩野悠人さんの「ゴーヤとキュウリ」、マーシーまつださんの「戦争って何、どうして」が印象に残りました。
【入選】
■ 八巻孝之 「耳鳴り」
日常をランダムに切り取り、シャッフルしたフォト・コラージュのような作品。造形的にはオーソドックスな手法なのですが、シャッフルする視点が、メスを執る外科医のように冷徹で鋭く、ピンポイントでメスを入れられた言葉たちが傷となって開き、あたかも連間から血が染み出して来るかのような… 詩でしか表しようのない〝痛み〟を感じました。
■ 杜梨乃 「香りの祈祷」
料理する行為を軸に、五感に訴えかけながら、〝わたしの不在〟を露わにする作品。〝神が死んだ〟世界で、取り残された贖罪羊の残影が、深い香りとなって鼻腔を突きました。
■ 催花亮太 「花火」
簡潔ですが、一語一語の響き合いが、とてもエッジが立っていて、リズミカルで鮮やかです。作者の夜を濡らす息遣いが耳元を掠め、きらめく情動が花開きました。
■ 牛坂夏輝 「トカゲの詩、あるいは恋愛関係」
構成については、連想に頼り過ぎていて奥行きがなく、少し難点があるようでしたが、今期の投稿作品の中では、最も〝質量〟(塊感・マッス)を感じました。暗い独房の壁に、血まみれの指先で爪を立て、刻みつけた言葉のような… 重い触感があり、孤独感が迫って来ました。
■ 緒方水花里 「リベンジライト」
ドットの集積であり、その場で好きなように修正可能なスマホ画像を、あたかも〝写真〟であるかのようにリアルタイムでアップしている現在… かつて、プロの写真家の間では、〝(ファインダーを)覗いて天国、焼いて(現像して)地獄〟と言われた、アナログ写真をモチーフに〝一発撮り〟したような手法。さて、白紙というフィルムに焼き付けられたアリスは〝天国か?地獄か?〟… 〝光と影の芸術〟を体現し、フォーカスもシャッタースピードもグッドタイミング!見事、逆光のリベンジライトに浮かび上がる、アリスのシルエットを捉え、ここが〝煉獄〟であると知らされました。
【佳作】
■ 中村太 「熱波」
今期について、入選作品のタイトルが少し焦点ボケしているかな(全作品ではありません)と感じていました。しかし、この作品は、タイトルをはじめ、トータルとして質が高く、特に〝・〟と〝間〟の使い方に瞠目しました。〝侘び寂び〟〝静寂と間〟という日本人特有の美意識(感性)をひと跨ぎして、〝ダイナミズム〟の時代が到来する… そんな予感を抱く作品です。
■ 中村憂 「刺青」
〝自分自身と対話する〟というのは、とても奇妙で複雑でありながらも、欠落と喪失感を伴います… その〝奇妙な欠落〟と〝複雑な喪失感〟を〝刺青〟に込め、肉体の内部へと下りながら、疾駆する地下鉄の空間とシンクロさせることで、〝内〟と〝外〟の境界が溶け合い、稀有な透明感がある作品となっています。
■ 三明十種 「in the 夕景」
泥臭いのにとてもポップ。振り切り感が良かったです。三明さんは、ざっくりとした触感が持ち味かと思っていましたが、シャウトとビートがストレートに刻まれて心地良かった。パンクでアナーキーであるなら、もっともっと振り切って、得意のざくざく触感を全面に出し、ノイズ〝ギリギリ〟でも面白いかも知れません。
■ 春日野あやめ 「パッカーしゃと ぬいぐるみ」
〝ことばのちぎり絵〟とでもいいましょうか… 言葉をちぎって貼り付けたような、辿々しくもありながらも、連間に深い奥行きがあります。目の前の現象に惑わされることなく、作者の視点が〝あるべき位置〟にしっかり収まっていて、技量を感じました。
■ しきゅう 「ストロングゼロ」
私は創作について、「〝素材(モチーフ)選び〟が九割、〝(詩を)書くという行為〟は一割」と考えています。そんな〝素材の力学〟だけで書き上げたと思われる作者の〝勢い〟、その〝勢い〟とは真逆な〝冷静かつ分析的な視点〟… その〝勢い〟と〝視点〟が、同居している点に可能性を感じました。
■橘麻巳子選評
□総評
詩のことを考えると、私自身から語れるものは未だほとんどなく、ここでは出会った人々のことばを少し紹介するに留めたい。
ひとつは「書いたものはみんな取っておいた方がいい」ということ。
もうひとつは「何人かに良くないと言われたからと言って、その作品を自分も良くないと思わなくてもいいのではないか」ということだ。
今でも、それらのことばを時々思い出す。
【入選】(3篇)
■芝眞帆『小鳥が死んだ』
「小鳥が死んだ」という印象的な行が繰り返されることで段々と抽象的なものになっていくのに、「あなた」の行動はリアリティを増し、ありありと想像できる。しかし、小鳥と「あなた」の一度目の偶然の出会いのひどさに、読み手はかえって安心してしまうかもしれない。これ以上、ひどいことはここでは起こらないだろうな、と。
最終連での驚きは、そのまま交通事故という出来事における衝撃と重なる部分が大きい。読み手はここで一気に急ブレーキを掛けたような変化に、この作品に引き戻されるだろう。
死、がやってくる時、そこに容赦というものはないだろうと思う。この作者もまた、人間の心を持つのと手放すのとの狭間で作品を仕上げたのかもしれない。現代のマザーグースとも呼べそうな、優れた詩だった。
■大西優佑『隣人』
「黄身」「から」「日々(ひび)」「絡(から)め」「割れた」「溶けた」等のことばは全て卵を表す要素と思われるが、考え抜かれた繊細さがある。細やかなことば遊びは前回からこの作者の特徴と思える。
「…」を挟んだ括弧は過去の記憶を想起させ、「隣人」とのやり取りの中のせりふではないのか、とも一瞬思える。そして、例えそうでなかったとしても、この2つのせりふは超現実世界を描くような状況にも読め、日常言語から丹念に外れている。
作品自体がある種のズレを持ちながら、意味を逸脱し続けているのだ。その端々は互いに編み込まれ、文様のようになって完成されている。
■永井雨『夏だよ といいたかった』
二連目にて空気が変わる。前連までのユーモアとはうって変わったような行き場のない緊張感を「じゃないと 真夏が危なかった」の一行がさらに奥へと誘う。
全体としてコラージュを思わせる変則的展開に前回よりも技術の高さを感じた。
最後の三行の空間の取り方は思い切っていて清々しい。「隕石さん/隕石さん/隕石日和だよ」というこのたっぷりとした三行と、「紙飛行機」が落ちたこととは関係があるのだろうか。「わたしはいまひとりでいる」、「二」、「三」の意味を考え、何か(またはわたし)が天から落ちたのだろうということ、視点が複数あるのではないかということを思った。「隕石日和だよ」と言うのは落ちておいでと呼びかけているのかもしれない。読むほどに可能性が増えていくという面白味を、この作者は短期間で獲得している。
【佳作】(3篇)
■岩下瓜『繋ぎ目に真昼は佇み』
構築や構成ということばではなく、もっとやわらかな、人間の手つきが感じられる作品だ。
語り手と母との関係や、現在それぞれがどのように暮らしているかといった事は、むしろ読む上で妨げになる想像のようにも思えた。この、ここにあるもの、語り手に訪れた思い出だけに身を任せてもきっといい。
「幼いわたし」は日に日に遠ざかり、記憶の中の姿は常に移ろう。電線の影もまた、真昼とその後では形を変えていくだろう。やさしさに包まれているようにも見える作品にふと隙間を感じて心惹かれるのは、そうした儚さの魅力なのかもしれなかった。
■三明十種『夏の翳』
旧字体や片仮名の効果が前回の投稿よりも増している。一雨、来そうだ、という一般的な言い方に対し、「(一雨、狂イさうだ)」と書く。狂いそうな状態の人間の頭は、時として通常時よりも多義性に富んでいるのかもしれないと思わせた。
「夏の翳」という、長い時間を要して見えてくるだろう対象を、実際頭が境界を超えるくらい観察したような、浮遊感が強く残った。
■あらいれいか『しょうめいたん』
ことばのイメージの集積が、想像可能な限界を軽々と突破してくる。これらのことばから浮かぶ映像は飽和し、加算され、打ち消し合って、それでも無意味を表すという方向性には行っていないように思える。「イメージを振り払っては継ぎ足す」と作品内にて書かれている部分があるが、この行為は作者が終わりを設定しなければ脳が働くかぎり続けることが出来るだろう。ことばがイメージとなり、イメージが更なることばを生む楽しみを、読み手は大いに受け取るだろう。
■根本紫苑選評
【入選】
嶋田隆之/「エリンギ」
晩ごはんの食材を選びながら昨夜のことを思う優しい人の姿が目に浮かぶ。夫婦喧嘩ってだいたい、つまらないことで始まって、謝るに謝れないまま時間が過ぎて、余計こじれたりする。話者の、謝りたい気持ちがエリンギを通して現れている。いろいろ悩んだ末に選んだ「エリンギは今夜ピーマンと炒めて/焼き魚に添えて出す//一言添えて出す」と終わる。この、最後の一連が好きだ。「仲良く並ぶエリンギを選びなさい」というらしい。本当にある言葉なのか、作者が作った言葉か分からないが、今後野菜売り場に立つときっとその言葉を思い出す。
こやけまめ/「からの臓器」
こころを返す代わりに、飲み干したコーヒーカップをみぞおちに入れる場面がおもしろい。ぽかんと空いたこころの空虚を、からの臓器として表現するのはとてもうまいと思う。単なる空虚より、そこに臓器があるのにからであることのほうが辛いかもしれない。コーヒーカップは、いい香りのコーヒーで満ちていたことを覚えているはずだから。だけど、こころも、コーヒーカップも返さなければならない。最後は、なにもなくなったみぞおちが内側から抉れてことばが初めて出てきたと締めくくっている。空虚を何かで満たそうとしないで、さらに内側から抉れてことばにしていくところが詩人らしい。
横山信幸/「水影」
長年一緒に暮らしていた家族が、だんだんその人ではなくなることを見守るのはとても辛い。変わってしまった妻のことを、「君が透きとおった」と表現できるのはすごいと思う。変わってしまっても、家族であることに変わりはなく、変わってしまったことを受け入れて、胸の奥の虹について考えようとする。「誰にもおもねらず、うそもほんとうもなく/内側を透きとおらせて、わがままに、」透明な水のようになってしまった妻の影と夫の影が重なり、虹となってほどける。透きとおった→透明な水→透明なレンズ→光を屈折させる→虹、だから、妻の影は虹を落とす。言葉の選び方も、虹という視覚的要素も愛情に満ちている。
鈴木和則/「影を踏む」
「死は生がつくる影さ。だから、生が消えれば死も消えるんだ」と、言い、「自分の影が薄いことに気づかされた」、定年退職後の「私」と「元同僚」。酔いが回り、「生きるとは、しょせん、戯れさ。死という影の影踏みあそびなんだ。どう生きようとそれ以外に意味はないんだ」と言う。確かに、生きるも死ぬも、ひとりの存在に対して、意味はないかもしれない。ただ、友人と酒を飲み愚痴る今が、妻に先立たれて悲しんでいる今があるだけ。年を取り、家族や友人がひとりひとりあの世へ行ってしまい、自分も後先短いことに気づいたとき。何ができるかといえば、きっと何もできない。影踏みあそびで、戯れるしかない。
加藤雅水/「音叉としての海、または、欠落する風の書物」
語りかけるような口調で始まるところが良い。「海がね、うん/あの裂けた音叉だったんだよ、ほら/…それが、ぼくの声を、/ぶつ切りにしてくるのさ」この一連がなかったら、すっと詩の中へ入っていけなかったかもしれない。音叉とは音の調律に使うらしい。その音叉が壊れていたら、まともに調律ができない。海とは、声とは、そして風とはなんなのか。ひとつの解釈としては、海は情報の海や書物の海。途方もなく広い、知識や文化や文学や世界のいろんな情報で満ちている、図書館や、インターネットではないかと思った。あまりにも膨大な情報はむしろ読む人を惑わせる。狂わせる。声を上げる気力を奪い、黙らせてしまう。風の強い海辺で、いくら叫んでも何も伝わらないように。
【佳作】
公園/「鳥」
意味は言葉になった瞬間、確定してしまう。そこに留まってしまう。言葉にした瞬間、伝わってしまった瞬間、言葉以上は伝わらなくなってしまう。そのさまを、鳥と、空を区画してしまう電線でうまく表現している。しかし、伝わらなければいいと思う反面、伝わってほしいと願ってしまう。愛の告白も、詩を書くことも、同じだと思う。止まっていながら、鳥は、どこまでも飛び続けていきますように、と願いたい。
妻咲邦香/「バス停」
どうしてバス停だろう、と思った。「私」は「あなた」が好きで、実はどこにも行かないでほしい。ずっと「私の温もりの中で」「永遠にあなたは待ちぼうけ」してほしい。でも、それなら、バス停になりたいという願望はおかしい。バス停で長居する人はそうはいないから。恋人になりたいでも、「あなた」が身にまとうかポケットに入りそうなものでもよかったのに、バス停だとずいぶんと距離感がある。でも、見守るだけで距離感を保ちたい関係かと思えば、仔猫とじゃれ合い顔を近づけたらそのすきにさっと入れ替わりたい、とある。この矛盾だらけのところが、恋ごころであり、この作品の魅力かもしれない。
嶋田隆之/「蛇口」
長年使ってきた蛇口が壊れた。それを見ながら、話者は自分の怪我や病気を思い出す。なんとか骨をくっつけてもらい、手術をしてもらい、家族に腕をもんでもらいながら、年を経て暮らしてきた。人の身体に取り替えのできる部品なんかない。直しながら付き合うしかない。でも、むしろ、代替部品がありそうなのに、古い型だからって、蛇口は治らない。「で お前は直らんのか くっつかんのか」、「で お前はおしまいか 縫ってもらえんのか」と嘆きながら話者は取り外された蛇口を見下ろす。身体の衰え、老いや、その先にあるものを思い、私も黙って蛇口を見送りたくなる。
小川尚子/「イカナゴ」
イカナゴの釘煮は春の風物詩らしい。食べたことはないけれど、この詩を読んだらおいしそうに思えてきた。孫に作り方を教えようとする祖母とのやり取りが描かれている2連が良い。ユッサユッサ鍋を振りながら、「ちょっと来なさい、見ときなさい/これくらいで振るんやから/よう見ときなさい」と、孫がどんなことをしていても声をかけてくる割には、作り方は勘だけで目分量なところがおもしろい。祖母が一年かけて準備した春のお知らせ。それを受け取っていた親戚や友達はきっと、ずっと春の味を忘れないだろう。
杜梨乃/「祖父の辞書」
祖父の部屋から見つけた古い辞書がある。それは、祖父との思い出でもあり、祖父から受け継いだものでもある。それは、辞書というより、家族の生きてきた歴史や記憶や思い出に違いない。それを大事に覚えて、まとめて手で拾い上げているのが、この作品だ。少々散漫なところもあるが、祖父に日本語を教わる場面の2〜3連は良いと思う。祖父の辞書の続きを、ぜひ書き続けてほしい。