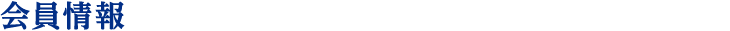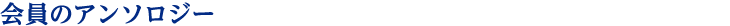会員のアンソロジー8・河津聖恵氏~
河津 聖恵 カワヅ キヨエ
①1961(昭和36)1・9②東京③京都大学文学部独文学科卒⑤『神は外せないイヤホンを』『ルリアンス』思潮社、『アリア、この夜の裸体のために』ふらんす堂。
プロメテウス――尹東柱に
加茂大橋の欄干にもたれ 夏の北山をのぞむ
(白い闇を抱え)私は帽子をまぶかに
〝死ぬ日まで天を仰ぎ〞と呟く小さな人にな
る(誰もみない)
遠近法よ 揺らげ……
(緑は故郷のように近づき 水は未来の北方
を青く映す)
光、光、絶え入るすべての至福と哀しみ そ
の明るみ……
詩人が恥じ 慕わしく消した名〝童舟〞も静
かに蘇る
この冬 春の幻のようにあなたをふかく知っ
た
〝私を呼ばないでください〞という遺言に逆
らい
プロメテウスと名付ける あなたを知ってゆ
く私を
川中子 義勝 カワナゴ ヨシカツ
①1951(昭和26)7・22②埼玉③東京大学大学院(修)修了④「地球」「嶺」「ERA」⑤『遙かな掌(て)の記憶』土曜美術社出版販売、『ミンナと人形遣い』沖積舎、『ものみな声を』土曜美術社出版販売。
カササギのいる風景
街道が国の境にさしかかる小高い丘のうえ遠く入江をのぞむ心地よい眺望の片隅に
画家はひっそりと立つ絞首台を描いた
目をこらすと横木にカササギが止まっている
画家がついに描かなかった鳥の啼く声を
耳にした者はいつの時代の誰だったか
こわごわと目を伏せ背を向けながら
ときに激しく怒号の礫を投げながら
傍らを数多の人々が通り過ぎていった
だが時の移ろいを越えてすべてのものを
通り過ぎたのはむしろその絞首台であった
遠く風景遠近法の収束する辺りから
峠道に散る小石を跳ね上げる勢いで迫り
夜を趨り抜けていったのは誰の声だったか
日ごと増し加わる時代の奔流から免れようと
詩人は喧騒を逃れ度々この地を訪れたが
詩人が愛して身を寄せた樫の巨木ではなく
埋もれた銃剣が風に応えようとしている
詩人がついに記さなかった風の声を
歴史の五線譜を区切る小節線のように
ひとり聴き止めたのはその絞首台であった
①1942(昭和17)3・5②山口③広島女子短期大学国文科卒④「Griffon 」⑤『青いカヌー』書肆季節社、『こっそりサンバ』あざみ書房、『テストの時間』『かいつぶりの家』思潮社。
一本煙突
岬の一本煙突の火葬場は廃業になりました
真っ黒い煙突はそのまま立っています
父も母も そのまた父も母も
あの煙突から煙りになって消えたのでした
わたしはあの日の様が忘れられません
岬の突端には昔から
三本松が立っています
入り江のこちら側
父が残したみかん畑から眺めていると
三人の人が手を引き合って
海から上がってきたようにみえます
父はどんな気持ちであの煙突を見ていたか
老いていく今 電話で聞いてみたいです
夕暮れ時はたましいが帰ってくるのでしょう
ねぐらを求めてたち騒ぐ鳥たちに混じって
ひたひたと 忍び寄るものの気配が
確かに聞こえます
川原 よしひさ カワハラ ヨシヒサ
①1933(昭和8)6・10②兵庫③法政大学社会学部応用経済学科卒④「新現代詩」⑤『カーキ色のトランク』地球社、『ひそかの記憶』知加書房、『白い三拍休止』土曜美術社出版販売。
光源を見極めたい
むし暑い遠歩きに一息入れた
無住の草堂にゆれる灯は
ウルシの匂いもするが
追手の餓鬼共をまいた蛍か
いや 迷い人を誘う幽鬼か
夕闇を詰めてゆれる
堂内は幽霊船のようだ
ちぎれる灯はホタルイカの波乗りか
とても現在地をさとす灯台とは思えない
生ぬるい畦道にぬけ出ると
三〇センチほどの光の尾が走り
思わず追いかけ 立ち止まった
霧闇に一点の光を探しあてたからには
その光源を夜明け前に見極めたい
たとえ誘く負の星であっても
川村 慶子 カワムラ ケイコ
①1922(大正11)6・20②北海道③北海道教育大学卒④「日本未来派」⑤『復刻半生』銅林社、『土偶の頬』書肆青樹社、『馬』日本未来派。
生命 讃
あなたは若い時独りであった
結婚しても妻に病まれ独りであった
妻病んで十五年 死して十五年経ってのち
別の女を妻に迎えた
だがその女も病後であったと知って
落胆を隠せず 壊れた人形のように号泣した
三十年を共に暮らした
夫は頑迷なにして 妻も頑迷な
その間女は花を育てたけれど
男は庭に立って眺めることをしなかった
今 逝ける男は少なからざる蔵書を残した
世に言う限定本・稀覯本のたぐいである
泪を拭いて披き見 積み重ねる
戒名の蘭皐院で呼んでみる 蘭皐院樣ァー
こんなにも豊かなものをたくさん頂いている
この身体の底の方から満ちてくるものは何だ
生命・讃 生命 讃 だけである
苅田 日出美 カンダ ヒデミ
①1938(昭和13)②岡山③就実高校卒④「四土の会」「サヴァ」⑤『空き家について』手帖舍、『川猫』あざみ書房、エッセイ集『きょろきょろ目玉とうさぎの耳』吉備人出版。
からくり
時代劇で
悪人が吊り天井の茶室などこしらえて
邪魔な殿や水戸黄門を謀殺しようと
たくらんでいるという
おなじみのからくり
素人にはわからない
細かな装置で
気づいても容易には止められない
そんな仕掛けがいつのまにか
あなたとわたしの天井裏に
動きはじめているのだけれど
どうしても止められない
その位置さえも
知っているのに止められない
菅野 拓也 カンノ タクヤ
①1936(昭和11)3・10②福島③多摩美術大学美術学部絵画科卒⑤『海』『緩やかな季節』自費出版、『博物誌』大阪フォルム画廊、『薔薇園』求龍堂。
沈黙する球体
サッフォーからの春の便りが届いた朝
木々の繁みを流れる時間の緩やかさと
身体を吹き抜ける風の愛撫が
私をくつろがせる
魅惑の唇が豊満な言葉を湛え
獣性を取り戻そうと試みる午後
鳥の素早さで森へ消えていくものがある
密やかな肉のわななき
壊れやすい時間
砕け散る光
無機質な狂気
人間はなぜ愛し憎しみ合うのだろうか
なぜ傷つけられたら傷つけるのだろうか
愛することに飽きたから憎み傷つけるのか
その果てに殺し合うというのか
溢れ出ようとするのは水ではなく
雲や木や鳥の言葉だ
だがやがて鳥を飛び立たせる闇が迫ると
すべては安らかな加護の世界に閉じ込められ
もはや沈黙する球体となって
大宇宙の暗黒に浮かび上がるのだ
菊田 守 キクタ マモル
①1935(昭10)7・14②東京③明治大学文学部日本文学科卒④「花」「鳥」⑤『かなかな』『一本のつゆくさ』花神社、『仰向け』潮流社、『新篇菊田守詩集』『妙正寺川』『夕焼けと自転車』土曜美術社出版販売。
土筆橋
冬の日の夕ぐれ
土筆橋の上に立つと
西の空に
大きな鯨の形をした雲が
ゆったりと浮かんでいる
鯨の細い目のところから
夕日がのぞいていて
夕日は後光になり
鯨は光り輝いている
見ていると
鯨の後ろから
夕日が顔を出した
鯨の下の卵黄の太陽
妙正寺川に夕日は零れて
金色の細い帯になって流れている
菊地 勝彦 キクチ カツヒコ
①1932(昭和7)7・24②宮城③福島大学卒、慶応義塾大学中退④「飛地」⑤『夏草異聞』思潮社、『最前線へ』青磁社、『ミスキャスト』東京出版、『フィクション』書肆山田、評論『晩翠・省吾・亀之助』アステップ。
風
風はいつどこで生まれるのだろうか
そして
果敢に変貌を繰り返し
一つの最期にどんな花を見届けようとするの
だろうか
人々が行方を知らされず乗せられた列車の窓
をいっさんに叩いた
アウシュビッツの雛罌粟
人々が爆風に耳を削がれ青空の茸雲に目を剥
いた
ヒロシマの向日葵
人々が石畳に膝を折り半壊した鳥居に頭を垂
れた
ナガサキの蒲公英
しかし
世界はすべての音や生命の気配をすっかり消
して血塗れの造花でいっぱいだ
菊地 貞三 キクチ テイゾウ
①1925(大正14)7・19②福島⑤『奇妙な果実』昭森社、『ここに薔薇あらば』『いつものように』花神社、『詩に触わる』書肆青樹社、『蛇がゆくように』花神社。
夜明けに
天空の白むにつれ
宙に浮き立つずんべらぼうの壁
くろぐろと傾く地球の横っ面
先刻からあの岩肌にとりついて
蓑虫のように身をよじる
独りの男のロック・クライミング
あれがきみにせよぼくにせよ
巨いなる稜線の意志の前で
すでに祈りの声をのみこんだまま
ぼくらはただみつめるばかりだ
明けてゆく永劫のうねりのなかの
ちいさないのちのめざす先が
希望の輝きであるか失意の闇か
だれにも告げることはできない
(福島民報紙平成19年元日、新年詠)
菊池 敏子 キクチ トシコ
①1936(昭和11)8・30②大連③下田南高校卒④「展」⑤『紙の刃』紫陽社、『ポキポキ』花神社。
素敵な質問
今年の夏はことのほか
よく雨が降りました 雷も鳴りました
ひとりで家にいると 雷鳴と稲妻は
私だけに向けられた強烈な敵意のようです
雷から私が見えないように
まっ昼間から雨戸を閉め カーテンを引き
雷の癇癪が治まるのを じっと待ちます
ある日のラジオ番組の
夏休み子ども科学電話相談で
こんな質問をした子がいました
「かみなりさんは なんびきいますか?」
おもわず頬がゆるみました
そうか 雷さんは生きものだったんだ……
雷の科学的メカニズムはひとまずおき
私だったらどう答えよう――と
知っている限りの怪獣など思いうかべ
ちょっと楽しくもなってきて……
いらい 雷雨注意報が出されるたび
「さあ 何匹でもかかって来いっ!」と
やたら威勢よくなるのです
①1957(昭和32)10・28②岩手③宮城教育大学卒④「山毛欅」「地球」⑤『今 という時間を』野火の会、『一度見たものは』花神社、『すすきの原 なびいて運べ』思潮社。
返信
りんごの実が紅くなると
虫たちはもう鳴かない
くらい山かげ
刈り取られた稲
過ぎてきた街の明かりに向かって
走っていく
わたしたちは種なのだから
手元からこぼれてしまうことも
さようならが言えないことも
伝えたかった言葉
そこから先をめくる指先
重すぎるほどに揺れている青葉
陽射しを浴びて木々が立ちつくし
わたしたちは種なのだから
運ばれていく
地上にも
その向こうの空にも
菊池 柚二 キクチ ユウジ
①1932(昭和7)7・13②宮城③東北学院大学英文科卒 早稲田大学大学院演劇専攻④「舟」「青い花」⑤『森へ』『木々も草々も花々も』書肆青樹社。
幼年期
いちまいの葉っぱに全宇宙が投影している
そういったひとがいる
ほんとうだろうか
そうなら虫食いだらけの葉脈のどこかに
わたしのいのちが見え隠れしている
ついでに喜びや悲しみとか
そんなちっちゃいものたちも
葉っぱにしがみついている
ほんとうだろうか
森へ行くたびに葉をいちまい千切る
今日うっかり落した葉を踏んでしまった
全宇宙が消えて
その一瞬わたしは存在しなかった
たぶん
こんなことがいつまで続けられるのだろうか
菊地 隆三 キクチ リュウゾウ
①1932(昭和7)5・15②山形③東北大学医学部卒④山形詩人⑤『鴉のいる風景』『待つ姿のエスキス』あうん社、『夕焼け・小焼』『父・母』書肆山田。
へ
〈いろはにほへと〉より
へのへのもへじのような
いきかたをしてきた
きばれば
へしかでなかった
のろくさのろま のんべえの
のぼせのたれめだ
だんごはなよ ものはなよ
あおばなたらさんで
もっといいはなさかんか
さかん さかん
へのへのもへじのうらがわで
いつもこっそりゆめみてきた
はずかしいはずかしい
きれいな はなのゆめだ
きさま いまわらったな
くちがへのじにまがってるっていうのかい
へのへのもへじでもいい
おれのいのちだ
いのちの部(へ)だ
つべこべいうな
へ
岸本 英治 キシモト エイジ
①1939(昭和14)11・29②福井③近畿大学法学部法律学科卒⑤『魂の河』思潮社、『残り火』『母の国』私家版、『岸本英治詩集』芸風書院、『夜の屋根の上』思潮社。
母が逝って
影が
枕元にやってきて
枕を揺り動かす
背中をたたく
なかなか眠れない
しばしば目を開ける
深夜
影は声を落として発っていった
声をゆっくりゆっくり拾いながら
夜が明けた
岸本 マチ子 キシモト マチコ
①1934(昭和9)11・29②群馬③中央大学経済学部卒④「鮫」⑤『那覇市場界隈』『コザ中の町ブルース』『サシバ』『えれじい』『ヒミコ』『花でいご』花神社。
たたかい
詩を書くという事は
一種のたたかいでもあるといったのは
誰だったか 確かにそれは社会というより
傲慢でけちで嘘つきで浪費家で怠惰な見栄張
りの自分とのたたかいなのかも知れない
この間も
「鹿尾菜ってなあに」と聞かれて困った
「ええっ 鹿の尾っぽの菜っぱですって?」
ろくびさい鹿尾菜 おかしいどの字引にもな
い
農業協同組合は?
「あのー鹿の尾っぽの菜っぱというのですが
えっ分かりませんか そうですかありがと
うございました」
そうだ漢和字典! 鹿の十一画
いちか八か引いてみる
あった海草の一種ひじき 菜っぱじゃない
なあんだひじきかあー
こんな事も分からないなんて
ろくでもない自分に腹が立って腹が立って
涙が出た
北岡 淳子 キタオカ ジュンコ
①1947(昭和22)1・3②長野④「白亜紀」「未開」「ERA」⑤『生姜湯』書肆青樹社、『サンジュアンの木』『アンブロシア』土曜美術社出版販売。
夏
仰向けに蟬がおちてくる 下草刈りの済んだ木陰は姿を隠すものもない 死にゆく様を
みごとに晒して差しのべる手を拒む もはや
何ものも不純なぬくもりに過ぎないのだ 枝
枝からは絶え間ない蟬時雨が降りしきる だ
が とむらいの声明ではなく生きるいのちの
唄 私の小さな犬よ 複眼に映える無数の空
を侵してはいけない
やがて星々の雫が蟬の羽を濡らすだろう
虚しく星を映す眼からついと流れて 草の葉
にきらめいておちるだろう 幾度も朝がきて
あるとき 日常の足が忘れられた屍を砕く
だろう そうして犬の嗅覚にも留まらずに命
の跡は消される 私の小さな犬よ みごとな
野の死を私たちは見たが 蟬よりもむごく
名前ごと砕かれて今も呻く魂たちの夏がある
言葉の届かない夏がある 身のうちを灼か
れながら かなしみの眼をしずかに注ぐ夏が
ある
夕刊
聞き漏らしたのは 明け方
河底からいっせいに草魚が跳ねあがった音
大きな地震にみまわれた中国・四川省
倒壊した校舎の 互礫の下で息絶えた少年は
固く手の中に 一本の鉛筆を握りしめていた
(文明は気を失っているのですか?
いえ いえ 血の匂う町のずっと遠く
一面に咲く芥子の花に見とれているのです
私は新聞をめくりつづける 探しているのは
鉱石のような手が虚しく掻いた土ではなく
棒●!*
キャンデー売りがこぼしていった滴
飢えた野犬が大きな円を描いて近づく地平と
私は少しもかかわりがないけれど
まちがっていたい
いのちがこんなふうに写し取られた紙の裏で
北川 有理 キタガワ ユウリ
①1951(昭和26)8・21②香川③東京大学文学部卒④「火牛」「庭園」⑤『ベンゼン環のエクリプス』思潮社。
あしぶみ
なかば透きとおった鍵束が
海馬を闊歩する夜明け
眼のすみで音もなくはじけるものがある
ありもしないテリトリーをはじきだされる
感触は雪原の夜のようになじみやすい
あるいはとても簡単なことかもしれない
ある日ある刻を境に
どこの誰でもなくなるというのは
「しばらくぶり。どちらに」
かさならない顔と名前と関係が
闇のほころびから沈んでくる
壁のしみから雨の記憶がしたたるように
「遠いところに。ようやく
解放されました(自分から)」
回収されない悪意の
あやふやな句読点をたぐり
指間をすりぬけるなにかを
あやうく光芒と言いくるめ
踏まえることも踏み潰すこともままならない
言霊をひっそりと
迎え撃つ
北川 れい キタガワ レイ
①1932(昭和7)9・26②東京③岩手大学学芸学部卒④「焔」⑤『ママンの木』『蓮台野』Láの会、『花の郵便』『托鉢の朝』土曜美術社出版販売。死神
「来るな、来るな」と
亡母が手を振った
ぼくは川を渡ることが出来なかったよ
意識の戻った夫がいう
それで
あなたが生き返ったわけが分かった
お母様が押し返して下さったのね
美しい花の野も
流れる広い川も見て
帰ってきた人の側にいる今日の平安
でも 何時か
「おいで、おいで」と招かれる
働き続けた姑の大きな手が
熊手のように広がって
わたしたちを引き寄せる日
その日は何時
怯えるわたしに
柱に寄りかかっていた
白装束の死神が笑った
北畑 光男 キタバタケ ミツオ
①1946(昭和21)7・23②岩手③酪農学園大学酪農学部卒④「撃竹」「歴程」「雁の声」⑤『死はふりつもるか』『文明ののど』花神社、『救沢まで』土曜美術社出版販売、『足うらの冬』石文館。
雪ひらのうさぎ
高原の牧草地には/光が吹き渡っています
牧草の海のはるか向こうには
船がうかんでいます
牧草は/海の波のように
つぎつぎと光をはこんでいます
私はトラクターに乗り
光を刈りたおしていきます
音もなく光はたおれ/影をつくっていきます
そのなかに/からだを刈られたうさぎがいま
す/うさぎは
かすかにけいれんしたまま息絶えていきます
私の手のなかに/うさぎの濃い影がうつって
います/夜になると
くらい海のなかに散る夜光虫のように
星がまたたいています/うさぎの魂です
うさぎのことだけを思っていると
星は雪ひらになって
私の海のなかにふってきます
ふかい海の底の方へ
雪ひらになったうさぎがふってきます
北松 淳子 キタマツ アツコ
①1932(昭和7)1・2②宮城③東北大学文学部史学科卒④「青い花」「方」⑤『存在の童話』芸風書院、『群青色の譜』土曜美術社出版販売、『見えない城』『河童の祈り』『時間の忘れ物』書肆青樹社。
長月
きみは黒曜石に化身して
海峽を丸木舟で渡った
脊梁山脈の青い足が石化し
森の木々が冷気に反応するとき
北国の魂が少しづつ前進する
戦いの気配は見えないけれど
トリカブトやウバユリの狼煙があがる
雲のスフィンクスは慌てて
謎々の形態と色彩を太古の辞書に聞く
持つことなく織るタピストリー
星の扉に寄りかかる四季と
大地の壺を手にしたきみの祈り
鮭や熊や鹿 狐や猪の
現象界の生き物が
たどたどしく生死の姿を謡う
きみは黒曜石になって
三界にあふれる水を注ぐ
北村 真 キタムラ シン
①1957(昭和32)1・3②兵庫③静岡大学教育学部卒④「詩人会議」「冊」「飛揚」⑤『群居』『休日の戦場』『始祖鳥』視点社、『穴のある風景』ジャンクション・ハーベスト。
返書
遠い場所からやってきたのだから
住所は記されてはいない
一瞬のあいだに通り過ぎたのだから
ことばにならなかったのだろう
深い場所へ砕けていったから
まなざしのような光だけが残されている
だから 哀しみの水槽をくぐり抜けた光跡を
醸造酒のように時間をかけて
翻訳しなくてはならない
目を閉じ暗闇の中で
その手紙を読み終えたなら
あの人たちがしたように
太陽のもとへ返さなくてはならない
北村 均 キタムラ ヒトシ
①1946(昭和21)6・15②愛媛③広島大学政経学部経済学科卒④「火皿」⑤『自虐的終章』炎社、『ことばと影』春陽社出版。
注意信号
ギャー
と思いがけない音を残して
車は止まった
信号は注意信号
突っ走ろうと
アクセルと踏み込みかけたが
視界の端に白バイが過ぎった
スーと横に並びこちらを伺っている
止まったのだから文句はあるまい
私は素知らぬ顔で前方を見ている
コンコンと警官がドアーを叩く
目の前は向日葵畑
「何か」
「ちょっと道の端に寄ってもらえませんか」
「何故です」
「ここ、一方通行です」
チョット待って チョット待ってよ
目の前は向日葵畑
入る前に教えろよ
あんた ずーと付いて来たのじゃーないの
木津川 昭夫 キツカワ アキオ
①1929(昭和4)10・28②北海道③旧制中学卒④「火牛」「青い花」「日本未来派」⑥『迷路の闇』砂子屋書房、『掌の上の小さい国』思潮社。
大泉学園界隈
練馬の大泉学園のわたしの散歩道には
牧野富太郎博士の記念庭園やミニ牧場があり
野性がまだ少し殘っていて楽しい
水の少い白子川に乱舞する燕を見て
橋をわたり 遊歩道を行くと
市街地の中に浮島のような牛舍があり
そこに二十頭余りの乳牛が飼われている
針槐の白い花がしきりに風に散り
針槐の白い花がしきりに風に散り
こぼれた飼料に山鳩が群らがっている
狹い牛舍をのぞくと 人影はなく
繋がれた牛たちの淋しい目が睨んでいる
いつの間にか牧場の大部分が駐車場になり
車が乱雜に溢れ 牛の憩う場所が少ない
満月の夜 わたしは騒々しいので
舌を切られた 可哀相な牛たちを想う
橘田 活子 キッタ カツコ
①1942(昭和17)11・6②東京③慶応義塾大学文学部国文学科卒⑤『花粉』山梨働く文学の会、『神ドノのおヒルネ』甲陽書房、『にぎやかな哀しみ』朝日新聞出版サービス。
汚れた手(二〇〇八、五、十二、四川省大地震)
崩れおちた巨大な瓦礫のなかから
いっぽんの手
ペンを握りしめたまま この子は
このぺンでどんな未来を描いていただろう
にんげんの
十本の指をもつ手
さまざまなものを摑み捨ててきた
おいしかった時をたべ
食べ過ぎた魂は弱虫になり
未来の夢も金庫の中で鎮座させられ
とおくにちかくで
かくされたじぶんの欲望と偽善は
抱きあい信じられている
じぶんの眼に届かないわずかな欲望が
暮らしのなかに汚れていく
じぶんの手
災害は
いっぽんにほんさんぼん……と
汚れた手を炙り起こしていく
絹川 早苗 キヌガワ サナエ
①1937(昭和12)7・7②福岡③慶応義塾大学大学院修士④「いのちの籠」⑤『空の卓』『海嘯』『マダム・ハッセー』ふーずの会、『紙の上の放浪者』土曜美術社、『レクイエム』『独り居の記』『林の中のメジロ籠』横浜詩人会。
みずうみ
みずの うみは つぶやくだけみずから あらあらしく
さわぎたてる こともなく
やまや のの うでに いだかれ
むねの おくふかく ひっそり
いのちを まもっている
みずの うみで くらすものたちは
しおからい ことばを はっせず
あれくるう かんじょうも
ほとばしる おもいも
みずからの りんかくの なかに とじこめ
けはいだけを たちのぼらせる
わたしの なかにある ちいさな みずうみ
みなもに ゆめみごこちの ボートをゆらし
それは
ひとり しんかんとした ときにだけ
すがたを あらわす
①1932(昭和7)1・25②鹿児島④「嶺」「地球」⑤『風の中のボタン』こだま詩社、『ガラスの中の季節』C.P.P.『軽い九月』的場書房、詩と詩論集『魚歌』作家社、『レモン色の光』舷燈社、『海』『葡萄色のパピヨン』横浜詩人会。
やがて深い冬
二十年前にあなたと歩いた真夏の
朝霧高原 今車で走っています
想いは はがれ はためいて
遠い日の木立の中にふるえています
沢山の言葉をまき散らして過ぎた旅の日々
折々の風の匂いまで あふれてくる
幾度か私たちを佇ませた風景 今
鮮やかに息づいている
ずっと昔に私自身を葬ったはずの想いが
遠く はるかに あふれてくる
湖の水際 小さな漣
今 空は あまりに青く空は秋を感じている
あの日よりも一層美しく
時間の中に迷いこんでしまった
人生の夕昏れは 音もなく
地上から空へ向って昏れてゆく
深い闇の中に絵が溶けてゆく
①1932(昭和7)4・5②朝鮮③徳島大学工業短期大学部中退④「地球」「隊商」⑤『少年のいる風景』『故地再訪』キャラバンサライ社。
胡天西方詩鈔
スーヴェニール
ホータンは西域では唯一の玉の産地として知
られた所だから
妻には白玉のなかでは夙に珍重されるという
羊脂玉のネックレスをひとつ
娘たちにも同じものをそれぞれ
息子には白玉の杯を一対
これがこの旅のスーヴェニールだ
それらを鞄に詰める
傷まないよう柔かい紙に包んでつめる
詰めながら想う 往古此処を通過した旅人も
やはり家郷の親族に同じものを求めたであろ
うことを
そして駱駝に着けた旅嚢の底に
同じ様に丁寧に仕舞ったであろうことを
結局千年を経ても人間の営みはそんなに変っ
てはいないことに
その時漸っと気が付いて苦笑する
そして納得する それでよいのではないかと
客舍の外はポプラ並木に真夏の陽射しが眩し
くて
出発にはまだすこし時間が残っている
木村 和夫 キムラ カズヲ
春を待つ顔の
霜に枯れた赤い草や木の葉に埋もれ
蒼白いものの虫たちや
草や木の根たちは
土に深く閉ざされたままの魂で眠っている
そんな山の斜面の乾いた畑原に
強風は黒煙を立てて吹き荒れているが
そんなところにも
太陽は優しい光をそそいでいた
いまだ寒気が
盛んに働き掛けている地上には
枯れ草ばかりがはばを利かせていて
黄緑の葉の萌え出る声は
あまり聞こえてはいないが
寒気に羽を広げる太陽の
その光を過ぎる木立の音に
春を待つ顔の瞳が潤んでいた
木村 恭子 キムラ キョウコ
①1945(昭和20)5・17②岡山③岡山朝日高校卒④「くり屋」⑤『ノースカロライナの帽子』詩学社、『あざらし堂古書店』三宝社。
植木屋さん
夜のどこかで
まだ剪定が続いている
町内の人は
夕刻には家の前を通って帰って行ったと言う
又別の人は
角の店で床屋談義をしていたと言う
別の町内の人は
仕事を終えると
向日葵の種子を数える子供の宿題を手伝い
町の外まで
時計の調子を直して歩き
林の麒麟を眠らせてから
そのあと
静かに脚立をたたんだと言った
木村 大刀子 キムラ タチコ
①1937(昭和12)5・4②愛媛③尾道短期大学国文科卒④「蘭」⑤『風とわたしのうた』流域発行所、『砂の音』『ある朝、いつものように』蘭発行所。
諫早 一九九八
ここら辺りですよ、と言われてタクシーを
降りてみると、堤防の向こう側は茫々と広が
る草の海である。
ドミノ倒しのように、巨大なギロチンがつ
ぎつぎと落とされたとき、大地のあげた鋭い
悲鳴。水しぶき。干涸びて罅割れていた干潟
や、息絶えだえのムツゴロウ。繰り返しテレ
ビに映し出されていたあの情景はどこにも無
く、風も、もう潮の香を運んでは来ない。
一度殺された干潟では、今、きらめく真夏
の太陽に向かって、緑の芽が、堰を切ったよ
うにわっといのちを噴き上げているのだ。人
間の思惑などどこ吹く風。大地はすでに新し
い神話を紡ぎ始めているらしい。荒ぶれる雑
草のことばで。
いつの間に集まって来たのか、生まれ変わ
りの赤トンボたちが、干潟の死を見届けに来
た私たちの頭上、透きとおる瑠璃の空をしん
しんと旋回している。
木村 迪夫 キムラ ミチオ
①1935(昭和10)10・9②山形③上山農業高校卒④「山形詩人」⑤『まぎれ野の』『マギノ村・夢日記』『いろはにほへとちりぬるを』書肆山田。
夜も昼も
桜桃花の季節が訪ずれると
村の男たちは眠れない
夜半冷気に身をさらしながら樹から樹へと
駆けめぐる
あたかも夜鷹の眼のように
凍てつく気圏を凝視しながら
狼火のごと 弄りながら 火を放つ
炎は燃える桜桃花のことばを聴きながら
夜明けを迎えてなおしとぶることもなく
赫あかと樹のおもいを照らしては
次第にのぼる陽のなかへと溶けていく
起きよ 蜂よ
眠らない男たちの根気にならって
飛べよ 蜂よ
肌色艶やかな身をおどらせる 村女のように
わが村の
むかし夜這いの寓話に託された
(小さな恋人たち)の
結実のために