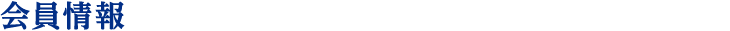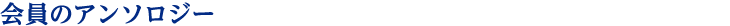会員のアンソロジー13・髙橋喜久晴氏〜
髙橋 喜久晴 タカハシ キクハル
①1925(大正15)2・18②静岡③専修大学卒④「幻」⑤『見知らぬ魚』狼の会、『日常』詩学社、『中世喩法』『中世覊旅歌』樹海社、『巡礼記』思潮社、評論集『詩の幻影』花神社、評論集『薔薇と落暉』遊々窟。
独楽――回転の極みは
独楽は
懸命な回転を試みる
めまいすら透きとおってしまう悦楽のときを
求めて
よろめきつつさぐった定位置
足のきっさきを鋭く大地につきさし
稔りをあげてしばしの回転陶酔
おだやかな季節のうつりかわり
和顔愛語がとりかこむゆたかな風景に囲まれ
れば
懸命必死も次第にゆるやかな表情をみせる
ゆらぎゆらぎなかまとの別れの挨拶をかわし
ついに訪れる横転
こころ静かに 迎える大地との交歓
その浄福の歓びもわるくないが
いま一度 居ずまい正しく試みる
純粋停止ともみえる激烈回転の極み
逆転の秘儀
夢見る死のごとき透明な生
落陽の中の独楽の せめて優雅な
ダンディズム
高橋 玖未子 タカハシ クミコ
①1954(昭和29)4・3②青森③弘前大学教育専攻科(心理学)卒④「飾画」「青い花」⑤『けもの落とし』路上社、『アイロニー・縫う』書肆青樹社。
群生の中で
何も考えない人のように立っている樹
深く黙考するように見える木々
樹と対峙するとこちらの思念が透かされる
その落葉松は
山の中腹 杉林の中に
二本連れ添って立っている
親子 姉弟 夫婦かは知らぬが
常緑樹の中に孤立して
季節の移ろいを鮮明に浮き立たせている
みんなとは違う特異な個体 際だつ個性
人の世では
時に差別を生み迫害さえ受ける口実が
山の生態の中に
優しさと厳しさと共に包み込まれている
季節はゆるやかに秋に向かい
銀色に染まりだした針葉が風に揺れる
その樹の一角を通るたびに
削げかかった心の破片が戻ってくるのだ
高橋 重義 タカハシ シゲヨシ
①1944(昭和19)4・11②福島③福島大学教育学部卒④「卓」⑤『天の音楽』『秋のぴあの』『雲のおるがん』『夏の栞 秋の栞』私家版。
螢
宵闇の田園に
数知れぬ螢の影を追って
満天の星明かりに迷いこんだあの夏
蚊帳に放ったすくない螢のふたつ みっつ
闇に点る青磁色のともしびに
母と子は行く末をいかに案じたか
朝になれば
いのちを消しとめてしまうはかなさを
ただ手探るようにしてひそかな涙をこぼした
あれは こころの奥に
螢火のように点るものがあって
憶おもいはいつも青い夜道を還っていったのだと
高橋 次夫 タカハシ ツギオ
①1935(昭和10)5・12②宮城③岩ヶ崎高校卒④「竜骨」「鮫」⑤『鴉の生理』時間社、『骨を飾る』近代文藝社、『搔痒の日日』書肆青樹社、『孤島にて』土曜美術社出版販売、『雪一尺』竜骨の会。
春のエスキス
――あるいは 詩の 骨格のための――
遅刻
福寿草の 陰の 微笑
*
なのはな なのはな
カナカナ蟬の 殻の 幻聴
*
桃の花の玉子が 萼を割って 産まれそうだ
少年の 教室の 黒板
*
谷合の村が ひとつ 花に消えた
翡翠の影が ひとつ 瀧に消えた
*
ふきのとう ひとりの物言い
炭焼き小屋に 忘れられた 薬缶
*
マンサクは 思考の海を さすらう
やがて 黄砂の嵐
*
吹雪の 巣に灯る 蠟梅
試練 血の 骨格のための
高橋 昭行 タカハシ テルユキ
①1930(昭和5)8・4②栃木③旧制県商卒④「柊」⑤『禁猟区』『わが魂は地底に燃え』『立証』落合書店。
倒木に挟まれた夕陽に
枯れた木の向こうに 罅割れた太陽がある
閉ざされた扉には バラが絡まっている
花弁は密かに散り急ぎながら
しかも優しく諌めているようだ
起こりかねない 凩を
豪雨の袋を背にもつ 乱雲たちを
堀り返せ 愛と懺悔の埋まった土塊を
引き出して 火焙りにしよう
傲慢という名の蚯蚓を
己は 時代遅れの 驢馬なのか
否々 糞尿に塗れて匍い出し
その尻に止まっている 蝿なのか
時には巨大な死体の上で
時には アフリカ孤児の睫毛に纏い
戯れている 身の程知らぬ蝿たちよ
倒木に挟まれた夕陽にむかって
両眼をぎらつかせた 一匹の蝿がいる
高橋 優子 タカハシ ユウコ
①1948(昭和23)7・7②栃木③日光高校卒④「POISSON」「Who’ s」⑤『花頸』言葉の会、『鏡』現代文学刊行会、『冥界の泉』沖積舎、『薄緑色幻想』思潮社、『薔薇の合図シーニュ』天使舎。
刻印
幾重にも咲き沈める花房の下を歩む。雨に
濡れて、流れゆく時間は異なった輝きを秘め、
肩に滴るこれらの花房が、寒さのなかでひら
く今の花と知っていながら、かつての花びら
の冷たさに顫え、遠く隔てられてありながら、
ひとつの冷たさが貫いて、ふっと私の今を喪
わせる。
身をのべて、思念の縁へと漂いでる花房の
薄片に纏わる他者の影。それら白濁した花び
らの襞に潜む他者の魂の呻きが、外界へと滲
み透って、さらなる過去へと私を置き去りに
する。濡れそぼつ呻きに、ぬけ殻となった私
の声はいっそう微かに、花びらは絶え間なく
腐蝕し、無音の底に散りしいてゆく。
昏さのなかに仄明るむ過去の水位に沈みな
がら、束の間交りあって消えていったはずの
時の流れが、あたかも揺籃であったと、そう
呟いた唇の冷たさが、逃れがたく私の感官に
触れる。互いにひた隠しあった苦しみの、見
えない真綿のような花房の連なり。けっして
消えない刻印にも似たあれらの時間…………
髙原 木代子 タカハラ キヨコ
①1931(昭和6)1・25②福島③棚倉髙女卒④「の」「地球」⑤『山繭』書肆青樹社、『夕暮れの厨房』土曜美術社出版販売。
ピオーネ
新年のたより初秋のたより
お目にかかることもなく何年もそうして
あなたとは生きていることを確かめあってき
たものでした
秋が見えてきた頃あなたにピオーネを送りま
した
十日程して運送屋さんから電話がきました
該当する電話番号に連絡がつきません
そう言えば残暑見舞に返信はなかった
知人に尋ねたところ七月に亡くなられたとか
ひっそりと逝ってしまった人よ
運送屋の倉庫でピオーネは崩れてその日わた
しの夢も崩れた
抗うことも選ぶことも出来ず
或る日たしかにわたしにもその日は来る筈
この秋のわたしの思いは深く
赤紫のピオーネは哀しい色になりました
高松 文樹 タカマツ フミキ
①1926(大正15)1・3②和歌山③陸軍経理学校卒④「PARNASSIUS」「日本未来派」⑤『時計』『こころと霊』『空無』思潮社、日英対訳詩集『時間』(TIME)POETRY in Nippon。
体内時計
1965年
ドイツのユルゲン・アショフ教授が
ヒトの体内時計の周期は
1日25時間と発表した
ヒトは朝起きて
10万ルックスの太陽光を浴び
体内時計を1時間早くリセットし
太陽の運行からの体外時計
24時間に調和させ
生体時計を保ち 生体リズムを作っている
1997年10月
東京大学の程博士は
ヒトの第17染色体には
時計の遺伝子があることを発見した
知らず識らず
ヒトは大きな宇宙のリズムに同期し
幸せの日常を深い永遠のいのちに
繋いでいる――。
田上 悦子 タガミ エツコ
①1935(昭和10)8・30②東京③日本女子大学附属高校卒④「詩人会議」「檪」「飛天」⑤『とうとがなし立神』飛天詩社、『はなれ里の四季』詩人会議出版、『女性力』コールサック社。
人間
最後まで残った 敵対する飢餓の兵士二人
互いに銃剣を向け合っていたが
同時に バナナ一本 目の前に発見した
分けあって食べてから
また銃剣を相手に向けるのだった
――で
まめ
皮もやぶれずに
照りよく煮上がった豆を
一粒づつ箸でつまんで口に入れた
豆のことをかんがえながら
たて続けに十粒くらい入れた
嚙むと中味が口中にあふれた
「まめ」と 言った
高見沢 隆 タカミザワ タカシ
①1957(昭和32)10・26②長野③桜美林大学英米文学科卒④「ティルス」「歴程」⑤『Night Down』『宙の鬱人』思潮社。
不動の恋
静まりきった風景にあぶら蟬の鳴き声が回
転している 汗が陽炎の深淵に滴り落ちて声
は竜巻のように天を駆けめぐる わたしの鼓
膜には小刻みに震える蟬の翅が呼吸をとめ張
りついている 難聴のなかで大木に囲まれた
丸い石畳を歩く 歩いてゆくと幻視の神社に
たどり着く そこには夏の神が奉られている
のだ なぜかわたしの皮膚は失神して風景に
象嵌される 「涼」という文字を鳥居にな
ぞってみる すると神社の扉を開けて巫女た
ちがわたしの足元に打ち水をはじめる その
うちの一人が輝く陽炎となり手招きをする
わたしは招かれるまま神社に入る 丸いしか
も永遠に奥行きのある空間を感じる どこか
らか声が響いてくる なぜ否定する(され
る)のか それは世界を肯定することを学ぶ
ためだ
わたしは実在と虚構の淵に揺いで存在して
いる 遠くで雷鳴の音がする あぶら蟬の鳴
き声が反転している わたしは淵の光を浴び
ながら擦り切れた翅を震わせ不動の夏と恋を
つむぐ
高安 義郎 タカヤス ヨシロウ
①1946(昭和21)5・18②千葉③明治大学農学部卒④「玄」「ホワイト・レター」⑤『次元鏡』東京学芸館、『むかし むかし』昭和図書出版、『母の庭』ごま書房、リーフノベル集『逢魔が時』五月書房。
河原コスモス
芽ぶいたひと株のコスモスを
河原に見つけて
支柱を添えた
秘密めいた秋風がたったころ
かろうじて残った花は
色あせていた
手折られた跡がある
どんな花器に飾られたろう
あるいは
占いにちぎられたのか
世界時間の異なる僕には
花に尋ねる術もない
足もとに夕日がひたり
河岸にさざ波がのたる
コスモスの花びらが一枚
時間の欠片の
ように波に浮いていた
いつしか脳裏に
無数の花びらが降りかかり
高柳 誠 タカヤナギ マコト
①1950(昭和25)9・13②愛知③同志社大学文学部卒⑤『卵宇宙/水晶宮/博物誌』湯川書房、『都市の肖像』『月光の遠近法』『触感の解析学』『星間の採譜術』『廃墟の月時計/風の対位法』『鉱石譜』書肆山田。
*(水の面の月と中空の月)
水の面の月と中空の月
二つの月は互いを照らし
聴こえぬ音楽を心に響かせる
互いが互いの鏡となって
いつまでも光を投げ掛けあう
目にもあやな闇のうちに
光の柱が浮かび上がり
月長石の柱が浮かび上がり
心騒がす光の音色が響きあう
心狂わすものと心清めるもの
二つの月は互いを照らし
闇のうちに月宮殿を浮かばせる
あえかな光に漂う月宮殿
廃墟の月宮殿は漂い 浮かび 流れ
月長石を通した光を
地上の闇へと送り届ける
その青みがかったあえかな光が
心を騒がせ 心を鎮め
二つの月に心は千々に砕ける
水の面の月と中空の月
心狂わすものと心清めるもの
高山 利三郎 タカヤマ リサブロウ
①1948(昭和23)3・2②栃木③早稲田大学国語国文学専攻科修了④「へにあすま」「青い花」⑤『かくれんぼう』七月堂、『ブロッコリーの疾走』書肆青樹社。
花々
五月の空を撹拌する
ねじれ合った雲と
舞え上がった夢が
混じり合い沈殿する山躑躅
晴れた日は勝手口から非日常へ
怠惰な坂を転げ落ちるのもいい
誰も見ていないからといって
油断してはならない山帽子
夕暮れがせまると堰を切ったように
飛び立つ小鳥の群れ
天空で輝きはじめた星達と
溶け合いながら落花する小手鞠
夜が明ければ
たっぷり水を張った水田に
深緑色の苗が並び
五月の水田は賑わう
今年も畦道には
燈明のように花開く黄菖蒲
高良 勉 タカラ ベン
①1949(昭和24)9・1②沖縄③静岡大学理学部化学科卒④「KANA」⑤『岬』海風社、『サンパギータ』『絶対零度の近く』思潮社、『僕は文明をかなしんだ 沖縄詩人 山之口貘の世界』彌生書房。
喜界島望唱
一度も行ったことのない 喜界島
いつも奄美空港から
はるか海上に望んでいた
DHCプロペラ機は飛ぶ 激しく揺れながら
台風の渦巻きのヘリを
北上せよ台風 波よ静まれ
きかい 喜界
かつて「鬼界島」と表記され
恐れられていた島よ なぜ
何度も遠征しながら 敗北を重ねた
琉球王国侵略軍 何故
島の港は 形状は どのようにして
グスク(城)へ登るのか
いま島の歴史が
一枚一枚発掘されつつある
その地の霊へ
しかしチャーター船は出ない
うねりは私を寄せ付けず
はるかに望唱する
白い波の華にかすむ
喜界島よ
財部 鳥子 タカラベ トリコ
①1933(昭和8)11・11②新潟③小学校卒⑤『わたしが子供だったころ』私家版、『腐蝕と凍結』地球社、『中庭幻灯片』『烏有の人』『モノクロ・クロノス』思潮社、『胡桃を割る人』書肆山田。
水郷――十九行の詩を求められて
葦の葉を舟が擦り切っていく音がする
わたしはどこへ行こうというのだろう
――ここが十九行ときめられた詩の入口
わたしの髪の毛は水にひたされている気配だ
よどんだ水の匂いが立っている
(どこか奥深い場所で……)
馬の蹄があらあらしく葦原を倒していく
一斉にたなびいているのは甲冑の武者たち
(どこが戦場か……?)
雄叫びし 魂切るもの いななくもの
そこへ埋もれていく者たち
赤い箙が宙に浮き
しばらく葦の折れる音が続いて
やがて血が消え
音が消えた
水底を覗くと
しずかに一輪の紅い蓮が浮いてくるところ
舟べりから手を伸ばして
わが知らぬ想い出を折りとった