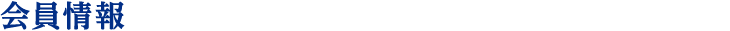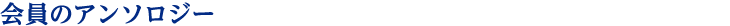会員のアンソロジー22・前川 幸雄氏~

前川 幸雄 マエガワ ユキオ
①1937(昭和12)4・25②福井③国学院大学大学院(博)④「青魚」「詩彩」⑤『青春哀歓集』印美書房、『杭州旅情』土星社、『田奇詩集』朋友書店、『西安悠遊』土曜美術社出版販売。
蟬が鳴く
ミーン ミーン ミーン 蟬の声に思うのは
八十路の母が語った あの唄のこと
十七、八の娘盛りに 輪になって踊りながら
即興で 掛け合い 唄ったものだという
来ては抱きつくあの大木に 泣いて別れる
あら 夏の蟬
さまよさまよと 呼び出す声は お花畑の
あら 蟬の声
恋いに焦がれて鳴く蝉よりも 鳴かぬ螢が
あら 身を燃やす
可愛らしいわいの 螢の虫は 闇の夜に出て
あら 灯をともす
山家で出会った父母の青春を思う……
父が先立ち 母が逝って二十七年
父母の年にはまだしばらく間があるが……
ミーン ミーン ミーン 空気を揺るがし
悔い無きように生きよ と 蟬が鳴く
ミーン ミーン ミーン 残年を惜しんで
命の限りに生きよ と 蟬が鳴く
前田 新 マエダ アラタ
①1937(昭和12)11・26②福島③大沼高校農業科卒④「詩脈」⑤『貧農記――わが鎮魂』歴史春秋社、『秋霖のあと』土曜美術社出版販売。
醗酵する思想
このごろ
行くのではなく
帰るのではないかとしきりに思う
オクタビオ・パスは時間が
血のなかを円環するといったが
ぼくがいま見る。未来とおぼしき光景は
凄まじい人間の殺戮の過去だ
石斧の人を鉄剣が剌し貫き
槍の騎馬隊を銃弾が撃つ
そしていま、核兵器をもつ侵略者の欲望が
支配を秩序といい、偽りの平和を口実に
世界を恫喝して席巻する
ぼくはその直線的な未来に絶望する
だから、このまま行くのではない
否定し、始源に帰るのだ
ぼくのなかで醗酵する思想に
死がゆっくりと熟成する
前田 嘉代子 マエダ カヨコ
①1941(昭和16)7・5②東京③文化学院卒④「さやえんどう」⑤『讃美歌』『プラハ』紫陽社、『赤い貝穀』花神社、『土の声』紫陽社、『祝砲』花神社。
恋人
小さな喫茶店に
午後の陽射しが満ちて
道行く人々の影が
走馬灯のように淡い壁を巡る
ガラス越しの景色は夏のなごりの茂み
かすかに虫たちの声も聞こえる
草の実がはじける
窓辺で本を読むひとがいて
ときおり白いカップを口に運ぶ
店主はいつも真剣にコーヒーを淹れる
妻はパンドラの箱に鍵をかけて
新しい恋によじ登る
ぽっかり
空が写った心に
草の実がこぼれる
昼時の泡立った空気も静まり
店主は午後の昼寝です
前原 正治 マエハラ マサハル
①1941(昭和16)6・10②宮城③早稲田大学英文科卒④「地球」「開花期」「撃竹」⑤『緑への風見』『光る岩』国文社、『独りの練習』石文館、『魂涸れ』書肆季節社、『詩圏光耀』土曜美術社出版販売。
こおろぎ
――成田敦さんへ(鎮魂歌)
凍りついた時空で
それでも
一匹のこおろぎが目覚める
その声は
しずかにふかく
世界にひろがっていく
その光る触角を
暗黒の夜に濡らし
あの世とこの世の融け合う
懸崖までせり出し
息絶えだえに一匹のこおろぎが
ひとの身代りに
せつなく世界をうたう
そのはかなさを そのうつくしさを
歌は
世界をふるわせ
世界にしみいっていく
そして
世界も
ふいに息をとめたこおろぎになる
槇 さわ子 マキ サワコ
①1939(昭和14)3・7②東京③梁川高校卒④「地球」「福島自由人」⑤『般若』あぶくま詩の会、『月夜のアトリエ』土曜美術社出版販売、『祝祭』ふらんす堂。
天空の飾り
連れ立って山の斜面をくだる
谷底に近いところまで降りて
藤の古木の根方で休んだ
沈黙を振り切るように手を伸ばし
木の時間の深さに触れる
ざらつきごつごつした木肌から
木の温かさが伝わってくる
やがて春がくれば青々と若芽が育つ
葉のあいだから天空の飾りのような
花房の重なりが宙にさがるだろう
古木であればあるほど
花穂は濃い翳をはらんで咲く
人の時間にも
芽吹きと結実の時が
くり返し訪れる
あなたとわたしのこころにも
のぞきこめば眩む深さで
花が咲いたこともあったではないか
恋人よ
牧田 久未 マキタ ヒサミ
①1948(昭和23)4・9②京都③慶応義塾大学文学部卒④「地球」「RAVINE」⑤『やわらかい石』土曜美術社出版販売、『13月・目撃』書肆青樹社、『うそ時計』角川書店。
つじつま
つじつまあってないといけませんか
生きてないとだめですか
死んでないとだめですか
それは罪ですか
それは悪ですか
それは悲しみですか
きっちりしないといけませんか
あやふやなまま明日を迎えてはいけませんか
昨日はきっちりとかたづけないとだめですか
いまでもなく
さっきでもなく
ちょっとあとでもなく
ありのままを
見つめていてはいけませんか
何も決めないまま
明日を覗いてはいけませんか
牧野 孝子 マキノ タカコ
①1939(昭和14)3・31②樺太④「日本海詩人」⑤『夢だんだら』思潮社。
千年婚
ある日
ともに暮らす おとこの
喪のはがきが届く
しみじみと ときにひたされ
古い時計が
十三時をうつ
そのうち おんなも
そんなはがきを書いたような
気になって
たぐり寄せる糸ぐちから
ちろちろ焚かれている
送り火に
ときおり 照らし出される
ふたつの貌を
ぼんやり 遠くに眺めている
牧野 芳子 マキノ ヨシコ
①1926(大正15)4・22②愛知③第一高女高等科卒⑤『航跡』詩と詩人社、『北の薄暮』『精英樹』国文社、『ある週末』築地書館、『アミエルの歌』詩学社、『白鳥橋』花神社。
ヌイの歌
音もなく小春日和の庭に現れ
水浴びをはじめた若いトラツグミの
全身に鏤められた黒い三日月
しげしげと辺りをみまわし空を仰ぐ
落武者のような虚無の目
銜えた小さなヒサカキの実
照葉樹の森かげに
いまも残る黄金の時間
越冬の日々も終わりに近い早春
オリオンの傾く夜明け前のひととき
美しい装いに秘めたおまえの寂寥の笛
胸にしみるその音色を
ヌイ*よ
きかせてくれるだろうか
今年もひそかな旅立ちのまえに
*「ヌイ」はトラツグミの方言(愛知)
眞下 章 マシモ アキラ
①1929(昭和4)3・7②群馬③小学校卒⑤『豚語』『神サマの夜』紙鳶社、『赤い川まで』沖積舎、『いろはにこんぺと』紙鳶社。
影を叩く
誰も見ていないからと
鉄のこころで叩きのめした
叩いて叩いてたたきのめした
これでもか これでもかと
コトバを捨てて叩きのめした
なり振りかまわず叩きのめした
一本のパイプになって叩きのめした
己れのこころを叩くことができないから
己れ自身のこころの影を叩きのめした
いきり立つ獣のこころを叩きのめした
声もなく蹲るものを叩きのめした
死ぬかもしれぬと叩きのめした
饐えたるこころのいたずらを
逃すものかと叩きのめした
死んでもいいと叩きのめした
叩きつかれて気づいたら
枕のそでが濡れていた。
増岡 敏和 マスオカ トシカズ
①1928(昭和3)12・11②広島③法政大学予科卒④「詩人会議」⑤『広島の女』あゆみ出版、『飛ぶ種子』ベルデ出版、『光の花』日曜舎。著書『八月の詩人』東邦出版。
茜の少女
――二人の妹の在りし日のこと
幼い妹が てんまり突いている
友だちはもういなくなって
妹の鞠一つ てんつく夕日を撥ねている
台所から母の呼ぶ声が上がると
勉強中の姉がよい返事をして
妹を迎えに出る
妹は顔のようなてんまり抱え
姉にうながされ
夕餉のにおいの這う露地に歌を合わせる
――安寿恋しや ほうやれほ
靜かなデュエットが翳を曳いて
ああ いまはむかし
夕日が山の端を染めるころ
茜の少女は
川を渡り雲に乗り
あの夏に消えた
呼びに行く
*亡姉=原爆死した私の上の姉・当時13歳
増田 耕三 マスダ コウゾウ
①1951(昭和26)1・20②高知③東洋大学法学部経営法学科卒④「兆」⑤『村里』『バルバラに』。
ココ
裏庭の片隅に眠る小鳥 ココ
おまえが死んでから多くの時間が過ぎたね
墓石がわりの四角い石がぽつんと
置かれているのみだが
ときおり通りかかると
おまえに呼びとめられた気がして
私は土の下からとどく
鳥のさえずりを聞こうとする
瓦礫まじりの陽のない場所に射す
懐かしい夏の陽射し
家族みんなで名前を決めて
そして次第に家族の一員となった
六年、七年がまたたく間に過ぎ
やがておまえはいなくなった
あれは何だったのだろう
どのような時間であったのかと私は考える
やがておまえは羽化するように
ふたたび私の庭から
飛び立ってゆくのだろうか
松井 潤 マツイ ジュン
①1960(昭和35)3・13②長野③東京理科大学理学部・北海道大学経済学部卒④「火曜日」⑤『宇宙の年齢がわかった日』『利己的な秋刀魚』『デジタル生活入門』花神社、『恐竜の思想』新風舎。
かたち
かんじ変換のもみじ
照葉。五裂に 鋸歯
指のさき 血に染め
空に透かし ひとときに
へんげ。生の 死の 帯びて色
山 山 山 の時間
紅葉。かたち残し 去り
うつわには書 手に
染まり 帯び ぎざ
ぎざひろがり 赤に黒
紙を透く 世界褪せて
あり 透いて かな変換に
もみじ。いちまいずつ 修羅に葉
鹿ケ峰 鷲ケ峰 天ケ峰
生 白く染まり 枯れ
手相。葉 葉 かたち踏み
飛び はじけ 水しぶき
雲に絹。窓またたき 道きら
めく 長刀鉾町 立売中之町
御旅町 坂のぼる下る
松井 博文 マツイ ヒロフミ
①1942(昭和17)4・11②広島③東京外国語大学英米語科卒④「火皿」⑤『ブーメラン』芸風書院、『旅をする記憶』土曜美術社出版販売。
果樹園
この先に果樹園がある
それは林檎であったり
葡萄や梨であったりするだろう
色も形も味も違うだろう
だがそれらは確かな「物」であるはずだ
そして
わたし達が進む道は同じだ
ああ 美しい果実達
それらはどのようにして
成熟に至るのか
わたし達は結果しか知らない
そして何よりもまず
結果こそ偉大なのだ
あの林檎 あの葡萄 あの梨
その果肉 その果汁 その現前
言葉が「物」となるために
わたし達が進む道は同じだ
この先に果樹園がある
松浦 成友 マツウラ シゲトモ
①1958(昭和33)4・21②東京③横浜市立大学国文科④「鮫」⑤『風と光のレジェンド』土曜美術社出版販売、『影のレミニッセンス』詩学社、『空のマチエール』書肆山田、『フラグメントの響き』書肆青樹社。
器 と外部
滑らかな諧調へと進む 外部を欲する内質よ
その光沢と波打つ曲線の中へ時が忍び込ん
でいく この器の内部には木質が稠密に織り
込まれ 抱えるものは空虚でしかないのだが
器という形式は内部に閉じられていながら
過剰なほど物体の贈与を望んでいる しかし
この器には時間も空間もありとあらゆる存
在の解釈が内在化されてしまい 盛り込むべ
き物象が見当たらないのだ
器の底には悲しみが隠されている その中心
から広がっていく同心円の重なりと 次第に
傾度が高くなる斜面へもたらされる青い斑模
様よ 赤茶色の縁取りが大きな輪を描くとき
外部にようやく開かれた器の花が咲き乱れる
のだろう ここに置かれるのを望むのだ あ
えて苦しみを選ぶ者のように指定され 器の
重心へと落ちていく 気付かないほどの瑕疵
をも許すまい 白光が照り輝くこの地を
松尾 茂夫 マツオ シゲオ
①1937(昭和12)8・24②兵庫③関西学院大学文学部英文科卒⑤「すてむ」「別嬢」「現代詩神戸」⑥『ナルヴィクの太陽』VAN書房、『松尾茂夫詩集』土曜美術社出版販売。
海の今昔
海辺で育ったので
小学生のときから伝馬船なら櫓で漕げた
漁師の息子の同級生と
海から河口を遡上してみたり
沖に沈んだ難破船を探険した
ぼくらは遠浅の海に飛び込み
饅頭貝という掌ほどの円い貝を
バケツ一杯捕ったりしたが
中学生は沖合いで蛸を手摑みしてみせた
手慣れた
小船を突堤に繋ぎ止めては
クロネコ一丁のほぼ丸裸のまま
海辺で遊び呆けた遠い日の記憶
いまは巨大化した
イージス艦やらタンカーが
自動操縦で東京湾や明石海峡を闊歩する
――雀の子そこのけそこのけ御馬が通る――
海の大名行列が蹴散らしていく小船
松尾 静明 マツオ セイメイ
①1940(昭15)3・3②広島④「折々の」⑤『都会の畑』『丘』『地球の庭先で』『詩と童謡 子どもがひとり』三宝社。
キャベツの癖
曲がりくねったもの片寄ったもの真っ直ぐで
ないものも
巻き込んで じっとしていると
いつもあること きまっていること になっ
てしまう
すでに 癖になっている
青筋のたった頑固な美学も
内側へ内側へと主張を巻き込んでいくことが
外側をふくらませるのだと知っている処世の
脱がせにくい幼児のパンツを剝くように
剝いていくとやがて現れてくるものが
傷つきやすい不逞な僕の芯であることも
すでに 癖になっている
松尾 真由美 マツオ マユミ
①1961(昭和36)7・8②北海道③札幌大谷短期大学音楽科卒④「ぷあぞん」⑤『密約――オブリガート』『彩管譜――コンチェルティーノ』『睡濫』思潮社。
なお秘めやかな岸辺の患い
白昼にあってもまた
闇のある渚である
あたたかな空隙にかこまれ
日のかがやきに手足をさらし
およそ従順な地の上に立つ
そのような描線をえがきつつ
ひそかに瓦礫を溜めこんで
損傷を隠している
ひどく醗酵する渦の
これは諦念と倫理
物狂おしくうごめいて
埋没する語をもとめていた
だれにも見えない湿度だから
いつも明るい明日をむかえ
まるで波打ち際で戯れる子供の
けたたましい景色をまねく相関図に
晴れやかに接続し柔らかな容器をつくる
おそらくは無為の行為のほとりの塵芥
ひろびろと海原へ
消え去ることを
願っている
松岡 寛 マツオカ ヒロシ
①1928(昭和3)3・1②北海道③旧制向島工業卒④「時間」「眼」「湾」を経て現在は所属なし⑤『死者の門』昭森社、『松岡 寛詩集』芸風書院。
カロンの舟唄
しずかに裂ける雲
毒のまわりきった空にたのしくたれ
尖った馬がながれ 扁平な家具がながれ
ねじれた顔をふりあげ考える芦がながれる
プラスチックの血をしたたらして
舟べりにとりすがるたくさんの掌
スキマがほどよくなくなれば
あまった掌を容赦なく断ち切って発つ
すべて始めのまえに終りがあり
舟が終りをまちうける
たとえばナイロンの長靴下をたぐりあげ
「火のくちづけ」をくちずさみ
やせぎすの肩をすりよせてくる舟
冷えながらいつも罪をのせ罪をゆすぶる
このかなしい容器には罪の産めない罪がある
ひかれてはならないその唇の青さに
おもわず胸をふるわせよ
眼をいからせ舟脚をはやめる
いやだわあたしテレビもないそんな処
だけどおまえもう電気椅子はないのさ
過ぎ行く者たちの唄はたあいない(後略)
松岡 政則 マツオカ マサノリ
①1955(昭和30)5・13②広島③加計高校卒④「すてむ」⑤『金田君の宝物』書肆青樹社、『草の人』思潮社。
山地口琴舞
遠い島の
赤の部族
両の?に入れ墨をした老婦たちが
ルブを鳴らしながら舞っている
麻で織り染めた南洋の文様
遐遠な集団の記憶
我執はない
無垢、というのでもない
ただ人を人たらしめている裡なる光が見える
精霊オットフに捧げる舞
その影、の勁さ、
不意の桃色。
戴いた絵葉書を見ているだけなのに
血くだが熱くなる
うしろの山が迫ってきて
ルブの
タロイモの白い花
遠い島の
赤の部族
*ルブは台湾タイヤル族の竹で作った口琴。
松沢 桃 マツサワ モモ
①1948(昭和23)11・7②三重③宇治山田高校卒⑤『風の航跡』土曜美術社出版販売、『予感』書肆山田、『鏡の屈折率』書肆青樹社、『青ぶるーぷらねっと惑星』砂子屋書房。
島嶼
ひがのぼる すなどるひとのひたいに
ひがしずむ たがやすひとのひとみに
あの日以来 人々は無口
畑は家は 暮らしがこわれた
洪水 塩害 空から小石
破れ網 朽ちかけた船 櫂
孤立する 痩せこけた ホッキョクグマ
溶けはじめた氷河 ツンドラの凍土
エル・ニーニョ ラ・ニーニャの発生
温暖化の科学的データ 警告のニュース
海面の上昇 消える浜辺
直撃する現実が 先をゆく
逃れゆくのか 他郷へと
赤道直下 海抜四メートル
かたをよせあうのきした のぞみはいずこ
ひとひこうべをあおげば くものぼひょう
松沢 徹 マツサワ トオル
①1918(大正7)②富山③高岡商業学校卒④「北国帯」「木々」⑤『空気のなかの家』黄土社。
夏草刈り
裏の空地で草を刈っていると、
家の中で老妻の呼ぶ声がする。
「お父さんー」と二声三声。
急に何の用事かなと思う。
だが私は手を休めない。五十余年共に暮して
きた歳月の声が胸内に谺している。しかし
応えない。
――仕事が終ったら、聞こえていたよ、と言
えばよいとした。
汗を拭き、更に草むらへ進んで行く。
第11詩集(二〇〇七年刊)
『羊の小さな蹄の跡』より
松下 のりを マツシタ ノリオ
①1929(昭和4)10・23②岐阜③旧制工業学校卒④「さちや」「ガニメデ」⑤『羞じらう樹魂のように』土曜美術社出版販売、『佇むひとの』銅林社、『忙中閑』竹林館。
大樹
がっしりと岩をかかえた大樹
根を張ることすらむずかしかったであろうに
なんと命の強さよ
やさしさは岩を這い
まるごと咬みしめるように
生きる方向をまっすぐ立て
伸びつづける大樹
樹の智慧であろうか
根元を
風雨に耐え
雪の重みにも耐えつづける存在
その場所から動くこともなく
天にむかって呼びかけてきた
長い年月
何があったか
何を見たか
これからも黙して語らないのか
大樹よ
松田 研之 マツダ ケンシ
①1932(昭和7)9・18②岡山③日本大学文学部中退④「詩人会議」「道標」⑤『彼岸花のオード』りん書房、『ねぶかの花』詩学社、『夕陽のスポット』本多企画。
地上から少し浮いたところ
地上から少し浮いたところに
場所を選び、高さや向きを決め
粘着力のある糸で、年輪の形に網を張る
張り終えたら、真中に位置して待つ
水滴が網を白く顕わにする朝も
日光が溶かす昼も、ひたすら静止して待つ
獲物がかからなければ、その血を
己れの血にすることができない
地上から少し浮いているのだが
網は地上と切れてはいない
木と木に張り渡した数本の糸によって
辛うじて、だが確かに地上と繋がっている
今、傾く陽を浴びて網が煌めいている
ゴミと見紛うブヨのむくろや
木の葉をくっつけて
網を繕っているのか
張り替えているのか
松林 尚志 マツバヤシ ショウシ
①1930(昭和5)1・29②長野③慶応義塾大学経済学部卒⑤『H・Eの生活』無限社、『木魂集』書肆季節社、『古典と正統』星書房、『日本の韻律』花神社、『斎藤茂吉論』北宋社、『芭蕉から蕪村へ』角川書店。
馬酔木の花
吾背子にわが恋ふらくは奥山のあしびの花の
今盛なり
奥武蔵の朽ちかけた御堂のほとり
清楚な花を一杯につけた馬酔木が咲いていた
私は古畑に?を摘みにきた昔男
万葉の乙女が匂い立つ馬酔木の花を前にして
私の身体にも春が蘇るようだ
激しい恋を経た初老の歌人茂吉は
遠い逢瀬を前にして箱根に命を養っていた
茂吉の前にも咲き匂う馬酔木の花があった
茂吉に蘇ったのは甘美な恋の日々であったか
目合はけだもののように哀しい
馬酔木の花はたかぶる心を鎮め
果てしない幻のごとき連想へと誘ったようだ
彼方の壁の上にはマグダラのマリアが現れ
城壁をくぐる駱駝の列が現れる
そして幻は木の芽を急がせる春雨のなかにし
めやかに包み込まれてゆく
花の咲く
すらふごとし
松村 信人 マツムラ ノブト
①1949(昭和24)8・9②高知③関西学院大学文学部日本文学科卒④「凶會日」「イリプス」「別冊関学文芸」⑤『光受くる日に』矢立出版、『伝承』樹林館。
一行の言葉
書架に並ぶ思いのつまった本の群れ
一行の言葉さえつかみきれば
全てを無くしてもいいと思ったことがあった
その言葉を糧に生きていくことができればと
今ある書物が全て焼き払われようとも
体に残る一行の言葉さえあればいいと
――凄まじい空中の火花だけは命と取り換え
てもつかまえたかっ
と書いた天才作家のひそみに倣って
その後も本は増えつづけ
整理に明け暮れる
一行の言葉は浮かびかけては消え
うす暗くなった部屋の片隅に
愛猫が黙して私を見つめている
*芥川龍之介『或阿呆の一生』より
松本 昌子 マツモト アキコ
①1930(昭和5)10・17②大阪③豊中高女卒④「七月」・「アリゼ」「おたくさ」⑤『庭』文童社、『浮遊あるいは隅っこ』詩学社。
夏休み
ポプラの葉がきらめく
そよ風に
くるくる回っている
海から戻ると
ハンモックで微睡む
潮の香と
陽に灼けた 腕や肩
皮膚の匂い
蟬の声
驟雨のあとに架かる夕虹
やさしく暮れて行った日々よ
小さな
わたしから消えようとしない
其処に
帰りたくて 詩集を開く
遠い果樹園に
星が瞬きはじめる
松本 一哉 マツモト カズヤ
①1923(大正12)4・8②大阪③京都大学法学部政治学科卒⑤『サーカスの女王』私家版、『死んだまね』山河出版社、『鳥の論理』黄土社、『中原中也論』山河出版社。
放生記
一、 A寺
長い階段下に少女が一人立っている
小雀二羽を詰め込んだ
しかし真新しい籠を数十箱置いて
參詣人は
何バー
かを支払い
それを空へと放つのだ
二、 B寺
砂利敷の參詣道の傍らに
小亀を十数匹盥に入れて老婆が坐っている
參拜者は
何バーツかを支払い
その一を道に対向する池に放つのだ
タイ式放生の一型式。
①ワット・サケート(黄金の丘寺院)(バンコク)
②バーツ――タイの通貨単位。一バーツ=四円
③ワット・ポーチャイ(ノンカーイ)
松本 恭輔 マツモト キョウスケ
①1935(昭和10)8・9②東京③小石川高校卒④「新日本文学」「中庭」「新現代詩」⑤『響きの逢い引き』土曜美術社出版販売、『曲がり角には子どもも猫も』編集工房ノア。
端午の節句に
端午の節句 詩人の命日 その名は
楚その国を 愛するが故 楚王に直言
疎んぜられ 国は敗れて 投身の
民
そが漢詩の 扉開あけ初ぞめ 紀元前の世紀
わが民も かの地に学び 成す やまと式
かの地産の 古き宝は 今もきらきら
漢の民よ 遺産見に来ませ 日本で長生き
海越えて 歴史たどりて 共に添わん節句
拙くも 慎み贈らん やまと流絶句