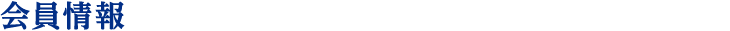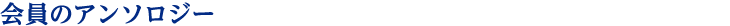会員のアンソロジー5・魚家 明子氏~
魚家 明子 ウオイエ アキコ
①1972(昭和47)8・16②富山③奈良女子大学国語国文科卒④「詩彩」「野の草など」 ⑤『逆ねじ魚類図鑑』『森には雨、五月』思潮社。
生
心が
きれいか汚いかなんて
考えるひまもなく生きてきました
と、目を上げて語る人よ
きれいな嘘をつくよりも
無骨な本当で誰かを傷つけていたい
本当でできた傷ならば
きっとふさがり強くなるだろうから
うちあけられない悲しみが
走ってゆく激しさの中 燃えて
返礼に慣れていないやわらかな耳を
ナイーヴな髪で隠して
あなたは今日も誰かの食事を作る
あなたは今日も小さな文字を記す
あなたは今日も
うおずみ 千尋 ウオズミ チヒロ
①1944(昭和19)8・14②福島③磐城女子高校卒④「衣」⑤『凌霄花』私家版、『憶』 みずほ出版、『牡丹雪幻想』コールサック社。
春雪
茶室へと続く
踏み石の優しさが
おりしも 立春の日に舞う牡丹雪の清冽な華
やぎのなか
まるで
水墨の絵のように
盲いた女の
視える筈のない視覚に映えている
振るまわれた一服の茶
香ばしく泡立ち 溶け広がってゆく
淡い
みどりの宇宙よ
その
柔らかに甦った色彩の記憶の向こう
雪見障子のガラス越し
裸木を包んで
白い見事な花が咲き積もっている
宇佐美 孝二 ウサミ コウジ
①1954(昭和29)1・17②愛知③愛知大学文学部卒④個人詩誌「アンドレ」⑤『虫類戯画』思潮社、『浮かぶ箱』人間社、『ぼくの太りかたなど』七月堂、『空の擬音が、ふ』不動工房。
海
目の前の水平線は
このように眠りたい
というぼくたちの
ながい
ずっと続き ずっと白んでゆく線の
眠りの端を
つかまえてぼくたちは
やっと起き上る波の群れ群れ
牛島 敦子 ウシジマ アツコ
①1972(昭和47)11・24②富山③京都大学文学部国語国文科卒⑤『緯線の振子』『磁気圏擾乱』砂子屋書房。
点景
膝の上にこぼれおちたのはあり得ない角度の
ひかり
ポリエステルのスカートがなぜか
ぱたぱたと鳴りひるがえって
車はちょうど川にさしかかる
土手の上 橋の頂上
喉いっぱいにせまりくる空
気づかなかった半ドア!
かけ忘れていたキーロック
傾きに耐えかねたふたつの扉が
こんなふうに飛ぶのだ あの虫たちも
かたくなな殻を 一瞬 つよく押し広げて
そしてまたゆくのだ いつか 心も――
閉ざすことに慣れきった日々の隙間から
薄翅をさらし 遠く弧をひき
無窮の紺色 秋の中心へ
臼田 稔 ウスダ ミノル
①1935(昭和10)12・3②徳島③東京教育大学国文科卒④「かおす」⑤『黒』矢立出版、『ハレルヤ』国文社。
おお脳よ
ぼくのかわいそうな脳よ
深い
ヒラリヒラリと出はいりするだろう
熱帯のあのキレイな
信天翁にくわえられて岩場の巣へと運ばれ
ヒナたちについばまれてあれ
かわいいくちばしに舌にさわられてあれ
或いは地の底でミミズの巣となれ
千匹万匹億匹のミミズにもぐりこまれてあれ
ミミズたちは性的にコーフンしてうごめこう
イモリやヤモリの出没する穴ともなるがいい
ぬるぬるした彼らのヒフがさわるとき
ぼくは性的にコーフンするだろう
ぼくの脳よグニヤグニヤに腐ってあれ
悪臭を空高く放て そしてぼくは
きで ああ ぼくは本当に死にたい
v ie は長過ぎ疲れはて満身創痍である
そしてさよならを言いたいのも
宇田 禮 ウダ レイ
①1930(昭和5)1・5②横浜③東京外国語大学中国語科卒④「焰」⑤『ブナになった少年』新読書社、『声のないところは寂寞』みすず書房。
ペイブメント
水玉模様のワンピースを着ている 裾をひる
がえして歩いてくる 竜旗のような尾ひれ
ぼくは大板ガラスの内側で女を見ている 横
断歩道をまっすぐくる 意志的に今日もくる
むきだしの鎖骨のしたで乳房が揺れる ペイ
ブメントを蹴る黑靴の尖った音 背びれ腹び
れは垂直に 胸びれは水平に ぴんと張って
どんどんくる 止まらないぞ 飛びこまれた
大板ガラスに水紋が広がる オーララ 目の
まえで白い腹が息づいている 雲南珈琲を飲
みながら人工交接の話を女とした おなかが
ふくらんで頃合の柔らかさになるとおなかを
絞って卵をだす 頃合と加減は男の指と掌が
知っている 次に卵のうえで雄の腹をしごく
水鉄砲の水のように精液が散る きみの卵の
数だけ無駄なく魚が誕生するよ でも気持ち
いいのかなあ 雌は眉間に皺を作った
内田 幸雄 ウチダ ユキオ
①1932(昭和7)1・2②神奈川③法政大学経済学部経済学科卒⑤『白い木』栄光出版社、『測鉛』潮流社。
蜻蛉
せまい裏庭で洗濯物を干していた妻が
指の間に蜻蛉の翅をはさんで見せにくる
手を差出すと蜻蛉が来てとまるのだという
蜻蛉と遊んでいると仕事が遅くなってしまう
そう言いながらも いつも
楽しそうに蜻蛉を見せにくる
きょうは指をちょっと咬まれた
蜻蛉って咬むのねとおどろいている
なんと蜻蛉が咬むことを知らなかったのだ
病気の後遺症で 大好きな
人形作りも折り紙もできなくなったので
家事の合間を日溜りで
草花の世話をしたり 蜻蛉と遊んだりする
夜 お勝手の後片付けがすむと
テレビの前に座って
翅を伏せるように両手を膝に置く
そのままのかっこうで
時々居眠りをする
内山 登美子 ウチヤマ トミコ
①1923(大正12)7・29②神奈川③横須賀高女卒④「日本未来派」⑤『炎える時間』『ひとりの夏』国文社、『アランの鼻は冷たい』思潮社、『天の秤に』花神社、『内山登美子詩集』土曜美術社出版販売。
根三つ葉の
根三つ葉のやわらかな茎を
さっと湯がいて
昔どおりの調理法で 食べる
それでどれだけの熱量が得られるか
などと思案することはない
香りを食べることの
煙りのようなものおもい
口中にわずか とどまり/たちまち消える
そう消えることの確かさが
眼をほそめて笑っているようではないか
さよならと言わず こんにちは と
咀嚼する人の口もとを
しばし愉しませて
あとはなにもないのだ
研いだ鎌でひと思いに刈り取った
ぼうぼうの野菜畑の
ひと握りの根三つ葉だった と
内海 康也 ウツミ ヤスナリ
①1931(昭和6)3・1②樺太③弘前大学教育学部卒④「飾画」⑤『夜のアンモナイト』 私家版、『かげろうの唄』思潮社、『焰』地球社、『青銅時代』国文社、『マジック・ナンバー』北の街社、『内海康也詩集』土曜美術社出版販売。
地霊頌
――ambivalence
無告のむごたらしさを生きのびて
あえかな愛の証
あかし
も幽かな残像にすぎない
わたしはうしろめたい亡命者だ
いつもつきまとう それ
今宵は月
ア ルテミス
の神の祝祭日
酒で飼いならした臓器も脳髄も
怒れる神経組織の蜂起も
萎えた身心の錆落としも
暴れまくるごうまんなブログの余白に
行方知れずの自分さがし
ことばはむなしく帰参する
悪意の時間を食べる光のあぎとは
腫瘍にも似たあの夏のキノコ雲
百万遍の裏切りと1、000ガロンの涙で
アンビヴァレントに折り合いをつけ
怨嗟の声は継
シークェンス
起する大きなうねりとなって
冒された水惑星に襲いかかる
屈辱と受苦の立ち位置から
愚直に生きる誇り高い亡命者だ わたしは
日盛り ケッセルの『昼顔』も咲いていて
海埜 今日子 ウミノ キョウコ
①1965(昭和40)11・5②東京④「hote l第2章」「すぴんくす」「ガニメデ」⑤ 『季碑』『隣睦』思潮社。
ゆうえんち
素材の過去にえさをつなぐ、のろしのような
嗚咽をあげ、まだ存続、まだ絶滅、そしゃく
のまさぐる接点です。気泡の侵食がやさしい
ので、ひたるふりで忘れるものか、一線ひき、
かすれ、まるでめくるめく遊園地、つきたて
るようにつきぬけるふりをして、食物として
うべなっていたのだから。おしよせる部位、
ひるがえり、あるいは遊具の突端で、そしゃ
くが下降を模倣し、剥離ぎりぎりをもちはこ
んで。一枚なげき、一枚ひしゃげる、気泡に
演技がせめぎあい、目撃するので、えさをか
すめ、大胆な告白として、忘れるものか、め
まいにたばねたかったのだ。嗚咽たち、ぶれ
て、そしゃく寸前の、いきられた手前で、お
ぼえますか、素材をかすめてえさをほうむる、
遊戯はだれもまつろわない。一声のあとで、
さきで、予告のようなのろしにそそぐ。
海野 庄一 ウミノ ショウイチ
①1930(昭和5)5・10②茨城③茨城大学教育学部国文科卒④「POEMS NOW」 ⑤『蘇生』わかばやし書店、『てんじょ山』国文社。
背
ことばを失念してしまったのか ことばを
おそれているのか そのようにしか おもえ
なかった 薄いくちびるが かたく 貝のよ
うに閉じている 熱いこころを 真直ぐな気
持を
あるとき 校庭の隅で出遭った ホウキで
掃除をしていた 上げた眼の奥がきらりと
光った この眼がことばのかわりなのか そ
うにちがいない
眼で意を伝えることを 予知しているよう
な眼 この眼はそうにちがいない 他を容れ
ることは 眼でできるのか 立ち去ってゆく
姿をかえりみながら 立ちどまって わたく
しはその背を見た
背に眼はないが どうも前から見るより
背の方が 他を容れる眼をうけとめずにはい
られなかった
わたくしは 少なからずうなずいた
埋田 昇二 ウメタ ショウジ
①1933(昭和8)7・8②静岡③名古屋大学経済学部経済学科卒④「鹿」「青い花」⑤『花の形態』詩学社、『富嶽百景』『風切り羽』『樹海彷徨』思潮社、詩論・エッセイ集『修辞と転位』土曜美術社出版販売。
滝
あるいは
水たちは
すでにあまりにも緩やかな流れが続いていた
から
いずれ
それもすぐに
崖が近づいていることに気が付いていて
落ち始めた 瞬間
目も眩む奈落の底に散策することを覚悟して
砕け散る水たちの一滴一滴が
いのちの最後の輝きを啓示して
落ちていったのかもしれないが
聴こえていたのは悲鳴ではなく
いみじくも
魯迅先生の言葉を憶い起こし
「絶望の虐妄なることは まさに希望と相等
し」と呟きつつ
しばらく傲然と瀧壺に沈んで
なにごともなく
ふたたび海に向かって流れていく
したたかな水滴の声は聴こえただろうか
梅田 卓夫 ウメダ タクオ
①1938(昭13)4・2②岐阜③名古屋大学教育学部卒④「アルファ」⑤『物たちの位置』秋津書店、『額縁』うむまあ会、『風景』西田書店。
永遠堀に沿って
城下町のはずれに竹やぶがある。薮の下に堀
川がある。ところどころに水たまりができて、
草が倒れこみ、茎の下に雲が映っている。水
の中にも風は吹いているのだろうか。地面の
中の遠いあそこ。ドストエフスキーは、永遠
を考えるとき、たとえば、ロシアの田舎に湯
殿があって、その、薄暗い隅に蜘蛛の巣が掛
かっているのが見えたという。
笹がゆれている。葉が水に触れたり離れたり
する。時間がさまよっているのは、三半規管
でも、宇宙でもなく、路地。石ころに寄り添
う昨日の影。地面の中の遠いあそこには、こ
の世から消えた明るい路地があって、角の郵
便局から坂を上ると、椎の木を漏れた光が路
面でゆれ、やがて正面に石橋が見えてくる。
真昼なのに、人は通らず、白々と石が陽光を
あびている。
江口 節 エグチ セツ
①1950(昭和25)4・21②広島④「叢生」「多島海」⑤『鳴きやまない?』編集工房ノア、『草蔭』土曜美術社出版販売。
虹
呼ぶ声に外に出ると
水蒸気をたっぷりふくんだ青空に
ふたえの虹がかかかっていた
おもわず 小さくさけび
どのくらい見つめていたか
頭上にひろがる毎日の空が
見知らぬ果てのように遠かった
恩寵のように
高みを けざやかに隈どるもの
裏の家で 早い夕餉を囲む声がする
煮物のにおい
駅の方角から警笛と車輪の音
街は低く ゆるやかに息を吐き
東の空に しずかな伝言が満ちていく
ここに生きている、こと
地上に棲む者は忘れやすい
いつも初めてのように うけとるのだ
江島 桂子 エジマ ケイコ
①1933(昭和8)2・11②熊本③熊本大学教育学部卒⑤『
誕生
荷が着くという
急ぎ駆けだした
港へ
夜明けのぬか雨が
髪をぬらし続けたが
かまえて拭かなかった
荷は小さな棺
その中に老いてしなびた顔
うみの水に耐え
ぴっちり閉じられた目
凝脂にふさがれた耳
生の向きと
死の向き
均しい力にひっぱられ
白い装束の袖を
旗のように振りながら
――怖いんだね
泣いている
江島 その美 エジマ ソノミ
①1944(昭19)5・19②佐賀③山口県立大学国文科卒⑤『合歓』『水枕』『水の妊婦』花神社、『水の残像』『天窓』土曜美術社、『モケレ・ムベンベ』書肆青樹社、『江島その美詩集』『水郷の唱歌』土曜美術社出版販売。
朝の楽器
鉄を 土に打ち込んだ長閑な時代も
鉄が 人を殺す戦さのさなかも
女びとには
鉄は 胃袋を満たす台所の道具だ
平和なあしたの鉄のために
夜が明けるように
女びとは
月の満ち欠けを数えつつ
命 孕み
命 育み
命 繋ぎ
血の鉄分だけを生き継いできた
鉄が 血と結びつくのを知っているから――
鉄は
どのような時代も
新しい朝の トントントン……
〈菜きざむ楽器〉こそふさわしい
江知 柿美 エチ カキミ
①1932(昭和7)10・20②東京③東京都立大学大学院(哲学専攻)修士課程修了④「アル」⑤『江知柿美詩集』芸風書院、『歯が痛む夜』『天にも地にもいます神よ』書肆山田。
神が死んだ日
「玉音」放送を聴いて 少女は
「天子」が呼吸をし排泄をする人間だったと
初めて知った
「御真影」の姿そのままに 一日中 一年中
あの姿勢で立っているのだと思っていた
みんな笑うがいいだろう 嘲るがいいだろう
あの時 少女の全身は砕かれ
魂は彷徨を始めた
少女は大人たちに縋ろうとした
師であった大人に 鍜えてくれた大人たちに
何故ですか 教えて下さい だが
大人たちはすでに少女のまわりにいなかった
衣を脱ぎ捨て 国中に散らばり
国境も越えてグローバルに 遁走していた
禁じられていた歌が流れ
「鬼畜」のことばが街を席捲していった
少女の中に不確かなものが充満し
もはやいかなる神も現れることはなかった
* 第二次大戦中、米英は「鬼畜」と言われていた。
江原 律 エハラ リツ
①1930(昭和5)12・20②岡山③岡山大学法文学部法科卒④「駅」⑤『琥珀の虫』不動工房、『曙のヒト』花神社、『インカの枯葉』思潮社、『遠い日』潮流社、『ねえ ジン』詩画集樹海社共著・画江原陣介『風吹く教室』樹海社。
風花
見上げてきた
ひとは空を
空のむこうの昏い
そこに舞う
風花のような星々を
重力の荒野に
たちすくんで
夕焼け
人っ子ひとりいなくなっても
地球はまわり
日の落ちゆく先に
夕焼けはある
空は
思い出が染めるのでは
ないから
蛯原 由起夫 エビハラ ユキオ
①1930(昭和5)5・8②福島③旧制会津中学校卒④「詩脈」⑤『天空への切符』『会津の鬼婆』歴史春秋社、『おれは犬ではないか』近代文芸社。
私は横に並べない
横に並ぶと往復ビンタの悔恨
教官から力が足りないと言われて
親友の顔を殴った
理不尽がまかり通った一列横隊
以後僕は横に並ばなかった
それは六十年も続いた
歩みの歴史の中で
いつも風のような存在があった
砂漠も氷河もただひたすら歩いた
一列に一列に妥協のない縦隊
風は僕の前や後ろにもいた
しかしその正体を暴くことはなかった
いつも他人と並ぶことなく歩いてきた
危なかった断崖の右側にいたのは
たしかに僕の風神だったと
最近になってしきりに思えるのだ。
大井 康暢 オオイ コウヨウ
①1929(昭和4)8・21②静岡③日本大学英文学科卒④「岩礁」⑤『ブリヂストン美術館』漉林書房、『哲学的断片の秋』沖積舎、『現代』『中原中也論』土曜美術社出版販売。
秋
木は空を裂いて立っている
大地の沈黙そのものだ
死んで行く人間は
残された者に寛大でなければならぬ
堂々と立っている幹のように
刈り入れを待たずに稲が折れ伏した
昨日は頭を垂れて重々しくゆれていたのに
夜来のはげしい風雨に耐えきれず
野分のなかで足首を薙ぎ倒され
黄色い穂を泥だらけにしたまま
倒れたら二度と立ち上がることはない
クレーターの底に折り重なって
枯れた玉蜀黍のように裸身を晒す
灰色の空の下を農夫たちは家路を急ぎ
埋葬の季節は慌ただしい
また 風が吹く
半月が色を濃くして
世界は残酷に凍って行く
大石 ともみ オオイシ トモミ
①1956(昭和31)1・1②愛知③愛知淑徳短期大学英文学科卒④「アルファ」⑤『ルーシー 遠い虹のように』樹海社、『手ぬ花』思潮社。
北京五輪の夏に
ゴールして
右手の拳を突き上げ
言葉にならない喜びを
全身であらわす人よ
より高く より速く より美しく……とは
ひとがヒトに与えた命題なのだろうか
水を分け 地を蹴り
わがうちなる野生
マンタ……カモシカ……シオカラトンボ
生きものの記憶を拳に握りしめて
より強く より遠く
見えない水搔き
透明な翼
言葉はいつも置いてけぼり
歓喜の潮騒がひいていくと
ようやく一周遅れでやってきた言葉に
ひとは夕焼けのように染まるのだ
大石 規子 オオイシ ノリコ
①1935(昭和10)3・10②神奈川③早稲田大学教育学部卒④「地球」⑤『あかねさす』花神社、『学童疎開その後』花梨社、『八月の友だち』クリエイティブ21。
白磁の壷
あなたが遺した白磁の壷
ふっくりと ふくらんだ腰
細めの口
梅 桃 水仙
藤 菖蒲 卯の花
萩 芒 桔梗
楓 南天 山茶花
季節ごとに ひと枝ずつ
壺に生けられ
そのたびに
壺は生きかえり
あなたとの 日々を夜々を
甦えらせる
そのとき 壺の肌は
しっとりと潤い
ほんのりと色づく
大岡 信 オオオカ マコト
①1931(昭和6)2・16②静岡③東京大学文学部国文学科卒④「櫂」⑤『記憶と現在』書肆ユリイカ、『捧げるうた50篇』『鯨の会話体』花神社、『うたげと孤心』集英社、『折々のうた』岩波新書。
三島町奈良橋回想
堀抜き井戸が狭い小さい庭にあつた。
茗荷がちよぼちよぼ生えてゐた。
塀ぎはに白萩の これは りつぱな群生もあ
つた。
ほんとにちつこい借家だつた、恥づかしいほ
ど。
だが何てつたつて あの透き徹る
冷たい清水。天の甘露よ 地の玉露。
なまぬるい水道水は引いてなかつた、そのか
はり
縄で吊るした西瓜が、真赤に冷えて滴つた。
観世流の謡をうなつてゐた父ちやんも、
暗いうちから釜をしやかしやか
母ちやんも、この水が 誇りだつた。
夢の中でも 伸びた藻草がゆらゆら揺れて、
坊やはやがて この奥の 水の都へ帰つて来
るのさ、
ゆらゆらと頰笑んで 手招きしてゐた。
大掛 史子 オオガケ フミコ
①1940(昭和15)1・27②東京③目黒高校卒④「墓地」「COAL SACK」⑤『丘の教会』東京文芸館、『花菖蒲イーリス』本多企画、『桜(はな)鬼(おに)』コールサック社。
白い馬
ラモリス監督の映像詩「白い馬」は
「赤い風船」と共に
うら若い季節の映画行脚の宝石だった
五十二年ぶりに封印が解かれて
モノクロのカマルグ湿原に再び現れた白い馬
野馬の王
強く誇り高く捕えんとする人の手に余ったが
ただ一人心を許した漁師の少年を乗せて
追手を寄せつけず海原を泳ぎ分けていった
共存の地をめざした少年と馬を翻弄しながら
幕が閉じられた青春の海
苛酷な朱夏の旅をめぐりつつ見たのは
燃え落ちる追憶のスクリーン
少年を乗せた高貴な幻影は滅んだ筈だったが
白い馬は還ってきた
歳月を嵌めて深い眼をした少年と共に
ああ
この煌めく白秋の野を駆けめぐれ
玄い冬の海にいつか向かうときまで
大澤 榮 オオサワ サカエ
①1956(昭和31)1・17②群馬③大正大学大学院人間学研究科修了④「山音文学」⑤『報復の杭』七月堂、『蝶のように』白地社、『丹頂夜曲』ゆにおん出版。
暗礁の先の埋葬
圧着されて焼け爛れた
プラスチックのように
顔面にへばり付いて
成型機の金型を流し込まれて包囲され
喉笛を 息の根を引き抜かれたか
義足は奪われ 鞄も義歯も
ロール巻きの鉄板のように身包み?がされて
凍結したレールの上で
尊厳は毟り取られ選別されたのか
荷物のように烙印を背中に押されて
どこへ向かったか
記憶を戻せるわけも無い
家族に再会できるわけも無い
悔しさが突き抜けた悔しさ
歯軋りが突き抜けた歯軋りだ
愛する恋人よ
貨物列車に満載された人々の空洞から
噴上げる悶絶は
攪拌したチクロンの侵襲は
全身は痙攣してそこから先は意識の外へ
番号もろとも埋葬されるのだ
大重 徳洋 オオシゲ トクヒロ
①1947(昭和22)11・2②宮崎③明治大学文学部卒④「同時代」⑤『帰郷』昭森社、『邯鄲』『丘の時間』舷燈社。
春の点火
あずき色にけぶる春先の雑木林
そのどこかに こぶしがあるのだが
ひっそりとまぎれている
ある日 わあっと空にむけて
白い燭光をいっせいにかかげるのだ
ああ あそこだった
点火された春の光
それを合図に木々の芽がゆるみ
みるみる明るい緑がとけだし
やがて横溢する緑におおわれ
ひとかたまりのゆたかな影
風に葉をゆらす林になると
こぶしをもう見分けることができない
目の覚めるような春の点火
そのために多分
雑木林のあのこぶしは
一年を過ごしているのだ
大島 邦行 オオシマ クニユキ
①1949(昭和24)5・7②茨城③茨城大学卒④「白亜紀」⑤『残闕』『水運びの祭』国文社、『魂、この藁の時間』思潮社。
余白に
(あんたは女房はいなさるか
女房は大事にせにゃいけん
盲目になっても
女房だけは見捨てはせん)
かつての筋骨はぼろぼろに
崩れる時間に耐えて 笑い波うち
お茶請けのない縁側で踞る
あんなに広かった世界は いま
茶柱の一本に喜ぶ
縁先の猫の額の
その先の思念には倦み飽きた
放蕩の果て 武勇伝からは
女たちが一人去り
また 一人去り
茣蓙のうえ藁一本の思い出だけがここに
声もなく寄り添い
最後の
老いは合掌の形でやってくる
*括弧内は、宮本常一『忘れられた日本人』
大城 貞俊 オオシロ サダトシ
①1949(昭和24)4・17②沖縄③琉球大学法文学部国語国文学科卒④「EKE」⑤『
い小さな物語』なんよう文庫。
煙突の煙
煙突の煙は
もう長く見なくなった
父さんを焼いて
母さんを焼いて
二人の伯父さんを焼いた
煙突の煙は
粛々として
空に1の数字を突き立てていた
生きた証のように
青さにも耐え
悲しみにも耐え
人間が消えていくことにも耐えて
薄くてもいい
風になびいてもいい
11の数字で並べればもっといい
土に帰るように
手を振るように
ぼくの煙は
ぼくを葬ってくれれば
大瀬 孝和 オオセ タカカズ
①1943(昭和18)5・12②神奈川③稲取高校卒④「ERA」、「吐魔吐」⑤『西国道・抄』一風堂、『夫婦像・抄』『赤い花の咲く島』薬玉社、『暗い夜の縞馬』『名前のない旅』ワニ・プロダクション。
水仙
両足を透き通るように痩せて
あの 年老いた男は
どこに 歩きだそうとするのだろうか
尋ね求めたものは 昨日もなかったし
そして 明日も見いだせないだろう
ただ 立ち尽くさなければならなかった
ただただ そうしなければならなかった
かなしみは
かなしみでしか 支えることができなかった
あの かすかに
ほの明るんだ しずかなもの
降り注ぐ雨に 一群の水仙の花が
その裸身を
そこだけを
太田 充広 オオタ アツヒロ
①1948(昭和23)9・29②大阪③関西大学経済学部卒・文学部中退④「火の鳥」⑤『牛頭の海』地帯社、『太田充広詩集』リトル・ガリヴァー社。
なにものかに
●過去の想い出はあまやかなままに
ぼくらは また
まえを見たのだ そこに何かが顕われる
流された汗と喘ぎのみがふさわしいなにもの
かに
応えるものは誰か
知っているものは きっといるにちがいない
●
ぼくの詩の女神は 気まぐれだ
暖かな春の陽の訪れに似て
たちまち蒼ざめた冬のカン馬にかわる
うしなわれた宝石は泥の海に沈んで
そう
もう浮かびあがってはこない
太田 隆夫 オオタ タカオ
①1937(昭和12)②福島③新制高等学校卒④「卓」⑤『風は記憶へと』私家版、『童戯考』卓の会、『水影についての覚書』私家版。
朝の電話
不透明な ひとかたまりの眠りに沈んでいた
わたしの 昨夜から今朝までの無明の果て
階下で電話が ひとしきり共鳴するから
身体から追い出される脆い安息と覚醒の到来
おととい俄雨が通りすぎるまでと
車庫の軒に雨やどりしていた白髪の人からの
時空の一隅を貸して貰えた 素朴な喜びと
濡れた両肩の処置の言葉の懐かしい真情
俄雨といえば 古い寺を尋ねたずねて
佐渡を旅したときに降られた 鮮やかな記憶
屋並みを煙らせた 見事な雨脚のしぶき
朝がた わたしの目覚めを誘った電話は
さしあたって 日常への回帰につながる
中途半端な日記を なんとか推敲してみよう
大竹 尹 オオタケ マコト
①1930(昭和5)3・31②岐阜③斐太高校定時制夜間部電気科卒④「あららと」⑤『巻貝』不動工房、『うし』国鉄詩人連盟、『さつまいもの話』不動工房。
あの日 あの時
――K夫人に――
ある日 玄関のチャイムを押す
と 暫くして返ってきた
――K夫人の声
静かに ドアが開いて
真っ白な レースのワンピース
その笑顔がまぶしくて
とまどっている私をたしなめ
優しく迎えてくれた
かつて 少年は広い
蝶々のように もつれあい 羽ばたき
遠ざかる二人のセーラー服を見送っていた
翔び去った歳月をひたすら追いかける
あの日 あの時 そこに確かに咲いていた
岡のうえの 道ばたの
野ばらのような 花模様
稚拙だが 今なら描けそうです
大塚 欽一 オオツカ キンイチ
①1943(昭和18)11・15②茨城③長崎大学大学院(医学部)卒④「風樹」「岩礁」「孔雀船」⑤『非在の館』思潮社、『蒼ざめた馬』土曜美術社出版販売、『美しき弧線の下で』風樹舎。
足音
大きな手から音もなく滴り落ち
浸みてゆく何かべと付くもの
色をもたないそれは
空にも土にも水にも浸み
あらゆるものを侵してゆく
ぼくたちはそれをわかち食らう
それは縺れたいのちの網目を侵してゆく
めだかの背骨と子猿の腕を蚯蚓の臓腑を
ぼくたちの未来を じわり
美しく刈り込まれた丘の向こうでは
鬼灯色した夕焼けがはてしなく広がり
昏い海が妖しい咆哮をあげている
薮の中で濡れた手が見えない網を張り廻らせ
闇空に巨大な花火をあげている
それらにすっぽりと包まれながら 棺を枕に
ぼくたちは束の間虹色の淡い夢を見る
千切れた小さな赤い糸玉と
その子の心臓に聴診器を当てながら
ぼくは迫りくる未来の足音を聴いている
大貫 喜也 オオヌキ ヨシヤ
①1926(大正15)6・10②山形③明治学院大学英文科卒⑤『眼・アングル』光線書房、『幽愁原野』北海詩人社、『黄砂蘇生』思潮社、英仏語対訳、英スペイン語対訳詩集『EL COMOS』スタンダードパブリッシングハウス、日漢対照『精選大貫喜也詩集』訳林出版社。
天と地と羊の里
――ルーマニア・北モルドヴァ地方で
行けども行けども山あいの農村地帯
バスはひたすら疾走し続ける
一筋の清らかな渓流沿いを
検証しながら遡上する一群れの鮭のように
藍色の空を区切る丘も斜面も
単一の原風景が車窓に果てしなく展開し
巨富も没落もありそうにない文明疎遠の
カルパチァ山脈の谷間を抜けてバスは山
登りづめて立ち尽くす緑の中の修道院
外壁を埋めつくす極彩色のフレスコ画
中世に栄えたモルドヴァ公国の遺産が
いま折からの日に 豪華な宝石となって輝く
相次ぐ文明の衝突も ここでは無縁の静けさ
若き日に背負い込んだ苦汁のクロスを
さりげなく
朝な夕な 神に祈り神に仕える 修道女たち
大野 杏子 オオノ キョウコ
1928(昭和3)3・7②千葉⑤「玄」の会『木洩れ陽』『弦月』『時は走る』『泡沫』『山鳩』東京文芸館。
合歓 の花
それは夢のうたげ
白とピンクのぼかし色の
花びらは絹糸の集まり
そこだけ輝いてみえるから
夕日は暮れるのを
遠慮している
風は音もなく流れて
やがて太陽はゆっくり去った
大きな樹蔭は薄れ
まるで黑い礫が
寄り集ったように
押し寄せてくる夜の帷
夢みるような合歓の花は
崇高な志を持っているかのように
夜毎淋しくはないのだ
平和色にあたりを染めて
果かないこの世を知らぬ気に
凛々しく咲き香っている
大橋 住江 オオハシ スミエ
①1931(昭和6)10・22②静岡③西尾高女中退⑤『憂愁』『生の揺籃』『フリュート讃歌』思潮社、『感受の森』青土社、『流れの幻想』創芸社、『沈黙の音』『ひかりの音』沖積舎。
しののめの海
それは
いのちのふるえのように
かすかな 息吹のきらめき
遥かな海の
ひかりの音
まだ だれもふれない
ひびきのように
生まれようとする
感受の宇宙をふるわせる
しののめの海の色
はるかに とおく
光の誕生
大橋 政人 オオハシ マサヒト
①1943(昭和18)9・24②群馬③東京教育大学文学部英文科中退④「東国」「ガーネット」⑤『歯をみがく人たち』ノイエス朝日、『秋の授業』詩学社、『春夏猫冬』思潮社、『先生のタバコ』紙鳶社、『新隠居論』詩学社。
朝の言葉
まあ、花はえらいね
いろんな色に咲き分けて
隣に住んでいる
田之倉トメさん、八十九歳
毎朝、勝手にわが家の庭に入ってきて
ひとまわりして出ていく
花はえらいもんだよ
だれが色を塗ったという訳でもないのに
毎朝、同じことを言っているのに
本人はそのことに気づかない
毎朝、同じことを聞いているのに
聞いてる方も聞き飽きない
いつ聞いても
新しい
朝の言葉だ
近江 正人 オオミ マサト
①1951(昭26)2・14②山形③山形大学卒④「山形詩人」⑤『日々の扉』詩学社、『羽化について』火立木詩の会、『北の鏃』東北詩人、『樹の歩み』『地上の銀河』書肆犀。
コスモス讃歌
生まれてこの方 ああ今日は生ききったと
両手を伸ばして言える日が
ぼくの時間にどれほどあったか
樹木を燃やし 果実を豊かに実らせて
霊峰月山の胴体に赤々と沈みきる夕陽
人はみんな別の人生ばかり生きていないか
(いまだ残虐と暴力が横行し
人の原始の殺意は変わりばえもなく
嘆きの加速度ばかり増してゆく
自分だけの永遠を夢想するからだ)
この生をいとおしむために
鋭利な脳髄よりも ぼくの舌を信じよう
自衛の論理より 君のやさしい指を
疑いの目よりも あたたかな眼差しを
想念の幻よりも 愛あることばの痛さを
すべてが過ぎ去ってゆくものなら
光の中にたしかに咲ききって
風に花びらの絹を無心にほどいてゆく
いちりんのコスモスの花宇宙こそ
ぼくらのいのちの暗示となるだろう
大村 孝子 オオムラ タカコ
①1925(大正14)10・4②岩手③花巻高女卒④「堅香子」⑤『ゆきおんな』La の会、『花巻の詩覚え書き』白楊舎。
草原で
ロシアの草原のまん中でバスを降りた
地平線は空から雲へとつづき
草原はさわさわと光っているだけ
どこからか目の赤い鴉が飛んできて
ガオッと草原をねじ伏せどこかへ消えた
風が痛くきらめき草むらは波立っていたが
あ、あそこに筆りんどうと野菊の花
あたりには低い芒もゆれていて
ここはチェーホフやプーシキンのくになのに
雲が反転すればわが北上盆地の秋
私らはみな草の名でつながっているのですね
ここでは戦争が繰り返されたというから
足もとには幾層もの骨が慟哭している筈だが
草原は荒涼と二十世紀をつつんで
ただ草の波と影が
折れ重なって走りぬけるばかり
うねる先には何もないような
けれどいつか探していたのだ
その先のどこかに小さい教会の
丸屋根が金いろに輝いてはいないかと
岡 隆夫 オカ タカオ
①1938(昭和13)11・12②岡山③広島大学大学院修士課程修了④「どぅるかまら」⑤『岡隆夫詩集』和光出版、中四国詩人文庫1、『麦をまく』『ぶどう園崩落』書肆青樹社、『二億年のイネ』コールサック社。
咲きほこり 咲ききって
咲きほこり 咲ききって
砂塵のようにふりまきたい
花の粉を 森中に――
老いた杉がいう
〈お命ちょうだい〉遅霜がいう
厳かに しめやかに
バラの新芽に
口づけしながら
峠は峠につらなり
重なりあい からみあい
峠は峠につらなり
気がつくと 峠を下っていた
想いの果てが宇宙の果てだ
桐のひと葉の
ひとしずくも
眩しすぎる
岡 耕秋 オカ ヤスアキ
①1933(昭和8)11・20②長崎③長崎大学医学部卒④「詩とエッセイ」「千年樹」⑤『バウム・テスト』土曜美術社、『もう一つの岬へ』書肆青樹社。
海辺のさくら
少し磯の香のする風が吹いた
そうして風はなんども通り過ぎていった
桜吹雪となった
さくら 小さなきれこみのある花びら
そのひとひらひとひらが無名のままに
姿かたちよく咲き誇り散る
ひらひらと無数の無常が散りいそぐ
残日を数える身には 心わびる風景だ
とりわけ輝くこともなかった
悔い多い歳月の終末まぢか
人生を閉じるのに
なんのためらいもないが
ひとひらの花びらのように
かたちをととのえることもなく
乱れたままに 散るであろう哀しさ
桜吹雪 その美しい一瞬 海も曇る
岡﨑 純 オカザキ ジュン
①1930(昭和5)2・7②福井③福井師範学校本科卒④「地球」「角」⑤『重箱』『藁』北荘文庫、『極楽石』紫陽社、『寂光』『岡﨑純詩集』土曜美術社出版販売。
敷居またぎ
まずは 玄関先で
一升ますの湯呑の水を飲めんした
此の家の水の飲み始めですんにゃ
一生飲みますという
花嫁の誓いでごぜんす
ほいて その湯呑を割るんでごぜんす
いっ気に割るんでごぜんす
花嫁の覚悟でごぜんす
こうして 若こうして
此の家の嫁になり
いくたりも子どもを産み
舅も姑もつれ合いも見送って
わての棺が出ていくときにゃ
わての飯茶碗が 最後に
玄関先で割られるんでごぜんす
あの世へ行けんすときの
敷居またぎでごぜんす
岡崎 葉 オカザキ ヨウ
①1951(昭和26)12・5②和歌山③向陽高校英語科卒④「Moderato 」⑤『飛行船』『世紀末ラブソング』『キスを知らない不良だった』編集工房ノア。
プロローグ
一つのいのちがなくなって
家の中から物が消えた
一つのいのちがのこした
診察券、オルゴール、がらがら
あの日のままの小道具が
主役になった舞台に
小さな椅子を置こう
人にはひとしく与えられた
椅子があるのだから
こころをしずめて
寄り添えば
短かすぎた人生の
かなしみとよろこびが……
その可愛いへこみに
お前を思い出す
詩集を広げて
小笠原 茂介 オガサワラ シゲスケ
①1933(昭8)4・25②青森③東京大学大学院独文卒④「火牛」⑤『日月の昏姻』書肆山田、『冷』『地中海の聖母』『地中海の月』『夜明けまえのスタートライン』『青池幻想』思潮社。
帽子
夜明け近く 階段を降りると
朝子の寝室の扉の下方から
薄明かりが漏れている
いつ帰ってきたのか
ほっとして扉を開けると
朝子が姿見のまえで帽子を選んでいる
見慣れない帽子のうえに
まるで生きもののような鶯色の小鳥が蹲り
薄黄の蝶か花かが群れ 震えている
ぼくに気づいて振りかえり
これから遠くまで旅行するので
全天候型の帽子にするのだという
開け放たれたままの窓から霧が入りこみ
カーテンの白いレースが揺れる
―――食事の支度する暇なかったから
自分でしてね
冷たくいうわりには暖かな笑顔に
木立の暗い緑が影を落としている
岡島 弘子 オカジマ ヒロコ
①1943(昭和18)10・13②東京③小田原ドレスメーカー女学院卒④「ひょうたん」⑤『水滴の日』『つゆ玉になる前のことについて』『野川』思潮社。
青い服 金の服
はだしで はしってきた
はだかの水に
青空が青い服着せても
たちまち
ぬぎ散らかして
にげる
はだしで はしってきた
はだかの水に
お陽さまが金の服着せても
やっぱり
ぬぎ散らかして
にげた
青い服 金の服
晴れ着の思い出もぬぎ散らかして
水ははだかのまま
きらきらわらう
岡田 恵美子 オカダ エミコ
①1931(昭和6)6・7②茨城③杉野芳子ドレスメーカー女学院卒④「条件」「嶺」⑤『レスボスの馬』『海のドラマ』龍詩社、『十軒町界隈』書肆青樹社、『白狐』花神社、『花暗』象の会、『焔の唄』地球社。
花無惨
薔薇も百合も
はらはらと花辨をほどいて
はかなげに散るものを
一と群の影を率いて
鮮かに咲き競った紫陽花
今は褐色に色退せた
それでもひしと枝にすがっている
花無惨 老無惨
せめて美しいままで畢りたいものを
杖にすがって余生を生きる
自ら断つこともできない生命
耀いてあるためには
生命のありったけを差し出し
誰かの為にできることを
力一ぱい燃焼して生きることか