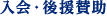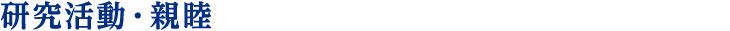● 日本現代詩人会ゼミナール2025in神戸
● 日本現代詩人会ゼミナール2025in神戸
3月15日、日本現代詩人会ゼミナールin神戸は13時30分より、神戸ラッセホール2階ブランシュにて行われた。久しぶりの神戸開催ということもあり、楽しみにこの日を待った。当日は曇りで後に雨が降り出したが、それにもかかわらず多数の参加者が来場された。参加者同士久しぶりの出会いを喜び、和やかな雰囲気が漂った。東京より、郷原宏会長、塚本敏雄理事長はじめ、春木節子ゼミナール担当理事、杉本真維子、青木由弥子、松尾真由美、渡辺めぐみ、広瀬大志,各理事もお越しくださり、遠い存在だった本部がより近いものに感じた。
第1部は、司会の季村敏夫氏が開会を告げ、郷原宏会長が開会の辞を述べ、次に神戸代表としてたかとう匡子氏の挨拶がされた。その後、蜂飼耳氏による講演が始まった。演題は「現代詩の宿命」であった。大変魅力的な演題にどのようなお話しが展開されるか開会の前から楽しみにしていた。
講演は、現代詩を書く者はどのような心掛けをもって書いているのか、という問いかけがあり、詩史を視野に入れずに詩は書けないのではないかという視点からお話しが展開した。そこで、現代詩の歴史を紐解き、まず『新体詩抄』の七五調について、長歌改良論争について述べられた。言文一致については川路柳虹を例にお話しを進められた。口語詩は当時「詩の典雅を傷つけた卑俗な作品」と人見圓吉は主張し、言文一致で書くようになるまでは、様々の論調を経てきたこと、また、折口信夫を例に挙げ、折口自身にも口語詩で書くことへの迷いがあったことを述べる。
これからの詩について、2000年以降のゼロ年代による詩は、70年代の詩人が創り出した詩が共存的風景をもっていることとは異なり、それぞれの詩人が抱えているものを、それぞれの詩人が独自に展開している。纏めとして、今日我々が書いている詩には、これまでの詩史の精神の動きが地層になって埋め込まれている。単に、行替えをしたり、連建てをするには先人が、戦いながら路を開いてきた詩の歴史が潜んでいることを忘れてはならない。次々と更新する現代詩を書くためには、詩史の地層を読み解くことが大切である。現在詩を書いている者たちにとって、刺激的な講演であった。
 第1部司会 季村敏夫氏 |
 たかとう匡子氏 |
 講演する 蜂飼耳氏 |
第2部は休憩をはさんで司会は神尾和寿氏となり、蜂飼耳氏と兵庫県現代詩協会会長時里二郎氏の対談に移った。先ほどの講演を柔らかに紐解くような対談であった。両氏の詩を披露し、それぞれの詩の書き方に触れた。現在の詩について、中心となるものがないことにより、周縁で言葉を使う、それが現代詩の強みでもあるが、中心がないということは、不安定さにつながる。それは、現代の生き方そのものが不安定だということと繋がるのではないか。和やかな雰囲気で対談の時間は過ぎた。その後、会場より質問を受けた。
次のプログラムは、自作詩朗読となり、5名が朗読した。和歌山の岡崎葉氏は、「春の夕暮れ」「春になれば」、「春の法則」を、岡山の瀬崎祐氏は「非情」と「診察室」、奈良の高橋達矢氏は「よたよた歩く神様」、姫路の野田かおり氏は「窓」、神戸の福永祥子氏は「普通の女たち」をそれぞれ朗読した。 最後は春木節子ゼミナール担当理事の閉会の挨拶で締めくくった。
その後、ラッセホールルージュローズにて懇親会が開かれた。塚本敏雄理事長により、開会の辞が述べられ、昨年日本現代詩人会の先達詩人になられた倉橋健一氏による乾杯発声がされ、相互交流を楽しんだ。遠方からの参加者によるスピーチ、日本現代詩人会の理事の方々など、アルコールで緩めた心で耳を傾けた。
初めてゼミナールの担当となり、春木節子理事には大変お世話になった。この場をお借りして、お礼を申し上げる。この1年間、春木理事のご指導をいただきながら、委員会を重ね意見交換をして進めてきた。結果、多数の方々の参加を得て、盛況な会となった。これまで、惜しみなくお力を発揮してくださった実行委員の方々、お疲れさまでした。
神戸という一地方での日本現代詩人会のゼミナール、周辺の会員にとっても日本現代詩人会の会員であることを自覚した日でもあった。イベントなどは東京中心に行われることが多いが、地方の会員のためにこの日のゼミナールが神戸で開催されたことは大変喜ばしいことであった。
 第2部司会 神尾和寿氏 |
 対談 蜂飼耳氏×時里二郎氏 |
 岡崎 葉氏 |
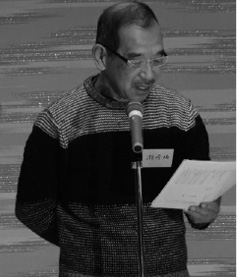 瀬崎祐氏 |
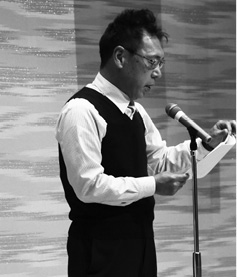 高橋達矢氏 |
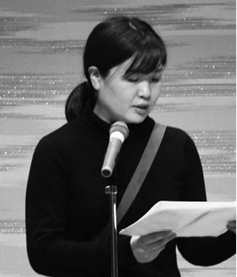 野田かおり氏 |
 福永祥子氏 |
報告 神田さよ
ゼミナール参加者数
128名(会員69名 会員外59名)
懇親会参加者数 67名
2次会参加者数 24名