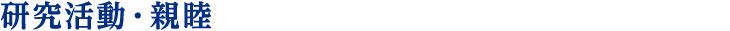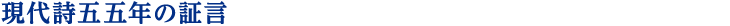シンポジウム 現代詩五五年の証言 ―日本の詩人が見えてくる―
「日本の詩祭2000」
六月三日 ダイヤモンドホテル
秋谷 豊 長谷川龍生 大岡 信 鎗田清太郎(司会) 中村 稔
 『資料・現代の詩2010』より
『資料・現代の詩2010』より
四人の詩人たち
司会 皆さん、今日はようこそおいでくださいました。また、講師の皆さま、お忙しいなかを貴重な時間を割いてご出席くださいまして、まことにありがとう存じます。今日の講師の四人の方は、戦後、日本の詩を代表する方々ばかりであります。これらの方々のお話を二時間半で、間に詩の朗読が入りますので、正味二時間で、どれだけまとめられますか、時間的制約がございますが、よろしくお願いいたします。
わたくし、このような方々の司会をするには不適格ですが、ただ、今日司会をやりますには意味がございます。ただいま日本現代詩人会創立五〇年記念の『資料・現代の詩2001』というのを編集しておりまして、この本には、三〇〇ページにわたる戦後詩年表とか、会員のアンソロジー、会の五〇年史等が入るわけですが、これは、あくまで会の歴史で、戦後詩のいろいろな方々、戦前・戦中からの大詩人の方々の名前が出てまいりますけれども、その詩の作品的評価とか詩史的な意味はこの本で触れられない。それではちょっと偏るのではないかというので、この座談会を詩祭で行なって、それをあとで文章にして入れようという案をわたしと秋谷さんが言い出しました。言い出しっぺなので、自分が言い出した手前、司会をやらなきゃならないというようなことで、大変僭越ではございますが、司会をやらせていただきます。
一番向こうから、中村稔さんです(拍手)。皆さん、戦後早い時期から詩を書いておられまして、中村さんは初期に「世代」という詩誌などで、立派な詩をお書きになっておられます。それから『無言歌』という詩集も大変立派なものでございます。また宮澤賢治の研究とか中原中也の研究などでもよく知られております。中村稔さんです。
それから、長谷川龍生さん。現在の会長さんです(拍手)。長谷川さんは、日本近代文学館が編集した講談社の『日本近代文学大辞典』を見ましたら、長谷川龍生の項目の一番最後に「攻撃的な孤立者」というような言葉が出てまして、長田弘さんの形容ですが、なかなかうまい。攻撃的な孤立者、スーパー・ドキュメンタリー詩法の創始者と言いますか、そういう方です。
それから、大岡信さん(拍手)。国際的にも大活躍の方で、その上現代詩に素晴らしい作品、評論、さらに日本の伝統文学についてのいろいろな著書を出されております。とくに朝日新聞が第一面に連載しています「折々の歌」は、二一年間続いている。これは外国の詩人がみんなびっくりするそうで、フランスの詩人もびっくりして、「ル・モンド」の第一面に毎日われわれの詩やわれわれの文章が載ることがあるだろうかと言って、驚かれているそうでございます。大岡さん、よろしくどうぞお願いします。
それから、秋谷豊さん。秋谷さんも、昭和二一年ですか、戦後間もなく福田律郎さんと「純粋詩」というのを、戦争が終わってすぐにやられて、それから今の「詩学」の前身の「ゆうとぴあ」、それが「詩学」になっています。そのほか「地球」を創始してネオ・ロマンティシズムというようなことを提唱なさって、「地球」は大雑誌として隆々と現在も続いております。また登山家としても著名な方です。よろしくお願いいたします(拍手)。
じつは、今からだいたい一時間ぐらいで第一部が終わりまして、あと、三時五五分ぐらいから、現代詩人の作品の朗読がございますので、お一人、まず一〇分以内でお話を伺いたいのです。最初が、「私の詩の出発」ということ、これは細分しますと、詩を書きはじめた時代。二番目が、出会った詩人、影響を受けた詩人。もし、時間的に余裕があれば、戦後詩の展開について、何か所感を述べていただければありがたいと思います。
私の詩の出発――中村
司会 中村さん、中村さんを拝見していると、なにか唐か宋の詩人のような、非常に高潔な感じがいたしました。第一線の詩人でありながら、いわゆる詩壇的流れからいつもちょっと離れて独自の道を行って、非常に端正な詩を書いている方という感じをもっています。戦後大ベストセラーになった原口統三の『二十歳のエチュード』、一高時代から、この原口さんとも親友だったそうですが、ひとつ、その辺からお話をいただければと思います。
中村 わたくし、かつて飯島耕一から「中村さんの詩は明治時代の詩だ」と言われたことがあるのですけれども、鎗田さんに、今日は唐・宋まで引き戻されてしまいまして(笑)。それほどでもないがなあという感じを持っておりますけれども。詩を書き始めた頃、出会った詩人、影響を受けた詩人というようなことで申しますと、中学時代に、二、三、習作したことがないわけではないのですけれども、詩を書きはじめたというのは、一九四四年に旧制高校に入学してからと考えています。ですから昭和一九年に入学いたしまして、たぶんその前年くらいから『萩原朔太郎全集』が出始めていますし、それからその二、三年前には、高村光太郎の『智恵子抄』が出ています。旧制高等学校に入りまして、上級生の人たちから、宮澤賢治を教えられ、中原中也を教えられ、それからその当時は、三好達治の『春の岬』という、これは創元選書というので一冊になった詩集がございまして、三好達治を読み、立原道造とかそういった詩人たちを一度に読むことになりまして、そういう人たちから非常に影響を受けたと感じております。
その場合、わたくしの場合若干特異だったかと思うのは、戦争中でございますから、わたくしが詩を読み始めた時代には、いわば「詩と詩論」の系譜につらなるモダニズムの系統の詩人たちが、ほとんど全員、戦争詩を書いておいでになって、それはもうほとんど読むに耐えるものでなかった。ですから、わたくしは昭和初期において「詩と詩論」なんかにお拠りになった方々がなさったいい仕事を、まったく知らない状態で詩を書き始めたのです。これは同世代の方々と比べてちょっと特異な体験であったのかなあというような感じがいたします。
詩を書くのについて、そういういろんな人たちから影響は受けましたけれども、とくに詩を書き出す前にお目にかかった先輩詩人は一人もいない。詩を書き始めて、多少雑誌等に書くようになりましてから、草野さんに生涯で四、五遍お目にかかっている。三好さんにはただ一回だけ、亡くなった前年にお目にかかっているというような状態で、わたくし自身多少人見知りもいたしますし、先輩詩人に私淑して指導を仰ぐというような気性でないものですから、そういう先輩詩人にお目にかかったということはほとんどないし、また、もうひとつは、わたくしは今まで同人誌に誘われたという経験がないんですよ。鎗田さんはああいうふうにおっしゃいましたけれども、誰も私を誘ってくださらないから(笑)、わたくしは止むを得ず一人で詩を書いてきたということなのです。
ただ、かなり多くの方と違って、わたくしが非常に恵まれていたのは、さっきお話に出た『二十歳のエチュード』を残して死んだ原口統三がわたくしの同級生で、そのとき一九四四年、旧制一高に入った同級生の文科の学生が、ほぼ七〇人いたわけですけれども、その中の一人であったのです。原口が自殺するということを宣言してから、死ぬまでを同じ寄宿舎でずっと一緒に過ごしたわけです。彼が死んで、『二十歳のエチュード』というノートを残したということが新聞に出たので、これは商売になるんじゃないかと思って訪ねてきたのが、伊達得夫だったのです。原口の遺稿は、もう亡くなりましたけれども、フランス文学をやった橋本一明という、原口の一番の親友が持っていたのですけれども、ちょうど橋本が留守だったので、わたくしが橋本に代わって伊達得夫にお会いして、それは見込みあるんじゃないですかなんかといい加減なことを言って、それが縁で伊達得夫と知り合った。そしたら、伊達得夫が、その当時は前田出版という本屋さんに勤めていたのですけれども、前田出版をやめて、書肆ユリイカを起こし、書肆ユリイカでいろんな出版物を出したのですが、なにをやってもうまくいかない。もういよいよ出版をやめようかと思うときに、那珂太郎さんが、その当時、那珂さんは女子高の先生をしてらしたのだと思うのですが「俺には生徒がいるから、生徒に売りつけるから、お前、損しないよ」と言って、那珂さんの詩集を出した。そのときはまだ『那珂太郎詩集』じゃないのです。本名の福田正次郎で出した詩集『Etudes』なんですけれども、それを最初に出版した。それをご覧になった中村真一郎さんが、それなら俺の本も出したいねということをおっしゃって、中村真一郎さんの詩集を出した。それに乗っかってわたくしも『無言歌』という詩集を、昭和二五年に出版したわけでございます。
そういうことから、それが伊達得夫にとって心ならずもであったのか、結局そこで本質に行き当たったのかわかりませんけれども、ともかく詩の出版社になり、やがては雑誌の「ユリイカ」を創刊するようになった。ですから、わたくしは詩の同人に誘われたこともないし、仲間もいないし、先生もいないし、弟子もいないのですけれども、伊達得夫を知っていたお陰で、いわばそういう詩を書く人たちの中心のすぐそばにいた。そういうお陰で、伊達と、思潮社の小田久郎さんは、当時いわゆる昭森社ビルで机を並べていた時期もありますから、小田久郎さんも知り、第二次の「ユリイカ」を創刊した清水康雄さんとも知り合うというような形で、大変恵まれた境遇にいて、詩を発表するのにあまり不自由しなかった。
ひとつには、わたくしはあんまり詩を書かないものですから、たまに書くと載せてはくださるというような関係で今日まで来ているわけでございます。一〇分くらいというお話ですが、鎗田さん、こんなものでよろしいですか?
司会 どうもありがとうございました。それでは長谷川さん、ひとつお願いします。
小野十三郎と私――長谷川
長谷川 いま、日本現代詩人会の会長をやっておりまして、これは、一期が終わって二期目なのです。一期のときは、わたくしは、あやしげなトリの怪鳥(会長)であります、というふうに皆さんに申し上げまして、今度は二期目に入りまして、わたくしの存在は現代詩人会の盲腸か十二指腸か、いまや紋白蝶あたりになっているのではないか(笑)、というふうに思っておりますが、わたくしは、かなり早熟でございまして、昭和一七年=一九四二年ぐらいから、その時代の現代詩をかなり読み込みました。その時分に、山雅房というところから、現代詩の三六人の作品集が全六巻で出ておりまして、それを買い込んでっくりと読んだわけであります。いろいろ立派なたくさんの面白い詩人がいまして、そのときは本当に、今はそんな気持ちはほとんどありませんけれども、その三六人の昭和一七年の時代の現代詩を読んで、本当に胸を膨らましたわけであります。
そのなかで、三六人のひとを一人ずつ殺していって、たった一人一本に絞ったというのは私の癖であります。それが、同じ大阪に住んでいた小野十三郎さんという人でありました。この人は大変厳しい人で、厳しいと同時にちょっと冷酷無残なところがある人で、その下でよくぞずっと耐え忍んできたなあというふうに思っております。小野十三郎さんが死んで、もう三、四年たちますけれども、ぼつぼつ小野十三郎を克服するということもやらなきゃいかんと思っております。
わたくしが書き始めたのが、習作時代は戦争中でありましたけれども、戦後すぐに詩を書き始めまして、大した詩も書かなかったのですけれども、小野十三郎さんから、その時分のアナキストのあとを引いている「コスモス」という雑誌に、わたくしの処女作と言いますか「山口線仁保」という詩を載せていただき、それからすぐに「日本未来派」に、これは安西冬衛さんの紹介でありますけれども、「都会について」というわりあい長い詩を載せていただいて、そこで皆さんの目にとまったわけであります。
それから大阪では、いろいろ小さい詩の同人雑誌を創ったり、運動をしておりましたけれども、浜田知章さんの「山河」という雑誌に加わりました。浜田知章さんはそれまでは岡本弥太という四国の宮澤賢治と言われる、人生派的な詩を書いていた人の雑誌をやっていたのですが、急遽、ちょっと左翼的な社会主義リアリズムと申しましょうか、社会主義ロマンチシズムと申しましょうか、そういう辺りへ浜田知章と一緒に運動を展開していった。そして次に、その時分、東京の方で井手則雄さんという人が「列島」という雑誌を創るというのでオルグにまいりまして、入らないかということで、その「列島」の方に入ったわけであります。しかし「列島」の井手則雄さんが大阪へ訪ねて来られる前に、私のほうに「荒地」の鮎川信夫さんがやってきまして、お前「荒地」に入れということで、「荒地」の詩人たちの作品を全部読破しました。けれども、どうしても馴染めなかった。つまり「荒地」は、戦争中に青春を喪失していた人たちでありましたので、人間的には非常に繫がりを持ちましたけれども、「荒地」には入らなくて、「列島」の運動を展開したわけであります。
出会った詩人というのはたくさんいますけれども、小野十三郎がわたくしの現代詩の師匠でございまして、助けてくれた詩人は、やはり安西冬衛さんでした。影響を受けた詩人というのはやっぱり小野十三郎で、小野十三郎を知ったお陰で、自分の詩というもののなかにおける自分というものを限定しないで、この世の中を生きていくということを教えられたわけであります。つまり、自分を突き抜けていく自分というものを確認するという生き方を学んだわけであります。ゆえにわたくしは、今たくさんの詩人たちの詩を読む場合でも、批評のある一点は、この人は自分を限定しているのではないだろうかという詩人と、この人はやっぱり自分を突き抜けていく自分を持つ詩人であるとかということで決めるという癖があるわけであります。
戦後詩の運動は、もちろん「列島」を中心にして展開したわけですけれども、「列島」は一一号で終わりまして、そのあと「現代詩の会」というのを創りました。そしてそのときは、今のこの「現代詩人会」に対抗する若手の会を創ろうと、それを発想しまして、そして関根弘を中心にして、大岡さんだとか皆さん若い人、「荒地」の鮎川信夫さんにも入っていただいた。そしてその時分の、大雑把な言い方ではありますけれども、とにかく右と左をある一つの俎に乗せて、それで進むというような「現代詩の会」というのを展開していったわけであります。しかしこれが数年にして、関根弘には悪いんだけれども、関根弘の、なんと言うかボス交渉によって、ついえ去るというふうなことで、わたくしの夢が破れたわけであります。
もちろん、その間「新日本文学会」のほう、あるいは代々木の共産党のほうから、かなり睨まれました。いろんな詩人が共産党に入ってましたが、それが全部除名になったりなんかした。黒田喜夫だとか関根弘も除名になったりしましたが、わたくしは共産党に入ってませんでしたからよかったものの、なんと言うか、中野重治さんとかいろんな先輩詩人を恨んだわけであります。壺井繁治さんなども。わたくしもそこで絶望に陥ったわけでありますが、たった一人国分一太郎さんという立派な教育評論家がいまして、この方が非常に慰めてくれて、励ましてくれたことを思い出します。
そういうわけで、なんだかんだごたごたしながら今まで詩を書いてきましたけれども、わたくし自身は、なにか全体的に左翼的な、あるいはマルキシズムを一つの支えとした、そういう詩人というふうに見られておりますけれども、じつはそうじゃなくて、わたくしの詩をずっと読んでいただければわかりますが、最初からわたくしは、むしろある意味ではトロツキズム的な立場に立っている詩人であります。そういうふうに申し上げておきます。ざっとこんなものです。
菱山修三・「コギト」――大岡
司会 それでは次に大岡さん。お一人お一人がお話になって、それで終わりというかたちですと、個人講演会みたいになりますので、どこかで時間を残して話し合うようにしたいと思うのですが、大岡さんよろしくお願いいたします。
大岡 わたくし、若い頃の話をすると、それだけでもいっぱいになってしまうのですけれども、皆さんがそのようになさってきましたので、わたくしもそうします。わたくしの場合には、このなかで一番年は若いのですけれども、終戦=敗戦とわたくしは言ってますけれども、敗戦の年に、わたくしは中学三年生でした。中学三年の夏に戦争が終わって、これで死ななくて済むということがわかったので、非常にわたくしにとってはショックだったですね。これからどうしたらいいかってことを考えさせられることになりました。その理由の一つは、学校がなくなったからです。学校が丸焼けになってもうぜんぜんなにもないわけです。そこから始まったので、そういう意味では、わたくしの場合には詩もそこから始まっています。一九四五年の八月十五日に始まったと言ってもいいのです。
それ以前にももちろん多少は詩など読んだことはありますけれども、本当にそういうふうに考えなきゃならなくなったのは一九四五年なのです。そのときに、わたくしの通っていたのは沼津中学―今は沼津東高校と言いますけれども、その学校も、今はわたくしが通っていた懐かしい感じの学校ではなくなって、別の所へ移っちゃったのですが。戦後、初めのうちは学校を探すので大変でした。探しましたら、いくつかの工場の跡が残っていたのです。沼津は、ほとんど市の中心部が焼夷弾で焼けたのですが、しかし、多少残っていた工場があった。そこの一つを学校で不法占拠しまして、生徒が全部で行進して行って、その日からずっとある工場の跡地をそのまま占拠して、工場で授業を始めました。それは一九四五年の晩秋頃でした。
その頃に、すでにもう、何をしていいのかわからないので、みんなそれぞれが勝手なことを始めました。そのために、結局その中学が新しく工場の所へ移ったときには、かなりたくさんのサークル活動みたいなのが出来てまして、たとえば、ついこの間までソニーの社長、そして会長だった大賀典夫という男がいますけれども、大賀はわたくしと同級生なのです。一級上だったんですけれど身体が悪くて落ちてきまして、一緒にやっていましたが、彼は本当にメカニズムに非常に強かったのです。その頃にメカに強いというのは非常に不思議な男でしたけれども。実際にLPレコードやなんかを聴くためのセットやなんかも、全部自分で造ったのです。進駐軍が放出したいろんな機械がありまして、そういうものを組み合わせて造って聴くものにしていたというふうなやつでした。そういう雰囲気でしたから、学校は一学年に全部で三〇〇人ぐらい生徒はいたのですが、そのなかでサークル活動をしたのは、たぶん五〇サークルぐらいあったと思います。
その一つになるわけですけれども、もちろん学校にはぜんぜん届けもしない文学少年たちの集まりがあって、それが僅か四人ばかりのサークルでした。それがわたくしと同級生三人なんですね。その三人は全部死んじゃったので、生き残りはわたくしだけなのですけれども、そこで初めて、「鬼の詞(ことば)」という変なしゃれた題の雑誌を創ってしまったものですから、それでみんな鬼になっちゃったのだと思うのですが(笑)。「鬼の詞」というのは、橘曙覧(たちばなあけみ)という幕末時代の人の歌の中から取ったのです。「鬼の詞」は普通のやつには聴かせない、普通のやつには聴けない鬼の言葉を聴けるのは俺たちだけだという、もの凄いエリート志向です。始めっからエリート志向で、今の中学生・高校生にはエリート志向はないですけれども、その頃はそういうのが文学少年の考え方でした。
そこで中学の三年、四年の間に八冊その雑誌を出したのです。雑誌を出した紙は、工場にいっぱい残っていた工員の作業日程の紙がありまして、それを裏返しすれば全部真っ白です。それを工場の片隅から失敬してきて、そのまんまそれをガリ版で刷ったのです。字がとてもうまいやつがいて、そいつに全部やってもらいました。それはとてもしゃれた雑誌だったのですけれども、数十ページの雑誌で、そこにわたくしは、初めは美文調の散文と、それから短歌をのせました。短歌は親父が歌人なので、歌だけは、五七五七七は簡単に出来ると思っていて、実際に出来たのです。それで、詩もそれから書き出したのですが、詩は一番下手くそでした。そういう意味では非常に幼い形ですけれども、こころざしだけは非常に昂然たるもので、全国の中学生のなかで一番優れているのは俺たちの雑誌だと、初めっから思ってました。だってほかに出てないんだからしょうがない、当然ですけれども。
それが、四年まではやったのですが、旧制中学の五年になるときに、僕とほかのもう一人の男は、旧制一高という中村稔さんの後輩になるわけですけれども、そこへ入っちゃったのです。それからあとも二回ばかり雑誌を続けて、結局終わりました。しかし、それが最初のもので、そのときに僕らを、指導はしてくれないけれども友達付き合いをしてくれた国語の先生がいまして、それと英語の先生が一人、二人ともまだ大学を出て数年の人で、一人は結核で沼津へ転地療養のために来て先生をやっていたのです。もう一人は、朝鮮半島へ召集されていって、それで行ったときから終わるときまでずっと二等兵だったという輝かしい人で、その人が、帰って来てからまた国語の先生になったのです。その国語の先生をやってくれた茨木清先生という人が、じつはその当時の流行みたいなものでしたけれども、学生時代に「コギト」の愛読者だった。とくに彼が非常に重んじていた人も二、三人いましたけれど、それにプラス保田與重郎さんを非常に愛読していたのです。で、保田與重郎の本をたくさん持ってました。それから「コギト」はやはり毎号持っていて、それらをわたくしが一高に入って大学に進んだころでしたか、全部送ってくれたのです。だから今わたくしは「コギト」と、それから保田與重郎の著作はたくさん持っています。わたくしの宝みたいなものですね。「コギト」と保田與重郎を中学生のときから読んでいたという中学生はあまりいないらしくて、のちのち篠田一士とか川村二郎とかいう人々と知り合ったときに、君はどうして中学生のくせに保田與重郎なんか読んだんだって、怒っているんです。彼らは自分たちの独占物だと思っていたらしいですね。それが、二、三年あとの生まれの、こんな小僧にどうして読めたかわからないというのですけれども、結局それは、茨木さんという先生がいたからです。それでわたくしはそれを後になって「ユリイカ」という雑誌が出来たときに、「ユリイカ」の伊達得夫が、なにか連載を載せたいということになって、君はなにがいいかって言うから、じゃあなんか書こうかと、「詩人の青春」という題で、初めは何人かの詩人について論を書こうと思ったのですが、結局、最初に保田與重郎論を書き出しました。それが六回ぐらい続いてしまって一冊分に近いものができました。そういう形でやったのですが、それが本になったとき三島由紀夫さんなどに非常に褒められて、珍しくそれを載せた僕の『抒情の批判』という本は、その当時、詩人としては異例のベストセラーになったのです。つまり三千部ぐらい売れた。
そういうことがありましたけれども、淵源は中学のそのころにあります。それからあと旧制一高に入ってからは、わたくしの沼津中学の先輩で同時に一高の先輩であった人で、東大に行っていた人がいました。その人は法科を出て伊藤忠というところで一所懸命やっていた時期なのですけれども、わたくしと非常に親しかったものですから、その人の家に絶えず遊びに行っていたのです。そこで、彼に読ませられたのが菱山修三さんという詩人だったのです。菱山修三という人は、今ではまったくというほど忘れられてしまっている感じですけれども、その当時は、日本の現代詩人のなかでは一番読まれていた人の一人です。その方の本を何冊か読んで非常に気に入ったものですから、その人の影響は相当受けたと思います。ですから、わたくしは戦後、詩を書いた若手の人間としては、特異な経験をしたと思います。菱山修三なんかをこの若さで一所懸命読んだなんていうやつは、ほかにたぶんいないと思います。菱山さんの何がよかったかと言うと、単なる抒情詩というのは、わたくしはその頃から好きではなかったのです。なにかものを考えさせるということが詩の非常に重要な要素であると思っていました。わたくしは一高ではフランス語をやったのですが、フランスの現代詩人とか、イギリスのT・S・エリオットなどを先頭にした、イギリスの三〇年代の詩人たちのものを読み齧っていたものですから、そうすると、そういうものに匹敵するような詩もあり得ると。それは自分が書くしかないみたいなことを思っていたのですけれども、よくよく菱山さんの詩を読んでみると、そこには批評というものと詩というものが合体しているところがあって、それはわたくしにとっては非常に興味があったので、影響を受けたと思います。
だから最初の詩集のなかにはそんな影響のあるものもかなりあるんじゃないかと思うのですが、いずれにしても、知性というものと抒情というものが、ばらばらになっているような詩は、あまり書きたくないのです。今でもそうです。それがもとを辿ればそこにまで行き着くということで、そのころに、保田與重郎だけではなくて、「コギト」という雑誌で伊東静雄の詩やなんか読んでいたということもありますから、わたくしの場合には単なる抒情詩から出発したという意識はないのです。そこから始まりました。そういう意味では雑駁な形で始まったというふうにも言えますけれども、いずれにしても若い頃にやったこと、五〇年以上むかしのことが、いまだにほとんど変わらずに残っているという感じがいたします。
『新體詩抄』から「純粋詩」まで――秋谷
司会 どうもありがとうございました。では秋谷さん、お願いします。
秋谷 今日、ここに四人――鎗田さんを加えると五人ですが――並んでいますけれども、このなかで僕が一番年が多いのです。僕だけ大正生まれで……あ、鎗田さんもそうですか。あとのお三人は昭和のお生まれですね。僕なんかの詩の出発点というのかな、僕らの時代というのは、詩の投稿というのがわりあい盛んだったのです。その頃の雑誌に「若草」とか「文芸汎論」というような雑誌がありまして、あと「日本詩壇」とか、そういう雑誌もあったように思います。したがって僕の同時代というのは、お名前が上がった鮎川信夫さんとか、いわゆる「荒地」を構成する詩人たちですね、だいたい大正一〇年前後の詩人たちで、もう一つの特色は、彼らは軍隊経験を持っているということでしょうね。僕も軍隊に入ってますけれども、僕は兵隊ですから。しかし「荒地」の連中というのはみんな将校なんですよね、田村隆一さんも海軍少尉でしたし、北村太郎さんは海軍中尉ですか。そして、そうしたなかで、しかし彼らもやっぱり投稿家の詩人であったわけです。それはかつて昭和一三年、一四年、一五年、あるいは戦中にかけての時代ですけれども、そのなかでたった一人、俺は投稿しないという人がいて、それは「荒地」に属していた木原孝一さんです。彼は、俺は投稿詩人じゃねえぞと、盛んに威張ってましたけれど。彼は、年少にして「VOU」という雑誌に入るわけですけれども。僕自身の詩の出発点というのは、そういうところから始まったわけです。
そういうなかでいろいろと教えられたことの一つは、やはり日本の詩の始まりから読めとか勉強しろって言われました。ここにある『新體詩抄』というのは、これはもちろん明治時代発行のそのものの本じゃない。戦後復刻版の『新體詩抄』で、明治一五年七月刊行になってます。この『新體詩抄』の「體」という字が、骨を書いて豊の旧い字で、外山正一、矢田部良吉、井上哲次郎らが翻訳したヨーロッパの詩を最初に読み始めました。発行所は日本橋の丸善、当時は丸善とは言ってなくて、これで見ますと、丸屋善七という名前になってますね。近代詩の草創期の詩をこういうところから僕らは読み始めていったように思います。
それから、上田敏の『海潮音』とか、それからさらにあとになりますと、堀口大学の『月下の一群』とか、あといろんなドイツの詩やなんか好きで、これはそこの写真にもありますけれども、村野四郎という詩人が大変ドイツの詩人のリンゲルナッツとか、リルケとかの詩人の詩を読んでおられまして、ドイツの詩を読めというふうに言われたように覚えております。僕は、やっぱりリルケとかヘルダーリーンとかを大変愛読したわけですけれども、もう一つ、韓国の金素雲という人がおりまして、この人が『乳色の雲』という訳詩集を出しました。韓国の詩人で唯一岩波文庫に入っているのは、この金素雲さんだけだと思いますが、『朝鮮詩集』というのもあって、この二つの韓国の近代詩や、地方の童謡とかを集めた本、そういうものを一所懸命読んだことを覚えております。
で、投稿雑誌の作品といえども、つまり詩の精神というのはあるわけですね。その時代とは何であったか、それは今なお問いかけるべき現在であるというふうに僕は思うわけですが、「文芸汎論」という雑誌、これも僕は大事にしている詩の雑誌の一冊ですけれども、これは一二月八日を特集しているのです。これは昭和一七年に刊行されてまして、ここに先ほど言った「荒地」の仲間の中桐雅夫とか、そういう詩人たちも書いております。じつは僕もこの雑誌に書いているのですけれども、むかしの投稿家というのは、女性の名前を使って出す癖がありまして、ここに「小さな家」という石井由美という詩人が、じつは僕なのですよ(笑)。これは、一応『資料・現代の詩』に記録していただきたいと思います。僕はじつは「四季」という雑誌にも投稿してまして、丸山薫さんが選んだのが、やはり石井由美という名前で選ばれているのです。秋谷は四季派の詩人なんて言ってるけれども、一つも「四季」に書いてないじゃないかとよく言われますけれども、じつは女の名前で書いていた時代がある。これが投稿家のロマンだったんです、いま考えても悲しいロマンですけれども(笑)。おそらく中村さん、長谷川さん、大岡さんは、なんだ、あいつは甘いやつだとお思いになるかも知れませんけれども、鮎川信夫も、かつての「若草」の投稿家、あと先輩では木下夕爾もおりました。中桐雅夫も投稿家でした。べつに投稿家をここに強調するわけではありませんが、あと、北村太郎ですね。彼は松村文雄という本名で「蠟人形」なんかにも発表しているのです。「蠟人形」という雑誌も今日ここに持ってきているはずですけれども、これは西条八十が主催した雑誌です。今日お見えの新川和江さんなんかも、これは戦後の時代ですけれども、若き頃「蠟人形」に詩を出しておられたと思います。
あと、もう一つ「新詩論」という、これは合本ですのでずいぶん立派になってますけれども、ここに昭和一八年一一月終刊とあるのです。昭和一八年一一月というのは大変意味があって、一八年の一〇月に学徒出陣があるのですけれども、これは全部詩の雑誌が廃刊になった年なのです。今まで出ていた「四季」とか「歴程」、「新領土」とか「文芸汎論」も全部廃刊になって、「詩研究」と「日本詩」という二つの雑誌に、政府の情報局の命令で統合されてしまうのです。この「新詩論」を編集していたのが、先ほどの村野四郎と北園克衛です。ちょっとこれ合本してますから立派に見えますけれども、じつは一二ページの薄っぺらな雑誌なのです。その時代のなかではほとんど詩の雑誌が刊行できない、紙もろくにない時代ですから。そういうなかで回覧誌やなんかを発行したりしました。三好豊一郎、この人も戦後「荒地」に属する詩人ですけれども、彼らと、僕も一緒に詩の小冊子を出した記憶はあります。「故園」とか「葦と泥」とか、回覧雑誌なんですよ。薄汚れた藁半紙に詩を書きまして、それを順繰りに郵便で回覧していくわけです。雑誌が出せないから回覧誌でやろうということで、それでそのときに鮎川信夫は「橋上の人」という詩を三好豊一郎に書き残して戦争へ行くわけです。それが、戦後「橋上の人」という作品で発表されるわけですが、そんなようなことを、いま思っております。
あと、もう一つ読んだのは、これは大正一五年の本なのですけれども、尾崎喜八の『高層雲の下』、このなかに山の詩もいくつか入ってまして、僕は尾崎喜八の『山の絵本』という本を読んで、山登りを始めるのですけれども。もう一つ、同時に読んだのは、これも昭和の初め頃、『雪線散歩』って、藤木九三(くぞう)という、おそらく皆さん大部分の方は名前をご存じないと思いますが、富田砕花という詩人と一緒に、この人は詩人ですけれども同時に山登りをやりまして、穂高の滝谷を日本で初登攀するクライマーです。この人の息子さんが、朝日新聞社の写真部におられた藤木高嶺さんです。この人は六甲の麓に住んでおられて、僕も若い頃お訪ねした経験がございます。なぜこの人の詩集にひかれたかと言うと、単なる山の詩ではなくて、ロッククライミングの詩を初めて日本で書いたのです。つまり、氷の壁を登ったり岩壁を登ったりする。それまでの山の詩というのは、高原の詩であったり、峠を歩く詩であったわけですが、そういう意味では尾崎喜八も峠や尾根や高原を歌った優れた詩人だと思いますけれども、この藤木九三という人がおそらく日本の、これは山岳詩と言っていいのでしょうか、山の詩の歴史のなかでは初めて岩登りの詩をお書きになった詩人です。これも僕は大事にしている一冊で、今日はなにか資料をお持ちになったらどうかというお話もあったので、何冊か持ってきました。これは戦中までの僕たちの活動です。
戦後は「近代詩苑」というのが出たり、これはあとでまたお話しする機会があるかと思います。あと「純粋詩」というのが、こういう小さな判で昭和二一年三月に創刊されるわけです。この年の六月号に田村隆一が「審判」という詩を書いているのですが、これが彼の戦後の第一作であると思っております。その後、この「純粋詩」はこういう版に変わりまして、この号には鮎川信夫が「死んだ男」を発表しています。で、「荒地」の人たちも僕らも含めて、戦後派の詩人とはなにかというのは、やはり死者を背負って生きてきた世代だということでしょう。鮎川の「死んだ男」もそういうことがテーマになっています。これは、のちに「造形文学」という雑誌にかわって、このとき初めて井出則雄とか関根弘が登場してくるのです。これを編集発行したのは、福田律郎という詩人ですが、彼は生活の苦しさのなかから共産主義に傾斜していきます。それがのちに「造形文学」が廃刊になってから、「列島」という雑誌――これはもちろんまったく別の雑誌ですが、そのころの「列島」の創刊号もここにありますけれども昭和二七年の発行です。『荒地詩集』が出たのは昭和二六年ですから、それから一年後に「列島」が創刊されるのです。この主力メンバーの一人には、かつての「純粋詩」のメンバーであった福田律郎とか村松武司ですね。これで見ますと、長谷川龍生、野間宏、浜田知章、みんな名前を並べております。ではまたあとでお話しする機会があるかと思います。
「四季」について
司会 おそらく第一部はあと七、八分です。まだ非常に話が古くて、戦後もまだ戦争が終わったか終わらないかぐらいのところです。次に、日本の現代詩というものを考える場合、現在にいたるまでの流れで、今でもなんらかの意味でそれの流れのなかにあるという、その大きな流れとして、まず、四季派的詩というのが戦前から戦中にかけてずっと流れていました。その影響というのは完全にないとは言えないと思うのです。このメンバーではおそらく長谷川さんは絶対に否定なさるでしょうけれども、四季派的な抒情の問題、それから「詩と詩論」に始まるシュールレアリスム、この要素をどちらから多く受けているかというのが詩人の現状で、そのほかに民衆詩派とが、プロレタリア文学の系統があります。この四つで、分類することに意味があるわけではないのですが。秋谷さんがネオ・ロマンティシズムというようなことを戦後唱えられましたが、四季派とはどういうところで違う意識を持とうというようなお考え、あるいはどの部分は継承すべきだと……
秋谷 そうですね、僕自身は最初は堀辰雄の散文とか詩を読んで影響を受けて、あともう一人、立原道造もいるわけですけれども、そういう人たちの影響下で詩を始めて、のちに村野四郎という先ほどの「新詩論」に多く詩を書くようになって、あれは鎗田さんがおっしゃったシュールレアリスムというよりはモダニズムでしょうね。やっぱり昭和の詩の、ヨーロッパの詩の新しい手法とか精神を確立した詩人たちだと思うのです。そういうものを僕らはどこかでそれを受け継いできた気がします。受け継ぐというより、一つの伝統の延長線上のなかで、僕らは戦後の詩を考えるという問題に、まず直面したと思うのです。
その一つは、四季派の詩人たちは、どっちかと言えば戦争中はこれは三好達治もそうですけれども、そのほか神保光太郎とか蔵原伸二郎とか多くの詩人たちも、これはもうその時代の反映のなかで、どっちかと言えば愛国主義的な詩を書かれたことは事実ですが、そういう平板な時代精神のなかで、本当の詩の持っている本質的なものがどこかに押し流されていったということを考えて、それを、戦後のあの時代のなかでもう一度回復させるというのか、確立するには、やっぱり批評精神が必要じゃないかと考えて、それで抒情と批評の複合というようなことを、ネオ・ロマンティシズムのなかで主張するわけです。
司会 どうも、ありがとうございました。中村さんについては、ある大きな県単位のコンクール、国民文化祭がありまして、その審査員の講評のときに「この詩は非常にうまいが、こころざしがないから駄目だ」と言われたことがつよく印象に残っています。先ほど、唐・宋の詩人と言ったのは古いという意味で言ったのではなくて(笑)、なにか孤高の精神を感ずるという意味で言ったのですが、四季派的なものについては、中村さんはだいたいどういうお考えというか、態度をとっておられますでしょうか。
中村 わたくしは、自分では「四季」の正統な後継者だと思っているのです。ただ「四季」の後継者だと思っていらっしゃる方は、わたくしをそうは見て下さってない。そういうことだと思うのです。わたくしは、もちろん掘辰雄も立原道造も津村信夫もその他の詩人たちも非常によく読みましたし、非常に大きな影響を受けたと思っております。ただ、やっぱりあの人たちの抒情というのは、戦争中の逃げ場所のような、逃避していったような場所における抒情であって、われわれの現代社会における抒情ではないと、そういう感じもあるわけです。それは、長谷川さんがさっきおっしゃった、自分はマルキストなのかトロツキストなのかと、そこら辺のところとも関係するわけですけれども。わたくし自身はもちろん社会主義者であったこともないし、共産党員であったこともないのですが、「四季」の人たちと顕著に違うのは、社会的な意識というものの持ち方が違うので、どうしても彼らの作品については、現在読めば飽き足りないという感じが強いのです。ですから、その社会的な意識というのは、いわば人間の運命であり、人類の運命であり、あるいはわが国の未来であり、そういったような人間的現実に根ざして、いかに生きるかというこころざしがない詩は、わたくしには評価できないところがあるわけです。そういうところが、言うならば大変大雑把なわたくしの「四季」観であろうと思います。
抒情と「こころざし」
司会 ありがとうございました。大岡さん、「コギト」の詩人というのは、「四季」の詩人とだぶってますよね、ある程度。もちろん「四季」も素晴らしい詩がたくさんあるわけですが、だいたいどんな評価をなさっていらっしゃいますでしょうか。
大岡 「コギト」の詩人で、僕が非常に優れていると思うのは、もちろん伊東静雄さんですね。それからほかにも二、三人いらっしゃいますけれども、あんまり四季派とコギト派というふうに、それほど僕の中では分かれてないのです。全体として言うと、じつはさっき龍生さんが言われた詩集で五冊本の詩集―山雅房の五冊本がありまして、それからほぼ同じころに、河出書房から『現代詩集』という三冊本でアンソロジーが出ました。わたくしは、その両方とも買っているのですけれども、非常に影響を受けたと思うのは、河出書房のほうの『現代詩集』三冊本で、そのなかにある中原中也とか三好達治とかこれらは本当に愛読しました。そのために、そういう意味で言うと、むしろ河出書房『現代詩集』に入っている四季派という感じですね。
それで、この人たちのものを読んだ上で、一高に入ってからすぐの頃に、一年か二年上の、高等学校の一年二年上というのは三年も四年も上の場合もあり得るのですが、その中の一人で都留さんという人がいて、その方が寮の廊下で「おい、君は詩を書いてるんだろう、そんならこれを買え」と言って、無理やりに買わされて非常によかったのは、中村稔の『無言歌』なのです。その『無言歌』が非常に瀟洒なきれいな本で、あ、こういう本屋から俺も詩集を出したいなと思ったのが「ユリイカ」なのです。その希望は果たせたわけですけれども。『無言歌』がわたくしにとっては四季派の抒情詩の一番典型的なるものだと思っています。だから中村さんが、自分が正統な継承者だと言われるのは当然なのです。つまり、単なる抒情じゃないのです。抒情のなかに非常に激しくこころざしがあるのです。それが唐・宋の詩人にもかなり近いような、一種のこころざし、それも悲壮感に満ちているトラジックな感じ、そういうものがこの詩集のなかには非常にあって、それは生とか死とかいう問題も全部含んでいる。そういうものの影響がわたくしはどうしてもあると思いますけれども。だから、四季派と言ったらむしろ中村稔から始まると言ってもいいようなところがあるのです。ただし中村稔以後はない(笑)。
中村 大岡さんから大変面はゆい発言をいただいたわけですけれども、ようするに一高―東大法学部という学閥は、日本の政治を非常に悪くしたこと、日本の社会に対して非常に大きな責任を負っているところだと思うのですが、完全にエリート社会でございまして、わたくしは大岡さんが一年に入ったときに大学に入っていたのですが、大岡さんが一年のときに「向陵時報」というのに発表した詩を、わたくしはいち早く目を止めて、この人はいい詩人だと(笑)。そういう評価が、いわばいま話に出た都留であるとか橋本一明であるとか伊達得夫であるとか、あるいは先輩で言えば中村真一郎さんであるとか、加藤周一さんであるとか、そういうところへパーッと広がるような、大変恵まれた世界にわれわれは育ったのです。ですから、わたくしの場合について言えば、わたくしが大岡さんの詩を認めたからといって大したことはなかったのですが、わたくしが「向陵時報」に発表した詩を中村光夫さんが認めてくだすって、中村光夫さんが、当時山本健吉さんや吉田健一さんと一緒にやっておられた「批評」という雑誌に、「向陵時報」に出した、一八歳のわたくしの詩をそのまま転載して下さるというような大事件につながった。ですから、さっき秋谷さんがおっしゃったような意味での投稿というようなことは、わたくしどもはない。たぶん大岡さんも経験がおありにならないし(大岡―ありませんね)、わたくしもない。それから、大岡さんについて、もう一つ申し上げると、大岡さんは「コギト」なり保田與重郎を戦後に読んでおられるのだけれども、わたくしどもは戦前戦中に読んでいるわけです。それで、保田與重郎の『日本の橋』という評論に非常に感銘を受けました。ところが『日本の橋』を除くその後のだんだん神がかっていく保田さんには、もうとてもついていけないと、そういう苦々しい思いを「コギト」の人たちに思っていましたし、それから立原道造の晩年に、立原道造が「コギト」に近づいていくわけです、芳賀檀さんなんかを通じて。そういう形で、立原道造がもっと長生きしたらばいったいどういうことになったんだろうということを、わたくしはその後も立原道造を考えるたびに、つねに思うのです。その辺が、大岡さんとわたくしは三年か四年しか違わないのですけれども、そこら辺のところで結構意識のずれというか、理解のずれがあるわけです。
司会 どうもありがとうございました。時間が経過いたしましたので、一応第一部を終わります。第二部の初めは長谷川さんに、ひとつ抒情詩批判をお願いし、そこから開会するということに(笑)。あと、朗読になりますので、一応シンポジウムのほうは中断いたします。ありがとうございました(拍手)。
――劇団とらばとーるによる現代詩人の作品の朗読――
「恨(はん)」を越える詩を
司会 では、これからシンポジウム第二部に入ります。先ほど予告しましたように、小野さんの、いわゆる「短歌的抒情を排す」という詩論は有名ですよね。ただ抒情という言葉は、なかなか簡単そうで難しいので、ただ抒情詩排撃と言ったら、古典的な定義では、詩というのは抒情詩と叙事詩と劇詩、アリストテレスの詩学なんかでもそうですよね。しかし、完全な叙事詩、完全な抒情詩というものもないので、叙事的な抒情詩、叙情的な叙事詩というようなところで、なかなかはっきり分けるのは難しい。小野さんなんかも、おそらく比喩的に、日本の、日常的になんと言うか浅い皮膚感覚的な、思想性まで高まってない抒情を排撃しているのだと思うのですけれども、小野さんの一番弟子の長谷川さんから、抒情とはなにか、いわゆる抒情詩を排するというのはどういう意味かをお話しいただければと思います。
長谷川 それは、先ほど中村さんがおっしゃったように、戦争中の四季派の抒情詩が、つまり現代史――ポエムの現代詩ではなく歴史の「史」の現代史がない、皆無だということの観点に立つわけです。それは、大岡さんにやられるかもしれないけれども、保田與重郎の「日本浪漫派」というのは、いろいろ古典の材料はいっぱい持っていたけれども、古典的見解は持っていたけれども、あの当時の現代史という歴史の観点がなかった。これは橋川文三なんかの考え方とわたくしは同じです。そういう意味で、小野十三郎さんの短歌的抒情を排すというのは、これは分析すると難しいのですけれども、これを言い始めたのは、昭和一二年頃のプロレタリア歌人の赤木健介さんがまずそれを言いはじめて、それから小野十三郎さんがそれに呼応して、そして中野重治さんが「お前は赤ままの花やとんぼの羽根を歌ふな」というふうな作品を書いたわけです。その辺からわたくしもそういう四季派に対する、抒情に対する抵抗があるわけです。
しかし小野十三郎さんは、九十何歳まで生きましたけれども、わたくしが現在見ている感じでは、途中で放棄したなあ、あれは。つまり短歌的抒情の問題を放棄したと思うのです。われわれ後輩に問題を提出したけれども、それを実際にやったかどうかということになりますと、わたくしはそれを放棄したように思うのです。簡単に申し上げますが、抒情詩というのは、突き詰めていくと怨念になるんじゃないかと。日本で言えば怨念、韓国で言えば恨(はん)になる。それをまた越えて行かなければならない。恨を越える、怨念を越える、恨みつらみを越えて行く、その越えていったところの抒情詩というものは出来ないものだろうかというふうなことを、わたくしは前から考えているわけです。
ゆえに、怨念というのは自分で持っているものもありますし、それから恨の場合は、韓国の詩人たちのあの民族的な恨ですね。これは金さんなら金さんという同族間で恨が一応確立している、それが村落共同体にまでその恨が広がっていく。その村落共同体が、今度はもうひとつ大きな群落共同体に拡大していって、今度は国としての、国家としての恨になる。こういうふうに拡大していく。日本の怨念の怨というのは個人的なもので、これは身勝手なものですから、これはどうも拡大していかない、ばらばらになる。そういう意味では、わたしくは大変単純でありますけれども、韓国のほうが正しいと思います。
ゆえに、韓国の抒情詩というのはいったいなんだろうかと。そういう抒情を若干わたくしは否定したばっかりに、えらいしんどい目に会っているわけであります。どうしていいかわからないような感じですけれども。しかし怨念の怨を越える、そして韓国的な恨のそういうものを越えていくところに、新しい抒情詩は出てこないか、すっきりした抒情詩というのが出てこないかなと。それは中村さんがおっしゃった、社会的なものをちゃんと身につけた抒情詩というものが出てこなければならないというふうに、短絡的に思うわけであります。それで答えになりませんでしょうか。
司会 うーん、まあちょっと一〇〇%とは言えませんけれども。では抒情詩という言葉で、まるまるこれは抒情詩だというときは、何を指しているのですか? これは抒情詩だから駄目だとよく言いますよね、長谷川さんは(笑)。
長谷川 それはですね、なんと言いますか、これはわたくし個人の考えですけれども、社会的なものを身につけますと、引きつけてくると、ル・サンチマンみたいなもの。ル・サンチマンというのは、これはニーチェが言ったんだけれども、つまり権力に対して反権力、権力を取られたほうの人間が恨みを持つわけですけれども、しかしもっとそれを卑俗に考えて、大衆的なそういうル・サンチマン、大衆的広がりを持っているル・サンチマン、それが個人の中にもあると思います。そういうものがない、さらっとした抒情詩というのは、わたくしはあんまり好きじゃありません。
中村 ちょっと申し上げたい。わたくしは、鎗田さんの分類が不適切なんじゃないかと思うのです。ようするに、たとえば高村光太郎の「根付の国」であるとか、「ぼろぼろな駝鳥」とか、そういう詩は抒情詩ではないのかというと、やはり抒情詩だと思うのです。ただ、たぶん鎗田さんが言ったような意味での抒情詩ではなくて、小野十三郎さんが「奴隷の韻律」とかそういったようなことでおっしゃったことは、やはり詩というものは歌っちゃいけないのだというような考え方、短歌的な歌を歌わない、つまり人を陶酔させない、だから典型的な抒情詩というのはどういうものかと言えば、「野ゆき山ゆき海辺行き、まひるの丘で花を敷き、つぶら瞳の君ゆゑに……」というような佐藤春夫『殉情詩集』というようなものが典型的な抒情詩だと。それから、たとえば萩原朔太郎で言えば『氷島』をとるか『青猫』をとるかということは議論の余地がありますが、『氷島』は別にしても『青猫』ですら、やはりあれだけの大変感情的な世界を歌いながら、あの中にはやはり現代文明に対する批評がある。
だから、戦前の詩と戦後の詩と、非常に違うことの特徴の少なくともひとつは、歌うか歌わないかということと、批評があるかないかということが、大きな違いじゃないか。これはわたくし何べんもお話していることなのですが、戦前の詩人は、高村光太郎でも萩原朔太郎でも中原中也でも立原道造でも、みんな短歌をまず書き、やがて短歌に飽き足らないで詩に入っていくという人ばっかりだと言っていいと思うのです。ですから書く詩というのも、おのずから歌うという要素が非常に強い。それに対して戦後の詩人たちで、詩を書く前に短歌をつくったという体験を持っている人は、たぶん大岡さんを除いてはいないので、それは大岡さんみたいに非常に意識的な人で、本来批評的な精神の旺盛な人だから、大岡さんのような詩になったのであって、むしろ、どちらかと言えば俳句から入った吉岡実であるとか安東次男であるとか、そういったような人たちが、現代詩のかなり前衛的なある部分をつくったんじゃないかというふうに、わたくしは考えているのです。
小野十三郎における「短歌的抒情」
司会 ありがとうございました。短歌にお詳しい大岡さんいかがですか。
大岡 僕は別に短歌に詳しくはないけれども、いまのお話で言うと、中村さんのおっしゃっていることは、僕もだいたい同じような考え方ですから、あまり問題はないのですけれども。龍生さんが、小野十三郎のことをおっしゃいました。わたくしもじつは小野十三郎さんは好きで、ずいぶん読んだのです。そして小野十三郎論というのも書きました。書いて、結局小野さんとお別れするつもりで書いたのです。もちろん小野さんとはぜんぜん僕は知り合いでもないけれども、この人に、俺は惚れてた、ある時期。だけれども、駄目だったというふうに、訣別するために書きました。初期のわたくしの批評は全部そうです。その人にすごく惚れてた、だから別れるためにということで、全部バイバイという評論なんですね、わたくしの批評は。小野さんの場合には、短歌的抒情の「奴隷の韻律」と彼は言ったのですけれども、その「奴隷の韻律」を体現しているのは、小野十三郎自身だというふうに思ったから、それでお別れしたのです。その作品の実例もいくつか挙げましたけれども、早い話が、非常にはっきりしているのは、小野さんの詩の中で、五七調の詩がいくつかあるのですが、そういうのを見るとじつにくだらない。だから、これは駄目だと思いました。あの人、本当にいい詩人なんだけれども、やっぱり短歌的抒情というものを持っていて、そこに足を掬われると完全にそうなっちゃうんですね。小野さんは、ある意味で言うと、そういう短歌的抒情ということを一所懸命言ったのは、自分自身の中にある短歌的な抒情というものを、まず絞め殺さなければならなかった、それで言ったんだと思うのです。
さっき、龍生さんが言われたように、あるときに小野さんが別れたかも知らんと、短歌的抒情に対する批評から別れたのかも知れないというふうに言われたけれども、そこのところ、龍生さんがどういうふうに考えていられるかわからないけれども、わたくしには、小野さんはやっぱり無理していたと思います。本当は七五調でも書けた人だと思います。それは書けたって当然なんですけれども。それを『大海辺』のころまではとっても我慢して、そういうことを抑えて、そして、工場地帯のこととか、あのころの詩人としては工場地帯のことやなんかを、あれだけ書けたのは立派な詩人だと思うのですが。にもかかわらず、そういうことを書いていた時期に、やっぱり七五調の作品もあるのです。それは、ある意味では彼が皮肉で書いた可能性がある。ところが皮肉で書いているのにミイラ取りがミイラになったというところがあるのです。わたくしはそれを見て、ああやっぱりこの人も本当は短歌的な精神がいっぱいある人だなと思った。わたくしは短歌的な世界に多少首を突っ込んでいたということはないけれども、餓鬼のころから、生まれたときからそういう世界に入っていたわけですから、そこで見てきましたから、短歌も俳句も現代詩も――俳句はあとですけれども、短歌も現代詩もわたくしにとってはそれほど違わないのです。違わないというのは、つまりわたくし自身が一人の人間である限りは、短歌でも現代詩でもできるよということが初めっからあったのです。だけれども、そういうことは誰にも認められないままにずっと来ましたけれども。我がが強い人間ですから、それでなんとかそのうちにわかってくれる人にはわかって貰えるだろうと思って、ずっときたわけですけれども。短歌と俳句と現代詩を分けて考えるということ自体が、わたくしにとってはあまり批評的でないのです。批評ということはどこにいても批評である、それが批評なのです。それは詩でも同じなのです。だから詩も批評も同じだというところに立たない限り、短歌は短歌、俳句は俳句となっちゃうのです。そういうふうにわたくしは思っています。しかし、ある意味で言うと、こういう考え方はこの日本では受入れられません。しかしわたくしは頑固にそう思っています。
ニュー・ロマンティシズム
司会 長谷川さんにたすけ船を出すわけではありませんが、これはやはり時代ということもあるのではないでしょうか。小野さんの詩論は昭和二〇年代初期から言われていたが、大きく問題にされてきたのは中期から後期にかけてで、昭和二五年には朝鮮戦争が始まっています。なにか日本の詩はもっと社会性を持ち、批判性を持て、それから一種の記録性も持てと、言いたかったのではないか。これは長谷川さんが、映画的なカットバックの詩を書いた戦後の旗手であるというようなことを、戦後詩史には書かれているわけですが、そういう現代詩を伸ばすためと言うか、ある程度現代詩を変えるための、そういう警告的な理論じゃなかったかと思うのですが。ではその件はその件としまして、秋谷さんに一言。
秋谷 そうですね、小野さんの、いわゆる短歌的であるということの問題で、僕はあれは短歌的詠嘆というのかな、日本の伝統的な形式が持っているものへの問題だと思うのです。同じころ、桑原武夫さんが「俳句第二芸術論」というのを言い出して世間を騒がせたわけですが、これなんかも主として形式論から出発しているような気がするわけです。先ほど、詩はこころざしであるということ、これは東洋文明の中心だと思いますから、当然、日本もそのなかでのことをいろいろやってきたと思うのです。僕らは、戦後「地球」という雑誌でネオ・ロマンティシズムというのを主張したわけですが、これも簡単に言えば現代における抒情というものを考えていこう、いわゆる確立していこうという一つの詩の活動であったわけです。僕らはたとえば第二次世界大戦中、戦争へ行っても、一九三〇年代のアメリカの詩人とかイギリスやドイツの詩人がつねに頭のなかにあったのです。自分たちと同じ時代の詩人たちはなにをやってるんだろう、やっぱり戦場で戦っているんだろうかと。そのなかで、イギリスにはニュー・ロマンティシズムという一つの流れが起きて、彼らは戦場で非常にロマンチックな詩を書いた。それは決して戦争詩ではなかったのです。文字通り戦争詩、戦場詩だけれども、いわゆる日本で言う戦争詩ではなかったということは、非常に大きなショックでした。それは戦後になってそれを翻訳して、日本に紹介した詩人、これは「地球」の同人の松田幸雄という詩人ですけれども、彼が初めてイギリスのニュー・ロマンティシズムを紹介して、僕らは共感したわけです。
いわゆる一個の人間として、現代というのは不条理に満ちているわけですから、その不条理そのものを人間存在の理由としていこうとか、そういうものは当然、詩の批評性というものは起きてくると思うのです。ただ単純にわれわれはそれを受け止めるのではなく、そこからもう一歩そこに深く入り込んで、批評を確立していくというのかな、そういう批評で見ることによって、抒情というものが変わっていくことを考えてきたと思うのです。だから先ほど朗読していただいたけれども、たとえば西脇順三郎の「旅人かへらず」とか、村野四郎の「枯れ草のなか」でもいいですね。鮎川信夫の詩も、田村隆一も、やっぱり一種の抒情詩ではないかなと思いました。それはただ単なる抒情というふうに、だから抒情詩は駄目だというふうな言い方も、これはちょっと狭義で、端的に過ぎるかなという気はするわけです。なぜ抒情詩だから駄目なのかということはまったくないわけで、だから本当にすぐれた抒情をわれわれは見つけて、そういうなかで、たとえば村野四郎の「枯れ草のなか」でも、人間の性というものを一つのなにか墜落していくものに比喩的に書いているわけですが、その事物のイメージというのですか、そういうものに置き換えていくことによって、やはり抒情というものが一つの形というか、そういう一つの抒情の魂の原型をつくっていくのではないかなという気はするわけです。
長谷川 抒情というのが堂々巡りであるということは、もうだいぶ前から考えているのです。いくらひねくり回しても駄目だと、つまり限界がある。最初わたくしが申し上げましたように、自分を突き抜けていく自分というものの詩の情がなければ、限定したもののなかでいくら精いっぱいやったって駄目だというのが、わたくしの詩を創るときの姿勢なんですよ。だから、これはしょうがないのです。
それから、小野十三郎さんは、さっき大岡さんがおっしゃったように、これはもの凄く短歌が好きな人だったのだと思います。しかし短歌が好きだったんだけれども、もし、五七五七七で短歌をつくらしたら、非常に下手くそな人だったと思います。そういうことも若干要素はあると思います。しかし、小野十三郎の出自というか、生まれつきのそういういろんな問題が絡んでいたのだろうと思います。そして、さっきも言った中野重治さんなんかも、ああいう「赤ままの花を歌ふな」という問題がありますから、そういうものも絡んできます。それから、中村さんがおっしゃった、批評の問題ですけれども、これは小野さんが「批評の錘を深く沈める」というふうなこともおっしゃっているわけですが、では小野さんの全作品のなかに、批評の錘が沈んでいるかというと、それはなかなか沈んでないものもたくさんあるように思います。その辺でやっぱり小野十三郎とは大岡さんは訣別したと。しかしわたくしは一応小野十三郎が取っかかりですから、これは自分が生きている間になんとか始末をつけて、でっち上げでもいいから始末をつけていこうということなんですよ。
「短歌」――茂吉と文明
司会 長谷川さん、ちょっとうかがいますが、小野さんは俳句には寛大なんですか。
長谷川 俳句もあまり認めなかったと思います。だから俳句も下手くそじゃなかったかと思うのです。
司会 それはつまり、定型がいけないという意味ではないのですね。なかにある情緒的要素がいけないと。もっとも俳句は、むしろ象徴の文学だというふうな言い方をしますね、一般的には。短歌はどちらかというと生活記録みたいな、生活記録にささやかな情緒や感情を混ぜてまとめるみたいな。だから短歌のほうが攻撃しやすいということはあるのかも知れないが……。
長谷川 しかし、短歌でもじっくり見ていくと、たとえば斎藤茂吉と、それからそのお弟子さんである佐藤佐太郎というのを、じーっと見ていくと、やっぱりそこに抒情の違いというのが出てくるのです。そういうことを小野さんはやらなかった、勉強しなかった。しかし、こちらは斎藤茂吉と佐藤佐太郎の違いというのはどこにあるんだろうというふうなことを掘り下げていきながら、斎藤茂吉はどうもつまらないけれども……、大岡さん、詰まらないのですよ、わたくしは。
大岡 わたしも、つまんないです(笑)。
長谷川 しかし、佐藤佐太郎はどうしても張りついてくるのです。そういうところがあるのです。
大岡 中村さんは茂吉を……。
中村 当然、茂吉は日本最大の詩人と思っているわけです。
大岡 わたくしはぜんぜんそう思いません(笑)。ここで論争すると面白いのだけれども、時間がありません(笑)。
中村 さっきの話でひとつふたつ感想を申し上げると、大岡さん、土屋文明が「鶴見臨港鉄道」をよんだのは、あれは昭和八年ころですね。あの無機的な世界というのは、小野十三郎さんの戦後のいい作品と非常に似てます。非常に近いところです。非常に近くて、しかし「鶴見臨港鉄道」というのは、土屋文明の力量をもってしても失敗作で、小野さんのあの一連の作品というのは非常に立派な作品です。その後の小野さんは別にして、あの時期の小野さんの作品というのは非常にいいものだったと考えているのです。
大岡 僕もそう思います。
中村 安心しました(笑)。かなり大岡さんとは同感するんだけれども、やっぱり同感出来ない部分というのはどうしても残るので。で、そういうことが一つなのですけれども、だからやっぱりああいう素材は短歌では歌えないんじゃないかというのが僕の感じなのです。やっぱりそういうことこそ、詩でなければ歌えない世界というものがあるのだということが、一つの感想なのです。
もう一つの問題というのは、さっき申し上げたように、「奴隷の韻律」とかなんとか言いましたけれども、たとえば「赤ままの花を歌ふな」とか、「金よ さやうなら李よ さやうなら……」という「雨の降る品川駅」の詩なんかも、あれもやっぱり歌っているんですよね。やっぱり戦後詩というのは、歌わなくなった、歌わなくなったために読者を失った。だから、中原中也のように、歌がある詩というのは、依然としてやっぱり渇望されているんだけれども、そことわれわれ現代詩を書く人間との溝を埋めるにはいったいどうしたらいいのかというところが、わたくしたちがいま袋小路に入っている問題なんじゃないかと、僕は思っているわけです。
司会 「赤ままの花やとんぼの羽根を歌ふな」という詩は、抒情でなく、リアリズム、いわば社会主義リアリズムに転換せよ、と自分に言い聞かせる、自戒の言葉というように、一般にはとられているでしょうね。しかし、ここでやはり歌ってしまった。
窪田空穂の長歌
司会 さて、この問題は、まだ一時間やっても結論は出ないと思いますので、ちょっと次に移りますが……
大岡 その前に、短歌の関係でちょっと。われわれはいま短歌短歌と言ってますけれども、歌人がどういう形式を持っているかというと、短歌形式プラス長歌というものがあるのです。長歌をつくれた歌人は非常に少ないのですけれども、現代にもいたのです。たとえば、わたくし今度、岩波文庫で『窪田空穂歌集』というのを編纂して出しました。そこには意識的に空穂さんの長歌と、それから空穂さんが明治時代につくった新体詩ですね、そういうものを入れました。入れてみて初めてわかってくるものがいっぱいある筈だと思って入れたのですけれども。その一つは、長歌というものが、形式的にぐーっと言葉を締めつけて、なおかつ非常に開放的な要素があって、叙述がいっぱい出来るのです。とくにあの人の「捕虜の死」という、自分の息子さんがシベリアで捕虜になって結局死んだのです、非常に酷い条件のもとに。それについて書いたもの凄く長い長歌がありまして、それは本当に立派な、現代詩史のなかで、ちゃんと位置を持つべき詩だと思いますが、それは空穂さんの業績を語る人でもまだ忘れてるのです。ですからわたくしは文庫本でこれでもかこれでもかと出しておきましたけれども。で、長歌という形式を忘れてやしないかというのがひとつあるのです。歌人たちはいま長歌をつくれません、ほとんど。それから現代詩人は、長歌なんていうのが存在していること自体認めてない。まったくわたしに言わせると、お前さんたちはおかしいよと言いたい。
長歌というものは、ストレートに何かを言うことができるというのと、ストーリーを創れるということがあるのです。「捕虜の死」というのは、息子さんが捕虜として死んだそのことを、空穂さんが病床にあって書いているのです。病床にありながら、シベリアでどういうふうにして死んだかということを、じつに克明に書いてある。それは戦友が教えに来てくれたことを病床で耳にして、それだけで書いているのです。だけど、じつにリアルな描写に満ちている。それは想像力の問題、想像力がなければぜんぜん駄目です。想像力のある歌人だったら、長歌をつくってもこれだけ立派な詩ができるということが言えるのです。そういう意味で言うと、わたしは短歌はどうのこうのとか、現代詩はどうのこうのということを言うのは、ちょっと足りないのではないか。それだったら長歌も入れて、日本の詩というもの全体を考えるべきだ。それは韻律というものは長歌には絶対に必要ですから、韻律はあります。それは五七五と違うのです。五七五七五七といって、最後に七七となるのが長歌形式ですけれども、五七調というもののなかに入るべき内容を入れるだけではなくて、入らない内容をどうするかということがあります。現代詩だってなんだって入れられないものはいっぱいあるのです。そこをなんとかして入れるということに詩人の力量がかかっているわけですけれども、いまの現代詩はずるずるですから、そういう形式的な制約はほとんど感じないで皆さん書いている。それが、今の現代詩が読まれなくなっている理由の一つです。
中原中也は、五七調なら五七調、七五調なら七五調でちゃんと入れていて、それからそこに入らないものを捨てているのです。その捨てたのはなにかということを、われわれは考えなければいけない。それが批評なのです。批評がないから、全部なんでもかんでも入れちゃえばいいという考え方が、いまの現代詩を毒しています。わたしはそう思っています。
「西脇から吉岡へ」か?
司会 ありがとうございました。一応この問題はここで打ち切りまして、比較的最近、去年出た本で、野村喜和夫さんと城戸朱理さんの『討議・戦後詩』、あれ、精読はなかなかできないのですけれども、ただ総括的に感じると、あの年代の、全般的とは言わないけれど、かなり若い世代のオピニオンリーダー的な人たちは、結局、西脇順三郎から吉岡実へという線を、現代詩の主流のように考えているように受け取られるのです。それがまた一面、どうも現代詩の世界を狭くしている原因ではないかと思うのですが、これはどうなのですか。現代詩の主流ですか? 大岡さん。
大岡 いやあ、ちがいます……。少なくとも西脇さんはそういうふうに言われてもいいけれども、吉岡実はまだ無理ですね。そういうことは言えないです。
司会 無理というのは、まだ評価は決まっていないという……
大岡 いやいや、わたしは評価なんかしたくないけれども。吉岡実は親しい友達だったからわかるけど、彼が、自分はこんなこと書いていいかなあと思って恐る恐る書いたものでさえも、もの凄く素晴らしいと褒められるでしょ。この傾向が非常に現代詩を毒しています。
司会 ただ、一部の若い人には、西脇から吉岡というのは、ちょっと偶像的に思われているところがありますね。それで、現代詩というのは、結局いまの現代詩をそのままというのではないけれども、やっぱりシュールレアリスムというのは、これを通ってきているというのが現代詩を形成している大きな要素だと思うのですが。しかし、シュールレアリスムの専門家ともいえる飯島耕一さん辺りは、ぜんぜん今までのシュールレアリスムの解釈は間違っていると、あれはシュールというのは意味が違うのだ、超えている意味じゃないのだと、リアリズムのもっとも熱して高揚した状態と解すべきだと言って、いま俳句へいこうとしているわけですが、だから、あの人の定型論というのも、そういうことが根にあるわけですよ。それでエズラ・パウンドとか、それからいわゆるシュールレアリスムの詩人たちは、じつは俳句が大好きだったのだと。それで、むしろ俳句のほうが彼らにああいう詩を書かせた源泉になっているというようなことまで言ってますが……。
大岡 形については、俳句形式というのは非常に魅力的です。それはフランスのシュールレアリスムだけではなくて、イギリスであろうとアメリカであろうと、みんなそうだと思います。だから、それはそれでいいのですけれども、俳句というものを受入れているというふうには思えません。なぜならば、彼らは、西洋の詩人は、日本の俳句を日本人が理解するような形ではぜんぜん理解してませんから。それは僕はよく知っています。それは当たり前のことです。日本語ですから、あれは。日本語がわからなければわかるわけはないのです。五七五という形式は非常に普遍的な形式ですから、その形式を受入れることはいくらでもできますし、実際、面白い作品はいっぱいあります。シュールレアリストで言えば、ポール・エリュアールなんていう人の詩は、結構、ある時期だけですけれどもハイク風でもありました。ただし、作品は面白くない。
司会 すると、現代詩の現地点というのは、シュールレアリスムを克服した地点にいるのですか? 日本の詩人は。
大岡 ぜんぜんしてません。シュールレアリスムなんて何も入ってません。入ったことがない、まだ。
司会 西脇さんはどうなのでしょう?
大岡 西脇さん? 西脇さんは、ご自分でも言っているように、わたしはシュールナチュラリスムだとかなんとかと言ってますね。シュールレアリストだって言っている人は一人もいないのじゃないですか。いま大方のひとはみんなそう思っているでしょうが、瀧口修造さんを日本のシュールレアリストだと思っている人が多いと思います。だけど、わたしは瀧口さんと親しかったからよく知っていますけれども、瀧口さんは、そう言われるたびに本当に身を捩って嫌がった。ですから、日本では自認しているシュールレアリストというのは三流のやつだけです(笑)。
秋谷 だから、シュールレアリスムというのは、日本の風土にはまだ本当に根づいてないのじゃないでしょうか。ただ俳句的に言えば、俳句は造型性がありますから、むしろ現代詩に近いかなという気はしますけれども。だから、むしろシュールレアリスムと言わないで、もっとモダニズムというのですか、西欧から入ってきたいろんな詩の手法とか精神を、むしろわれわれは考えるべきで、全部シュールレアリスムに限定するということには問題があるのではないでしょうか。
「現代」詩?
司会 そうすると、秋谷さん、現代詩を現代詩たらしめているものはなんですか、イズム的には。なんとなくみんな書いているわけですか?
秋谷 これは、現代詩とはなにかというと、現代を書くから現代詩だって、非常に単純なんですけれども。だからやっぱり現代を書くということは大変難しいのではないでしょうか。じつは現代を書いているつもりで、実際はずいぶんむかしのことを書いてるかもわからないし。だから現代詩というのは、やっぱり時代的な区分であって、おそらく明治の新体詩の詩人たちだって現代詩を書いている、現代を書いていたのではないでしょうか。だから万葉集の人たちも、天平の時代でも、彼らにとってはその生きた時代が現代であるわけですから。言い換えれば、歴史というものを僕ら一人一人がきちっと静かに、激しくというのかな、そのなかで表現していくものが詩になるのじゃないでしょうか。
司会 そうすると、もう五〇年たったから、戦後早々の詩は現代詩じゃなくなっていきますか。
秋谷 あの分け方は、大岡さん、別に近代詩でも現代詩でも、それほど違いないでしょう? 近代詩だから時間的に区分的に言って、ああいうのは過去のものだという考え方はないような気がするのですけれども。
大岡 その時代の人にとっては「詩」でしかないのです、どの時代も。だから、近代詩と現代詩というのは、後世のやつとか、あるいは脇にいるやつが言うことであって、その本人が、わたしは現代詩を書いていると思っていて、それで満足しているとしたらおかしな話で、現代詩なんて書いているやつはおかしいよ、と思います。詩は書いている、詩は。詩はつねにありますから。だけど現代詩というものは、いま書いているのが現代詩ならば、昨日書いたのは近代詩(笑)と。僕はそう思ってますけれども。だから昨日俺が書いたのは近代詩だと、今日、いま書いているのは現代詩だと、そういうふうに思ったっていいのではないですか。
秋谷 だから、先ほど朗読したあの詩人たちはみんな近代詩の詩人かと言えば、そうも言えないところがあるような気がするのです。むしろ、いま現代詩だとして書いている詩が近代詩であるかもしれないし。いま一番問題なのは、もちろん短歌、俳句、長歌も含めて、やっぱりそれは詩であることは間違いないけれども、むしろ散文との拮抗というのかなあ、その辺はやっぱりいま詩人は考えていかないと、散文で書いてもいいようなことを詩で書いたりしているようなものも、まったくないわけじゃないのです。僕は、むしろ詩と散文との問題というものが、僕は大きな課題に、これからはそういう時代になってくるような気がしますけれども。
大岡 まあそうですね。本当にその通りだと思いますけれども、問題は、では日本に散文はあるのかということですね。日本の散文ってなんだって言われると、これだと言えるものがあるかというと、僕はそれは問題だと思います。散文というものも、詩というものも、本当にやわなことしかみんな考えずに書いている、と思います。僕は非常に破壊的なことを言ってるかも知れない。
秋谷 破壊的というか、否定的と……。
大岡 僕は非常に否定的ですけれども、現代に対して本当に否定的です。
秋谷 でも、そういう中からまた創造の発展というのは生まれてくるんですよ。
司会 教科書的な分け方だと、萩原朔太郎以降を現代詩というと。だいたいそういうのが教科書的な考え方でしょう。
大岡 詩の世界の、近代詩とか現代詩とかいう、それの考え方で言うと、萩原朔太郎は明らかに近代詩人ですね、現代詩人ではないですね。だから教科書の定義と違うのです。
司会 いや、教科書そのものというより、教科書的な考え方は朔太郎からだいたい始めますよ、現代詩というのは、いわゆる民衆詩は一応アウフヘーベンしたという形において。
大岡 近代も現代もどうでもいいや(笑)。
秋谷 だから、やっぱり「詩」であっていいわけですよ。だから詩を募集するときに、最近は現代詩大会とか現代詩募集とかということが目につくけれども、いまわれわれが書いているから現代詩で、そういう意味での考え方ぐらいじゃないでしょうか。
大岡 単なる形式的な区別にすぎないですね。現代詩と言っているときは、短歌とか俳句とかいうものを一方に置いて考えているから現代詩と。それだけだったら詩でいいのです。
司会 すると、現代詩というのもそろそろ止めて、詩と言いますか。日本現代詩人会を日本詩人会にするとか(笑)。長谷川さん、いわゆる現代詩と、また使いますが、これを形成してきたのは、いまの比較的若い人は、西脇さんをガイネーシス的とかってむずかしい言葉まで使って、母神的とか大地的なとか、西脇さんから始まるような考えを持っているように思われますが。僕は、むかし「時間」にいたせいじゃないけれども、北川冬彦の功績が非常に大きいと思うのです。新散文詩運動とか長編叙事詩運動とかネオリアリズムとか、なにか北川さんはH氏賞事件で抹殺された感じだけれども、一番はっきりした形で問題提起したのは、あの人ではないかと僕は考えていますが。
長谷川 そうですね、北川さんはやっぱりちゃんと評価しないといけないですね。現代詩といったらなんですが、詩の歴史の上でちゃんと復権をしなければならない人だと思います。先ほどからずっと聞いてますと、日本におけるシュールレアリストというのは僕ぐらいしかいないんじゃないでしょうか(笑)。つまりリアリズムを追求して、リアリズムからぱーっと妄想に入っていくという、そういうのは僕ぐらいしかいないんじゃないかなと自慢したいんだけれども(笑)。
司会 それは大変新しい定義、画期的な定義ですよ。それで、じつはいわゆる現代詩、いま現代詩ということは評判悪いけれども、大事なのは政治の問題だと思うのです。戦後詩というけれども、言葉どおり、やはり戦後詩、戦後の詩でしょう。戦争というところ、敗戦というところから出発している。だから辻井喬さんなんかは、一九七〇年代かな、連合赤軍の浅間山荘事件をもって、日本の現代詩は終わったという。政治に対する姿勢というものが、戦後詩の骨格をつくってきたと思うのですけれども、その点はどうでしょうか。いまそういう抵抗軸はないですよね、若者はみんな政治離れでぜんぜん関心がないし。あのころは若者――詩人はとくに政治に関心を持って、そういう中から黒田喜夫とかああいう人も、長谷川さんもそうだろうと思いますが、谷川雁とかそういう人たちが生まれてくる。なにかこうバネを失っているという、政治と詩との関係というのは、中村さんいかがですか? 政治が起爆力でなくなったという点は。
中村 わたくしは、人類の未来について大変悲観的だから、今後、やっぱり危機的な状況が遠からず来るであろう、そうすると、もっといい詩が出るであろうと、そういうふうに思っています。
それから、さっきのお話で言えば、シュールレアリスムがないと大岡さんはおっしゃったけれども、そもそもがリアリズムがあったのかということがあるし、それから日本の自然主義と言われるものが、フランスにおけるナチュラリスムというものとどれだけ違うのかということも検証されていない。わたくし弁護士ですから、ちょっと申し上げると、じつはわたくしの知り合いの、もうお年を召したフランス人の弁護士なのですが、フランスの裁判というのは、いまはちょっと短くなったのですが、ほとんど五時間くらい裁判官を前に弁論というのをするのです。事件の要点をずっと説明して説得力をもって話す。その弁護士さんは、フランスで非常に名の知れた偉い人なのですが、その弁論の前の日に何をするかというと、ラシーヌを読む。ラシーヌを読んで自分の裁判所における弁論のリズムをつくる。そういうのが伝統というものなのです。そういうような意味で、大岡さんが言われた、日本には散文もないんじゃないかと言われるのは、おそらくそういうようなことに近いのだろうと思うのです。
大岡 そうです。
中村 それから、さっき申し上げた、斎藤茂吉は最大の詩人だとわたしは思っていますけれども、同時に最大の敵だと思っているのです。そのことだけちょっと。
詩に未来はあるか
司会 時間があと一〇分ですので、戦後五十五年の証言にはちょっとなりにくかったと思いますが、結論的に、詩というものの未来性と言いますか、現状を踏まえて未来性について、お一人三分ぐらいずつ、秋谷さんからお願いします。
秋谷 三分というのは難しい時間です。ようするに、もう美意識というようなものを、さっきの野村喜和夫さん、城戸朱理さんもそうですが、やはり言葉の実験派というのかなあ、僕は言葉というものをいろんな実験をしようと考えたと思うのです。しかし、そうしたいろんな美意識があっていいけれども、これからは美意識の代わりにもっと人間的な体験というのか、そういうものが必要な事態になるのではないでしょうか。つまり、創作体験ということが重要だと抑えておいて、人間の体験であるわけですけれども、僕は、前にカイバル峠の所へ行って、東西文明の十字路、あすこを越えてアフガニスタンに入ったのですが、もの凄い難民の行列に遭遇するわけです。そういうなかに旅芸人がいて、彼らは自称吟遊詩人で、自分で詩を創ったりなどして、それを楽器に合わせて歌って、難民を慰問しているわけです。しかし僕らは詩を書いているけれども、ただそこを旅人として通過するだけに過ぎなかったのだけれども、やっぱりそういうものをこれからの時代は考えていかなくてはならないのではないか。それは、世界を見るわれわれの目にも通じるものではないかということを考えました。
大岡 わたしは、現代の詩の問題というのは、七〇年代以後始まっている。いわゆる情報化文明の爛熟期、これがずっとまだ栄えていて、いまだに情報産業だけが栄えています。ほかの産業はみんな沈んだ。情報産業はそれでいい気になっているとわたしは思います。いい気になっても仕方がないくらいに、ほかの分野が弱虫なんだ。だけども、考えなければならないのは、たくさん情報を貰えれば貰うほど人間は豊かになると言っている情報化産業をやっている連中のトリック、それはぜんぜん違うのだ。情報というのは、貰えば貰うほどどんどん人間は断片化してきます。これは当たり前のことで、たくさん情報を得たって、それを知性が咀嚼して、自分の思想にして表現しなければならない。だけどそういうことはぜんぜんできないようになっているのです、いま。そういう時代です。だから、さっき中村さんがおっしゃったけれども、やがて大破局がくるだろうと。大破局というのは、わたしはもう一〇年前ぐらいにそういう詩も書きましたけれども、こういう状態では大破局がくるのは当然なのです。日本が最初に来ます。なぜかと言ったら日本人は信じやすいから。何も信用してない民族と違うのです。だからわたしは、散文があるのか、詩があるのかというふうなことをわざと言っているわけですが、散文があるかないかということはどこでわかるかと言えば、そういう批判精神がちゃんとあるかないかなのです。だけど、日本のいまの人々は、そういう批判精神はほとんどない、表現されてないとわたしは思っています。お前はどうしてるのだと言われればそれまでですけれども、わたしはわたしなりに考えてやっています。
長谷川 破局が来ようと破局が来まいと、わたしはたった一人でしか生きられないものですから、もうあといくらもないですけれども、生きざるを得ないわけです。その生きざるを得ない僅かな期間で、新しい素材を求めていくそういう方法、それから自分が現在持っている素材と、それから非常に伝統的な大変大切なものに折衷していく。そういう現在の持っているものと、過去へ溯っていく折衷主義の方法と、それからさっき大岡さんがおっしゃった長歌、これはわたしはやってるのです、勉強しているのですよ、これでも(笑)。長歌のいろんなそのなかにある問題、そういう三つの俎に置いて、新素材、折衷主義、古典の問題、それをちゃんと三つ置いて、破局が来ようと来まいと、たった一人でしか生きていけないということであります。
司会 中村さん、もう一度結論的に。
中村 わたくしは、わたくしたちの時代がもう終わったという感じを強くしておりまして、したがってもうわれわれが発言する場所はないというふうに考えている人間なのです。ただ、これこそ大正か昭和の初めかに寺田寅彦が、もし文明というものが人間の心を貧しくするものであれば、文明の進歩というものは不要なのだということを言っているのです。大岡さんは情報化社会という言葉でおっしゃったけれども、いわば情報化社会と一口に言えるような現代文明の進歩というものが、わたくしたちの心を非常に貧しくしてきたということを痛感しているし、それを乗り越えるだけの力がもうわたくしにはないなあと思う。やはり後世の人に期待したい。そういうふうに考えております。
司会 ありがとうございました。今日は戦後早くから出発しまして、立派な業績を残された代表的な四人、この四人の方が一堂に会してたくさん話すということは、これはまことに希有なことで、非常に貴重なことだったと思います。詩というのは、いわゆる美学的価値を求めていくのか、倫理的価値を求めていくのかというようなことも、非常に重要な問題としてあると思いますが、それはまた別の機会にいたしまして、今日はこれで終わります。皆さんご静聴ありがとうございました(拍手)。
(記録・遠藤和子)