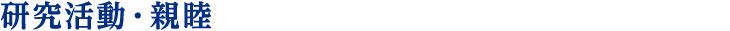現代詩ゼミナール&新年会2025
現代詩ゼミナール&新年会

開会の言葉 郷原宏会長
去る一月二五日(土)、アルカディア市ヶ谷にて、現代詩ゼミナールが14時より16時40分まで五階大雪の間で、新年会が17時より19時まで四階鳳凰の間で開催された。
現代詩ゼミナールの司会は、生駒正朗、冨岡悦子の両氏が担当。
開催に当たり、郷原宏会長より、次の要旨でご挨拶を頂きました。
「この現代詩ゼミナールは、日本現代詩人会が主催する詩人の勉強会です。講師は、日本現代詩の最前線で活躍されている広瀬大志さんです。演題は「Magical Mystery Poetry」という刺激的な演題で、実は私は半世紀、ミステリーの翻訳などをやってきたので、この演題にとても刺激を受けており、期待しています。その後は詩人の朗読会、懇親会と予定しております。勉強の後は宴で大いに歓談して、今日は一日詩ずくめで楽しんでください。」
次に本日の講演者、広瀬大志氏のプロフィール紹介がなされ、登壇された広瀬大志氏より、「Magickal Mystery Poetry」の演題で講演がなされました。
講演終了後は休憩を挟み、会員四名の詩の朗読が行われた。朗読者は、森水陽一郎氏、根本紫苑氏、伊武トーマ氏、高貝弘也氏。BGMを流しての朗読をされた伊武トーマ氏など、四名の個性が堪能できる朗読会となった。
次に冒頭で述べたとおり、会場を変えて新年会が開催された。司会は、犬伏カイ、水嶋きょうこの両氏が担当。
まずは、塚本敏雄理事長の開会の言葉で幕を開け、日本詩人クラブ会長の太田雅孝氏の挨拶、秋山公哉氏の乾杯の音頭で和やかに始まった。
新年会ということで、詩の談義で花が咲いた会場で、司会者は機転を利かせ、一部の出席者を登壇させてスピーチしてもらうなど、宴は楽しいものとなった。スピーチをした会員は、佐々木貴子氏、松下美和子氏、そして新入会員の黒崎晴巨氏、nostalghia氏、森うずまき氏、犬伏カイ氏でした。
また、広瀬大志理事が登壇すると、入会手続きを簡略化したこと、会員を増やしたい旨の話があった。当詩人会を盛況な会にしたいという広瀬理事の意欲が出席者の皆さんに浸透したことを期待したい。
最後は杉本真維子副理事長の閉会の言葉で宴は盛況のなか、終了した。
現代詩ゼミナール講演「Magical Mystery Poetry」講師 広瀬大志氏

講演する 広瀬大志氏
ご紹介に預かりました広瀬大志です。私の詩風は、よくモダンホラーとか言われ、荒唐無稽な話になりますが、詩の不思議な魅力を語っていきます。
モダンホラーとは、後味が悪く、不条理で、不可解で、心理的なダメージを受けてしまい、何でもない日常でふと垣間見た裏側の闇に目を向けて表に引きずり出すストーリーです。
例えば山村暮鳥さんの「風景 純銀もざいく」という詩。いちめんのなのはな いちめんのなのはな・・・。途中でヒバリが鳴いたりしていい風景で素晴らしいのですが、その風景に「包丁」という言葉をポンと投げ入れると、「いちめんのなのはな いちめんのなのはな 包丁 いちめんのなのはな ・・・」恐ろしく不穏な、危ない風景になります。一つの言葉の介入が、脅かすように新しい事実を引き出してしまう。こんな書き方を僕は追求していて、学生時代から公言しており、一つの仮説に辿り着きました。
それを今、初めて公にしますが、「詩はモダンホラーとかホラーも含めたジャンルで言うと、詩の本質はミステリーじゃないのか」という仮説です。
詩とミステリーの特徴を言うならば、詩は「比喩的な表現の中で生み出す言葉の強さ、インパクトというのが知る言葉になっていく」、かたやミステリーは 「イマジネーション、想像力によって新しい表現であるとか、新しい プロットっていうのを発明する」ということですが、両者とも潜在的にこの二つの能力を有すると思っています。
詩はミステリーという仮説を考えていくと、言葉が言葉をおびやかす不安が組み合わさっています。そして詩を作るという流れで言うと、二つ目の仮説は「詩とは事件じゃなかろうか」要は言葉が言葉の世界に起す、さっきの山村暮鳥もそうですが、社会的に事件性のある言葉ではなかろうか。三つ目は「 詩人ってどういう立場なのか」という仮説。詩は事件である、詩はミステリーである。では詩人は新しい言葉を見つけ出し、表現を発見し、あるいは言葉の謎を解く探偵じゃなかろうか。ここから詩人の探偵、もしくは 犯人としての要素を私流に仮説化して説明したいのですが、まだ本題には入りません。
唐突でヘビーな前振りでしたが、これから初めて詩に出会った時に帰っていただこうと思います。初めて感動した詩を読んで、あるいは初めて詩を書いてみた時に、詩はどのようにしてでき、詩のどこに感動したんだろうか、という部分を掘り下げます。
レジメを参照しながら、まず詩の構造を僕流に分析してみます。まず、詩はメロディー、リズム、ハーモニーからなります。メロディとは旋律。詩でいうと語り口調です。リズムとは律動。詩でいえば言葉の刻み方、行間の作り方、連の作り方などを決めるときのリズム性です。ハーモニーとは調整の領域で、詩でいうと韻を踏んだり、連ごとの形を作ったり、あるいはテクニックとして文字のフォントを変えたりすることです。この三つが土台であり、さらに詩を作る要素として二つのファクターがあります。一つ目のファクターはテーマ。このテーマは社会・体験・生活・物語などいくつもあります。二つ目のファクターはテーマを強固にする思想、知識、想像です。このファクターの組み合わせや掛け合わせで詩はできています。
そして詩の表現はどうやるか、僕の独断で考えますと文体、配列、比喩の三つです。また詩の魅力は、自分が思うことを的を得た言葉で言ってくれた共鳴、共感の喜び、詩の言葉の感動にあります。詩の読後は、自分でも詩を書きたくなる。これは他の芸術ではないことです。同人誌でも作ろう、詩集を出そうという意欲が湧いてくる。これは一般的な詩の構造あるいは詩の魅力ですが、詩に惹かれてやまないものは、本当にこれだけなんだろうか。
唐突ですが、二本の映画の話をします。一本目が「 西部戦線異常なし」という1930年公開映画。 二本目は1971年公開映画 「ベニスに死す」。どちらの主人公も最終シーンは、すがりつくように手を伸ばして死んでしまうという映画。伸ばした腕の先に何を求めていたのか。それは真実なのか、美しさなのか、愛なのか、死かも知れない。一般的に感じる共感とは違う別物で全く不可解、しかももっと根源的な何かで緊張感を持った世界を感じます。
詩にも、初めての表現が呼び起こす心の先ほどの共鳴とは全く違う衝撃があり、それは緊張であり、美しさであり、そして畏怖。この畏怖がミステリーの始まりだと思います。この畏怖を抱くような新しい言葉には「新しい表現との出会い」と「幻視する力」があります。幻視とは幻を見る、つまりありえないこと、これから起こりうることを見通す力だと思います。この二つが「詩の魔力」じゃないのか。
要は、そんな想像力を張り巡らすことのできる魅力的で魔力的な世界。まさにマジカルミステリーな世界に我々は足を踏み入れているわけです。 こんなに楽しい詩をやめられるわけがない、こんなに詩は面白いんだという話を今日はしたかったのです。
最後にもう一度申しますが、私たちの持っている武器の比喩。比喩を最強の力として詩を書いていきたいのですが、先ほど説明した二本の映画のラストシーンで、腕の先で指を伸ばし、何かにすがろうとする。それは、もしかするとボードレールも、ランボーもそうかもしれない。西脇順三郎も吉岡実もそうかもしれないし、皆さん方もそうかもしれない。皆さん方の伸ばしたこの腕と指の先に何かすごい表現があると期待しております。どうもありがとうございます。〈以上要旨〉
◆現代詩ゼミナール出席者
(二〇二五年一月二五日・敬称略)
相原京子・秋山公哉・麻生直子・雨宮汐里(旧・日下捺稀)・生駒正朗・石川厚志・磯崎寛也・犬伏カイ・伊武トーマ・尾世川正明・太田雅孝・大久保栄里紗・小野ちとせ・小山田弘子・鹿又夏実・川崎芳枝・川中子義勝・黒崎晴臣・小林弘明・古森もの・斎藤菜穂子・坂本登美・佐川亜紀・桜木利春・佐々木貴子・沢聖子・塩野とみ子・生野毅・鈴木正樹・末野 葉・関口隆雄・曽我貢誠・鈴木東海子・関 中子・田井淑江・高貝弘也・高木祐子・高橋加代子・滝川ユリア・竹内みち子・椿美砂子・富岡悦子・布川 鴇・根本 明・根本紫苑・nostalghia・福田恒昭・藤井優子・外村京子・堀 雅子・巻上公一・巻上開智・真崎 節・松井ひろか・松下美和子・光冨幾耶・水嶋きょうこ・水嶋美津江・みやうちふみこ・宮地智子・宮田直哉・森うずまき・森水陽一郎・雪柳あうこ・柳春玉・渡辺一郎・渡ひろこ(以下理事)郷原宏・塚本敏雄・杉本真維子・青木由弥子・秋亜綺羅・沢村俊輔・中島悦子・根本正午・野村喜和夫・浜田優・春木節子・広瀬大志・松尾真由美・山田隆昭・渡辺めぐみ
(計80名)
(記録・沢村俊輔)

会場風景