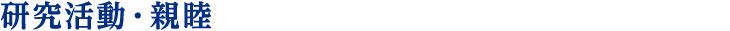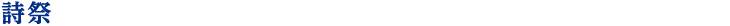日本の詩祭2016
日本の詩祭2016開催
起ちあがれ、わがミューズたちよ
H氏賞・現代詩人賞贈呈、先達詩人顕彰
6月12日、ホテルメトロポリタンエドモント
第二部は新倉俊一氏の講演。八木幹夫氏(理事)と新倉氏の質疑応答があり会場を魅了した。
18時から懇親パーティーに移り、田村副理事長の閉会の挨拶で終了した。
((会報の)詳細は2~7面。写真担当は石川厚志)
◇第1部(司会・斎藤貢、須永紀子)
始めに黒岩隆実行委員長からあいさつと司会者の紹介があった。司会は斎藤貢氏と須永紀子氏。
開会の辞で新延拳理事長は「今年の日本の詩祭のサブタイトルに「起ち上がれ、わがミューズたちよ」とありますが、会場のそこここに詩のミューズが立ち上がっているように見えます」と述べた。
H氏賞贈呈式
 まずは第66回H氏賞の贈呈式が行われた。郷原宏選考委員長から選考について報告が行われた。「今から三十数年前の芥川賞の選考で村上春樹氏の『風の歌を聴け』がノミネートされたことがありましたが、あっけなく落選しました。その時の選考委員の大江健三郎さんは、この作品はアメリカ文学の物マネで、自分の作品になっていないと反対しました。そのなかで、丸谷才一さんだけは、村上さんは大変な才能だ、これは日本文学史上の大変な事件であると評しました。結果はその通りになりました。新人文学賞の選考は難しいです。今回の選考委員は主観にとらわれずに公正な立場で選考をしていただきました。私たちは新しい才能を世に送り出すことができました」と述べた。
まずは第66回H氏賞の贈呈式が行われた。郷原宏選考委員長から選考について報告が行われた。「今から三十数年前の芥川賞の選考で村上春樹氏の『風の歌を聴け』がノミネートされたことがありましたが、あっけなく落選しました。その時の選考委員の大江健三郎さんは、この作品はアメリカ文学の物マネで、自分の作品になっていないと反対しました。そのなかで、丸谷才一さんだけは、村上さんは大変な才能だ、これは日本文学史上の大変な事件であると評しました。結果はその通りになりました。新人文学賞の選考は難しいです。今回の選考委員は主観にとらわれずに公正な立場で選考をしていただきました。私たちは新しい才能を世に送り出すことができました」と述べた。
以倉紘平会長から賞状と賞金が森本氏に渡された。
受賞詩集について白鳥央堂氏から「「書を捨てよ、町へ出よう」というのは寺山修司の言葉ですが、『零余子回報』を読んでいると、「書を拾え、本棚に戻そう」と言われているような気がするぐらい、本棚の似合う詩集だなと感じます」
また「書かれた言葉は常に過去にあって、そこで得た言葉を「いま書く」のだという強い責任感と、「俺は書を拾っていくんだ」という決意が、この出発の詩集にはみなぎっているような気がしてなりません」と語った。
森本孝徳氏から受賞の言葉があった。選考委員と会員にお礼と感謝を述べ「零余子」(むかご)とは植物の栄養繁殖器官のひとつであり、葉の付け根に形成されて、離脱後に新たな植物体を形成するといういわば無性生殖の過程における一形態です」と始めた。また「僕は「書くこと」の未来を託せるほど僕自身を信頼してはいません」や鈴木志郎康氏の作品から「感銘」をうけたのだが「この感銘とは《こんな眺めはいいなァ》の詩行に対し「成程僕は《終電車》で得体の知れない客たちに足で《けったり押したり》されている屑であり、またこの客たちも同様だが、他人に《こんな眺めはいいなァ》と言わせてたまるか」というものです。」と語った。「選考委員のお一人であった郷原宏さんが選評で仰っていたとおりこれは未だ高校生の《甘え》の内にある書物なのかもしれませんし、僕自身未だたしかな手応えを欠いています。しかし《読者によって選ばれる》ことの必要を僕は当面感じていません。」と考えを述べた。
日本現代詩人会と現代詩手帖から花束贈呈が行われた。
現代詩人賞贈呈式
 続いて第33回現代詩人賞の贈呈式が行われた。受賞は尾花仙朔氏の『晩鐘』に決定した。選考経過報告が、川中子義勝選考委員長から行われた。
続いて第33回現代詩人賞の贈呈式が行われた。受賞は尾花仙朔氏の『晩鐘』に決定した。選考経過報告が、川中子義勝選考委員長から行われた。
「尾花仙朔詩集は、「詩人とは」という問いに出発し、世界の存在への危惧を述べ、言葉の意義を問いました。時代の実相に、戦争を知る者の立場で正面から向かい合いました。真実の追究をしました。諸宗教の視座を交え、末法的現実を超え出る希求の眼差しがあり、手腕は卓越していました。観念の吐露ではなく、現代思想や古典の伝統から言葉が編まれます。思想と技量の一致を示し、一作一作が読者への問いを形作る点で抜きんでていました」と述べた。
以倉会長から尾花氏に表彰状と賞金が授与された。
原田勇男氏から受賞者の紹介が行われた。
「尾花さんの作品は、詩人としての真摯な生きざまと旺盛な批評精神に裏打ちされて、日本の現代詩に極めて独創的な視野を切り開いてきたと思います。幼少のころから身内の死を体験したほか、戦時中は戦争によって数多くの名もない人びとが無為の死を遂げた現実に直面し、自らが生き残ったという負い目を抱えながら、戦後を生きて来られた魂の痛みが感じられます。その意味で死者への鎮魂の祈りが作品の底を通奏低音のように流れています。一方でこうした庶民の人生を蔑ろにするような社会や国家の有り様に強い不信感を持ち、個の立場から批判の言葉を発しているのも、尾花さんの作品の特徴であります」と述べた。
受賞の言葉で、尾花氏はお礼を述べ「間もなく真夏です。七十一年前の八月ヒロシマとナガサキに原爆が投下されました。あの悲惨な大戦を忘れたかのように、今、憲法九条で守らされてきた国の形が壊されそうな瀬戸際です」と語り始めた。
「今の日本は典型的な衆愚政治です。詩人が、この憲法を蔑ろにして政治と国家を私物化する権力に靡き衆愚に与するとき詩は滅び詩人もまた滅びるのだと私は思います。後世の詩人からあの時詩人は何をしていたのか、お前はどんな詩を書いていたのか、と問われて恥ずかしくない仕事をしたいという思いです」と述べた。
先達詩人の顕彰
以倉会長から田中清光氏と田村のり子さんへ顕彰状と記念品の贈呈があった。
鶴岡善久氏から田中氏の紹介があった。「田中さんはデカルコマニーの詩人として有名です」と始めた。田中氏は立原、堀、リルケらに刺激されつつ独自の詩風を築いた。評論家で、作画は瀧口修造との親交が要因だった。詩の硬質、構築性は瀧口からのものと語った。
また鶴岡氏は、現在は憲法の最大の危機であり、日本現代詩人会も前文、九条、二十一条などを死守すべく強い改憲反対の声明も出すべきで、後世の詩人に田中氏の「東京大空襲」のような詩を書かせてはならない、と自説を主張した。
田中清光氏は顕彰を受け、「自分の深層に在りつづける深甚な実体験として、71年も前になりますが、〝東京大空襲〟のの中をさまよった体験が、ぬきがたいものとしてあります」としてリアルな大空襲の様子を語り始めた。「東京下町を集中して狙った空襲は2時間半という時間で、なんと10万人もの無辜の住民が焼き殺されたというものでした。住民の殺戮が周到に計画された焼夷爆弾投下でした。」さらに「家族4人で一晩中、燃える下町の中を逃げ回って、住居も、家財も、〝未来〟までを焼かれ、なんとか生き残りました。」と話を続けた。
またKという親友の安否を確認するために焼け野原の下町を歩いたことなど、生々しい戦争体験を詳しく述べた。
田中氏はパウル・ツェランやジャコメッティに触れ、現代詩というものをどう書くか、真摯に向き合う姿を感じ取れた。
紹介の清岳こう氏は「田村のり子さんと申しますと、『出雲國風土記』、ラフカディオ・ハーン、行動する詩人という単語が私の脳裏をよぎります」と語り始めた。『出雲國風土記』の編纂者に出雲在住の人物が深く関わっていること。出雲の人々の、歴史、生活等を克明に記録し伝えたいという願い。この強い思いが田村さんの詩の大きな特徴と述べた。ラフカディオ・ハーンとの出会い、「八雲会」への入会とハーン研究などを経て、詩集『ヘルンさん』を上梓。行動する詩人としては、島根の詩の『出雲石見地方詩史』を著わしたことなどを紹介した。
最後にアイルランド大使館長アン・バリントン氏のお祝いの言葉を伝えた。
「アイルランドと日本は地理的には離れていますが、精神的な意味では緊密であります。小泉八雲は、このことを日本の精神に共感し、日本の文化を理解することで見出したのです」「私たちは田村さんが詩を書く仕事を続けられ、魂の交感を持ち続けられることを大変喜ばしく思い、敬意を持っています」。
田村氏の受賞の言葉となった。「平素 居心地のいい出雲・国の地霊やら言霊の神様に見守られて静かに過ごしている私です。松江に十五年すごした小泉八雲・私共はヘルンさんと呼びますが、そのヘルンさんもやがてわが言霊の神となりました」。また「新文明と機械が人間をおびやかすことへのヘルンさんの抵抗は頑固で、例えば明治も30年代となるので東京の住いに電話はひきませんでした」と続き、「機械に頼らず人間の五感を働かして生きること。弱者の立場で共に生きること。ひとも自然も生き物も。そして女性を大切にすること」と話された。また島根原発にふれて「ヘルンさんがどんなに怒っているか!」と語った。
その後、田中氏と田村氏へ、日本現代詩人会、現代詩手帖、所属詩誌からそれぞれ花束贈呈が行われた。
詩の朗読として、H賞受賞詩集『零余子会報』の森本氏、現代詩人賞受賞詩集『晩鐘』の尾花氏が行った。優れた詩人たちの貴重な言葉と詩に触れることができ、有意義に第Ⅰ部が終了した。
(記録・光冨郁埜)
◇「詩祭2016」会員出席者
相沢正一郎、葵生川玲、秋亜綺羅、秋本カズ子、秋山公哉、朝倉宏哉、天野英、新井啓子、以倉絋平、池上耶素子、井崎外枝子、石川厚志、石田瑞穂、井田三夫、市川愛、市川つた、一色真理、一瀉千里、井上敬二、井上尚美、井上英明、植木信子、植村秋江、江口節、江島その美、大掛史子、大林美智子、小笠原眞、小笠原茂介、岡島弘子、岡野絵里子、小野ちとせ、
柏木勇一、方喰あい子、金井雄二、狩野敏也、川上明日夫、川上美智、川崎芳枝、川中子義勝、菊田守、北川朱実、北畑光男、清岳こう、草野早苗、草野理恵子、工藤富貴子、黒岩隆、黒羽英二、郷原宏、河野明子、こたきこなみ、小林登茂子、
斎藤正敏、斎藤貢、酒木裕次郎、佐々有爾、佐々木久春、ささきひろし、颯木あやこ、沢聖子、沢村俊輔、志田道子、志村喜代子、下川明、白井知子、新川和江、新藤凉子、菅沼美代子、鈴木東海子、鈴木豊志夫、鈴木漠、鈴木比佐雄、鈴木正樹、須永紀子、関口隆雄、瀬崎祐、曽我貢誠、
高貝弘也、高島清子、高田太郎、高橋次夫、田上悦子、田口三舩、田中清光、田中眞由美、田中美千代、谷口典子、玉田尊英、田村のり子、田村雅之、対馬正子、鶴岡善久、戸台耕二、富田和夫、富永たか子、
中尾敏康、中田紀子、中原道夫、中村純、中本道代、なべくらますみ、新延拳、西野りーあ、二宮清隆、布川鴇、根本明、野木京子、
硲杏子、服部剛、浜江順子、林田悠来、原利代子、原田勇男、原田道子、原島里枝、春木節子、坂東寿子、はんな、樋口忠夫、平井達也、平岡敏夫、平澤照雄、比留間一成、昼間初美、平林敏彦、福島純子、藤井優子、藤田晴央、藤本敦子、古屋鏡子、別所真紀子、北条裕子、堀内みちこ、
水木萌子、光冨郁埜、峯尾博子、峯澤典子、宮地智子、向井千代子、望月苑巳、森川雅美、森山恵
八木忠栄、八木幹夫、山田玲子、山中真知子、山本聖子、結城文、吉田隶平、
渡辺みえこ、渡辺めぐみ、渡ひろこ
――――――――――――――
・会員出席者 154名
・一般参加者 75名
・来賓・報道 33名
・懇親会出席 106名
◇第2部 講演 新倉俊一
「詩人 西脇順三郎とエズラ・パウンド」
第2部は「詩人 西脇順三郎とエズラ・パウンド」と題して新倉俊一氏の講演で始まった。新倉氏は西脇順三郎氏と親交があり、西脇詩学の研究の第一人者で『西脇順三郎全詩引喩集成』『詩人たちの世紀 西脇順三郎とエズラ・パウンド』『評伝 西脇順三郎』などの著作がある。現在明治学院大学名誉教授で日本エミリー・ディキンソン協会会長でもある。同じく西脇順三郎の研究者である八木幹夫氏による詩の朗読を交えながら、次のように講演した。(要旨)
「西脇さんの記憶はいろいろありますが、何と言っても最初の忘れられない強烈な印象は、先生を中心とする詩人たち十人ぐらいが参加した自作解説の会です。メンバーは那珂太郎、中桐雅夫、安西均、福田陸太郎、楠本憲吉、加藤郁乎、鍵谷幸信、関口篤、諏訪優、藤富保男、松田幸雄、それに私がレギュラーメンバーで、時々佐藤朔さんなどもお呼びし『アムバルワリア』から始めて、一九六七年四月から七三年の第一回の全集完成までやりました。先生は機知の精神が豊かで、いつもわたしたちはあっと驚かされました。
今考えると凄い詩の饗宴ですが、なぜあんなに熱心に続いたかと考えると、時代が急激に変化していくので「西脇さんの詩はそのうち、誰もわからなくなって死語になってしまう」という危機意識があったように思います。西脇詩には引喩が非常に多いので、生きておられる内にきちんと聞いておこう、という気持ちが皆にありました。これは先生ご自身にもあって、それが、七年間の読書会が終わってからも、私一人で毎週ご自宅に伺って、さらに七年間、先生が亡くなられるまで、例の「引喩集成」の仕事を続けた理由です。
従来、西脇さんを論ずるときには萩原朔太郎との関係とか戦後詩との違いとか、固定した日本の詩史の枠内で語られることが多いですが、星座表を手に星空を見るときのように、少し軸を横にずらしてみるともっと新しい構図が見えてくるのではないでしょうか。
西脇さんが帰国後、百田宗治の機関誌「尺牘」に新しい詩を書いてほしいと頼まれた時、創刊号に「カプリの牧人」「雨」「菫」「太陽」の四篇を載せていますが、このなかの「雨」という詩と一脈相通ずる詩風の作品がエズラ・パウンドにもあります。第一次大戦後英訳された『ギリシャ的抒情詩集』の中のイービュコスの原作を翻案して、現代詩風な付け句をした「春」という作品です。(「春」「雨」朗読)
西脇さんの「雨」という作品は全部が創作ですが、どことなく南欧の風景を喚起させる風や雨など春の季節をあつかっていて、その終わりに「この静かな柔い女神の行列が/私の舌をぬらした」と、やはり一種の〈付け句〉をしている。これがふたりに共通する新しい詩法でした。
イギリスから帰国後、西脇さんは教室でさかんにパウンドを口にしたと井筒俊彦さんが語っています。エズラ・パウンドの『詩学入門』を教室で詩作の教科書として援用されたようです。
西脇さんに強い影響を与えた海外の詩人として挙げられるのはエリオットですが、エリオットの『荒地』を現在のようなすっきりした形にしたのはパウンドです。エリオットはパウンドを批評家として最大限に評価しています。
戦後、弟子の岩崎良造訳の『エズラ・パウンド詩集』が荒地出版社から出ましたが、それにパウンドへの西脇さんの献辞「より巧みなる者へ」が載っています。ここには既に意識の流れに従ってジグザグ進む詩法、のちの『キャントーズ』風の自由な連想のスタイルへの始まりがみられます。「より巧みなる者へ」というタイトルは、エリオットが『荒地』でパウンドへの献辞としてつかったのに倣ったものです。(「より巧みなる者へ」朗読)
ちょうどパウンドが初期のイマジズムの簡潔な詩風から後の長い詩に移ったことと連動するように、西脇さんも『アンバルワリア』の短詩形から戦後は『旅人かへらず』を転機として、「初めも終わりもない長詩形」へ移行しています。『第三の神話』『失われた時』『えてるにたす』、これらはみな六十歳代に書かれています。
『えてるにたす』の「エピローグ」で犀星が『室生犀星全詩集』で捨てた「永遠」という言葉をできるだけ多く使った、と書かれています。(「えてるにたすⅡ」より朗読)西脇さんはこの詩集で「永遠」という観念を言葉で分節しようとし、いくら分節しようとしても分節できなくて無限の言い換え、換喩となっていきます。
西脇さんの詩はイメージが多いと言われますが、それだけではなく、この長編詩には音楽もあります。それはパウンドがイメージや諧謔と並んであげる詩の三大要素の一つの「メロポエイア」にあたり、長編詩を支える重要な特徴です。
パウンドは『キャントーズ』を説明して意識の叙事詩だと言っていますが、西脇さんの長編詩は「歴史を欠いた抒情詩」で、東洋的な伝統につながっています。西洋の詩人は歴史を直線的に扱う傾向がありますが、西脇さんの詩は(無)や(空)をめぐって永遠に堂々巡りする傾向がみられるのです。
西脇さんとエズラ・パウンドは詩情の傾向こそ違いますが、東西でともに長篇詩に向かったことには、現代詩の同時代的な問題性を抱えての実験があり、この長い詩は今後も可能性をひめているのではないでしょうか。」
講演の後は質疑応答となり、八木幹夫氏が自身の西脇詩との出会いを語りながら、西脇詩の非キリスト教、非仏教的な部分や詩法、将来への可能性などについて質問した。新倉氏は「西洋人にとって永遠とはダンテのように直線構造であり、西脇さんの永遠は円環構造で、東洋的世界を極限まで追求した」「西脇さんの詩は無を象徴しているが西洋人にはわかりにくいかもしれない」と答えた。
また、会場からは新川和江氏が西脇氏の思い出を語った。
西脇詩への理解と興味を深めることができた、有意義で充実した講演の時間であった。
最後は友部正人氏のフォーク演奏を楽しんだ。友部正人氏は沢山のアルバムと『おっとせいは中央線に乗って』などの詩集を持つフォークシンガーで詩人。「マウリの女」「銀の汽笛」「彼女はストーリーを育てる暖かい木」「はじめぼくはひとりだった」「歌は歌えば詩になって行く」の五曲をのびのびと演奏した。自由と孤独、希望などが溶けあった歌が会場いっぱいに響き、聴衆の心を揺さぶった。現代の吟遊詩人の姿を堪能することのできた時間だった。
黒岩隆実行委員長が閉会の言葉を述べて「日本の詩祭2016」は終了した。
(文責 中本道代)
◇懇親会
午後6時から会場を移して懇親会が開かれた。司会は柏木勇一氏と中田紀子氏。田村雅之副理事長が開会の言葉を述べ、続いて以倉紘平会長が「それぞれのかけがえのないミューズを大切にしましょう」と挨拶した。また名誉会員の平澤照雄氏から平澤貞二郎記念基金に千三百万円の寄付を受けたことを報告し「これから生まれてくる人のために心を尽くすことはわれわれの詩の本質である」と感謝を述べた。
新川和江氏、武子和幸氏、新藤凉子氏、菊田守氏の来賓挨拶のあと、平澤照雄氏の乾杯の音頭で宴となった。歓談の合間に遠方から出席した江口節氏、佐々木久春氏、井崎外枝子氏、一瀉千里氏、植木信子氏、北条裕子氏、中村純氏が挨拶。また新入会員の後藤大祐氏、玉田尊英氏も挨拶をした。午後8時、名残を惜しみながら閉会となった。
(記録 中本道代)