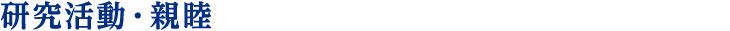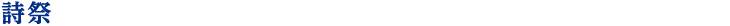日本の詩祭2015
日本現代詩人会最大のイベント「日本の詩祭2015」が、『いま同じ時代を生きて詩を語る』というサブテーマで、6月7日(日)、東京・飯田橋のホテルメトロポリタンエドモントで開催された。総合司会を新延拳実行委員長が務め、北畑理事長が開会の挨拶。詩祭は二部構成で13時からの第一部では、H氏賞・現代詩人賞の贈呈と、先達詩人4氏の顕彰。それぞれの挨拶と詩の朗読があった。
第二部は、芥川賞、朔太郎賞受賞の町田康氏をゲストに迎え、「現代詩をぶっとばせ」と題して、会員の山田兼士氏と対談。さらに会員5名による朗読隊が町田氏の著書『残響』(中原中也の詩に寄せる言葉)から13編の作品を朗読、それに町田氏が応じるという奇抜な構成で会場を魅了した。
18時から懇親パーティーに移り、金井副理事長の閉会の挨拶で終了した。
◇第1部(司会・下川敬明、永方ゆか)
実行委員長の新延拳氏が、現代詩の世界では詩人の考え方、価値観、批評の視座、技巧などが共有よりも拡散の傾向にあるが、受賞者、先達詩人及び町田康氏からいただく示唆により、詩についてゆっくり考える一日としたいと述べた。そして第Ⅰ部の司会者を紹介した。北畑光男理事長は開会のことばの中で、H氏賞受賞者の岡本啓氏、現代詩人賞受賞者の八木忠栄氏、先達詩人の石川逸子氏、岡崎純氏、新藤凉子氏、及び安水稔和氏への祝辞を述べ、芥川賞作家で萩原朔太郎賞受賞者でもある町田康氏と詩人の山田兼士氏との対談への期待を表した。そして、今年は戦後70年、阪神淡路大震災から20年、東日本大震災から4年と3ヶ月だが、過去と現在に向き合うその向き合い方で未来が開かれてくるようにも思われ、この場が詩の出発点になることを祈念していると語った。また、会員及び関係者の皆様の詩祭への御協力と御理解への謝意を述べた。
◇H氏賞贈呈式
次に第65回H氏賞の贈呈式に移った。廿楽順治選考委員長は、会員投票による上位8冊及び選考委員推薦3冊からなる30代1人40代1人50代から60歳代9人の計11冊の候補詩集について、次のように選考経過を述べた。各委員が5冊ずつ選び最初の投票で6冊に絞り、1冊ずつ議論を行い、2回目の投票で最も推したい順に3点2点1点と評価点数を変えて投票してもらった結果、草野理恵子詩集と岡本啓詩集が残った。この2冊について再度討議し、決選投票の結果、岡本詩集6票、草野詩集1票となり岡本詩集が受賞した。また、廿楽氏としては、岡本氏1人が若かったことや中也賞を直前に受賞していたことについて、二次的なことと判断したと述べた。
H氏賞の贈呈は財部鳥子会長が行った。受賞詩集の紹介者で、岡本氏の現代詩手帖賞受賞時の選者の1人だった石田瑞穂氏は、受賞詩集はアメリカのワシントンDCから新人欄への投稿作品が中心であり、アメリカと日本という2つの社会と文化、及び2つの言葉のはざまに立つ緊張感が、日本では味わえない抒情と言葉の力強さや優しさで、当時選者の心を打ったと振り返った。また、岡本氏がワシントンDCで出逢った様々な無名の人々との、人種や国籍を超えた声のコミュニティーのようなものを織り上げており、そのことが詩集の重要な横糸になっているが、それは戦略によるものではなく、野生性のようなもので書かれていると述べた。そして、帰国した岡本氏が日本の現実と切り結び今後どんな詩を書くのか楽しみである、と受賞を讃えた。 岡本氏は受賞のことばの中で、受賞の喜びとともに詩作を始めたときの経験を語り、生きてゆく上でのエンジンとしての詩があることに気づかされたと語った。また、アメリカに住み日本語で詩作する中で、どんな言語にも、何かの言葉の表情のような形で、生きてゆく上で切り離すことのできない感情が宿っていることに感動を覚えたと述べ、詩の手前の、人が生きること自体の中にある、論理的な分析によって捉えようとしてもこぼれ落ちる豊かなものに、文字で応える行為の一つとして詩があるのではないかと話した。
◇現代詩人賞贈呈式
続いて第33回現代詩人賞の贈呈式に移った。選考委員長の八木幹夫氏は、候補詩集の中で最終的に赤木三郎詩集、長嶋南子詩集、八木忠栄詩集の3冊が残ったとして、赤木詩集と長嶋詩集の特色を報告した。八木詩集については、表題作「雪、おんおん」の「おんおん」は怨念であると同時に雪深い新潟の風土の声であると指摘し、受賞詩集は自己の言葉と郷土の風土と都会的なセンスがしっかりとまとまった感があり、雪の「おんおん」という心音が本当の意味でビートの鼓動として響いてくることに共感したと述べた。
財部会長による現代詩人賞の贈呈のあと、八木忠栄氏と50年来のつきあいのある中上哲夫氏が受賞詩集について紹介した。八木氏は詩ジャーナリズムの中心的なところにいたが、様々なトレンドに災いされないよう個人誌を出し、書き始めからこじんまりとした詩を書くことを避けていたという。また、前詩集『雲の縁側』からは特に枠組を取り払い自由に書き始めた感があり、受賞詩集はその更なる発展形であると考えられることや、雪が若いときから八木氏の一貫したアイデンティティーであると語った。
八木忠栄氏は、受賞のことばの中で選考委員への謝意を述べ、自分は行儀の悪い詩しか書けないがそんな詩に現代詩人賞を与えていいのか、とユーモアを交えて語りつつ、「現代詩手帖」元編集長らしい現代詩の現況へのコメントを述べた。近年頭の良さそうな難しい詩が目につくが、現代詩のフィールドは広いので、いろいろな書き方があったほうが望ましく、フィールドが一つの方向だけを向いていると痩せてくるので、ますますお行儀の悪い詩を書くべきなのかなと思っていると。また、詩は頭で書くのではなく手足で書くのが持論だ、とも述べた。
◇先達詩人顕彰
先達詩人の顕彰に進み、財部会長から、石川逸子氏、体調不良で欠席の岡崎純氏の代理の安井杏子氏、新藤凉子氏、及び安水稔和氏に、顕彰状と記念品が手渡された。続いて先達詩人のことばに移った。石川氏は、最近最も心に響いてきたこととして、翁長沖縄県知事の基地問題をめぐる発言を紹介し、戦没者に対する哀悼の意を深く表した。そして、ニューギニア戦で亡くなった師に語りかける「A先生へ」及び「かなしみが」という自作詩を朗読し、歴史の暗部を凝視する姿勢を貫いた。岡崎純氏の先達詩人のことばは、岡崎氏のお孫さんの安井氏が代読した。地方に生まれ地方において書くことを選んだ岡崎氏が、同郷の福井の先達として慕う「先達詩人」藤原定氏と山本和夫氏及び福井に移住した詩人則武三雄氏の人となりへの感謝と崇敬の念が伝わってくる文章だった。そして、岡崎氏の「私にとって詩作とは、故郷の人々の言うに言われぬ悲しみ、言い尽くせぬ悲しみを、土壌として語りだす行為だった」という言葉を裏付けるかのように、安井氏が岡崎氏の自作詩「茶碗をわる」、「古井戸」、「極楽石」などの4篇を朗読した。
新藤凉子氏は、生きるのも困難な身体も心も弱っているようなときに詩は自分を救ってくれたと述べ、御自身の詩作回路について語った。自分にとって一番切実な問題を書くことが、社会やその風潮に違和感を抱くことに繋がり、その居心地の悪さが詩を書かせるのだという。そして、20代で受けた盲腸の手術体験に基づく「波」という若い頃の自作詩を朗読したが、「人間ハ生キテイルコトガツラクテモ/終リタイト叫ンデハイケナイ/闇ヲモ手ニ掬イ/生キラレルダケ/生キヨ/ワタシハマタ生マレテクルヨ」という詩行が、生あることの責任を痛感させ、時を経ても古びない鮮やかさで会場に広がった。
安水稔和氏は、神戸大空襲で黒田清輝の名画「朝妝」と「昔語り」が所蔵場所で焼失したとき、まさに御家族とそのそばを通って逃げ延びたことや、神戸震災のとき安水氏の自宅脇が通学路となっている小学校の小学生が亡くなったことを話した。そして、自分は亡くなった人々となんとか生き延びた人々と共に生きてきたのだと思うと述べ、T・S・エリオットの「現在と過去は/未来の中にあり/未来は過去の中にある」及び「そして、すべては常に今」(今居る場所で踊りなさいの意)という言葉を紹介した。被災の記憶を風化させまいとする強い使命感と被災者への同胞意識が伝わってきた。
このあと岡本啓氏が「グラフィティ」を、八木忠栄氏が「ライオンまたは有楽町駅前で驟雨に遭う」と「こぼれる、彦六さんよ」をそれぞれの受賞詩集から朗読、第1部が終了した。(文責 渡辺めぐみ)
◇第2部 対談・町田康氏を迎えて
第2部は、ゲストに詩人、作家、パンク歌手の町田康氏を迎え、会員の山田兼士氏(大阪芸大教授)との対談で幕を開けた。町田氏は芥川賞、萩原朔太郎賞、川端康成文学賞、谷崎潤一郎賞などを受賞、多彩な表現活動を続けている。対談は「現代詩をぶっとばせ」というタイトルで、朗読も織り交ぜながら、小気味よく展開された。
対談:現代詩をぶっとばせ(山田兼士×町田康)
当日は聞き手(山田)が用意した資料(B4判7枚)を町田氏に手渡して、適宜参照しながら対談を進めるように打ち合わせた。資料はおもに、2003年以降に刊行された町田氏の著書二十数冊から「詩表現」をテーマに抜粋したものである。
対談は町田康氏の詩「陣羽織着て昭和刀佩いた詩の死骸、地下足袋もはいて」(2003年)の朗読から始まった。「腐った詩、詠むあほ共、死にやがれ/腐った詩、腐っていると知りながら保身するもの、滅びやがれ/なめとったらあかんど神を人を/なめとったらあかんど犬を花を/なめとったらあかんど車海老のパスタ/天麩羅粉を浴びてまいまいこんこん/地下足袋はいてまいまいこんこん/おれはかならずおどれをしばく/おれはかならずおどれをしばく」。なんとも過激で正直なフレーズの連続だ。これがパンク精神。
話題はまず初期の短篇代表作のことから始まり、やがて代表作『告白』の連載時(読売新聞夕刊)の苦労や工夫へと移っていった。その工夫の一つは、毎回千字という枠の中で少なくとも一つは読みどころを作ること、そのためにエンターテインメント的要素が要ること。もう一つは、南河内弁を駆使するなど文章表現に工夫をすること。ここに町田氏の「耳の仕事」の重要さが示され、詩人的素質をうかがい知ることができた。また、近年盛んに書かれている猫エッセイや犬エッセイで、私小説的要素が正面に表れていることも、新しい可能性として触れられた。特に、犬視線からのエッセイ『スピンク日記』は興味深く、独自の文学的価値を産み出しつつある、というのは聞き手の認識。
続いて、詩表現にあふれたエッセイの数々に話題がおよび、自慢は決してしないこと、むしろ自虐的とも見えるユーモアを中心とすること、そのためのモチーフ選びのことなどを語っていただいた。一例として、エッセイ集『テースト・オブ・苦虫』から「酢トーカー」の一節を朗読し、言葉を意図的に誤解することから生じるユーモアの実例を示した。さらに、パンク歌手として出発した時点からこだわり続けてきた「歌」への志向に話題が進み、ここで歌と詩の相違などに触れることができた。歌はあまり内容が詰まっていてはいけない、むしろ空疎で無意味な要素が必要であること。さらには、古い歌謡曲や芸能などに話が進み、町田文学の背景を垣間見ることができた。話はさらに進み、次の要素は言葉の組み替えや区切りかえによる新しいイメージの創出。歌謡曲「伊勢佐木町ブルース」を「伊勢裂き鳥ブルース」と読み替える実例には抱腹絶倒。「あ、鉈」「しっ。照美」「な、豊子。破魔……」等々。「歌」といえば中原中也の詩にも触れざるを得ない。後の朗読企画にもかかわることだが、「中原中也の詩によせる言葉」との副題をもつ町田氏の著書『残響』に英語タイトルとして「machidakou sings nakaharachuya」と記されていることの意味を問いかけた。得られた結論は「中也はパンクだ」ということ。図らずも中原中也と町田康の共通項が明らかになったわけだ。中原中也の詩と町田康のコメント(実質的に「詩」と呼べる)を呼応させる朗読会は最初、山田が企画し、朗読作品の選定も山田が行った。
次に挙げたのは、エッセイとも小説とも取れる長篇(町田氏自身は「エッセイ」あるいは「随想」と呼ぶ)『この世のメドレー』。町田氏によれば、いくらフィクション的要素が多くても(例えば「私」が発狂したり死んだりしても)、少しでも自分の体験した出来事に依拠していればそれは「エッセイ」。その喩えとして町田氏が挙げたのは、落語家の故・桂枝雀。どれほど自由な動きを取り入れたとしても「足の指一本だけでも座布団に触れていれば、それは落語の所作」とのこと。町田氏の「エッセイ」が(詩表現をはじめ)あらゆる表現形式を含むことの背後にはそのような認識があった、ということだ。
最後の話題は「音」の面白さについて。時に強迫観念にもなり得る「音」の魔力の一端を、まずは「ドラえもん」の歌詞の解釈から、次いで『この世のメドレー』に挿入された「歌」の朗読で示していただいた。作中で敵対する青年に嫌がらせをするためのパンクロックの歌詞、という設定で書かれた五十行ほどの作品だ。ただし、これは「歌」との設定でありながら実際に曲が付いているわけでなく、今後も作曲される可能性は「絶対にない」とのこと。つまり「歌」のふりをした「詩」であって、「歌」そのものではない。実に巧妙に仕組まれた「詩論」とさえ、私(山田)には思われる。歌と詩は微妙に交差し合い重なり合いながらも、最終的には決定的に異なる表現同士である、という結論だ。
最後に、現代詩への提言などを聴きたかったのだが、時間の都合で割愛。ただ、ここまでの対話の中ですでにその示唆は十分に為されてきた、と考えている。(報告・山田兼士)
町田康氏と朗読隊「残響」を朗読
対談の後は、町田康氏の著書「残響」に収められた57編の中原中也の作品から13編を、会員5名で構成された朗読隊が朗読、それぞれの作品に寄せた町田氏の言葉を町田氏自ら読み上げるという趣向。さながら即興劇を演じている雰囲気で展開した。
黒い帽子に黒い衣装、蝶ネクタイというコスチュームで登場した朗読隊は、服部剛、峯澤典子、亜久津歩、小野ちとせ、光冨郁埜氏(朗読順)。
中也の「骨」「春の日の夕暮」「曇天」「臨終」「言葉なき歌」「サーカス」「正午」「(テンピにかけて)」「冬の長門峡」「汚れつちまつた悲しみに…」「一つのメルヘン」「詩人は辛い」「四行詩」を交互に、個性豊かに、会場いっぱいに響く声で朗読した。
その都度町田氏も立ち上がってマイクに向かい、スピードとトーンを変えながら朗読。時空を超えて谺しあう、中也と町田氏の魂の残響の一端がうかがえた。
朗読会終了後は朗読隊及び会場からの質問に町田氏が答えたが、その即答ぶりにも会場が湧いた。中也にはいつごろから関心を、という質問には「1997年頃で若くはなかった。中也が好きという高校の友人を白眼視していた」と答え、「歌と詩と小説は自分の中でどう区別しているのか」という問いへの答えは「適当です」だった。
◇懇親会
午後6時から会場を移して開かれた懇親会は会員、招待者、一般を含め150人を超す出席者で賑わい、詩集賞受賞者、先達詩人、ゲストの町田康氏も交流の輪に包まれていた。
司会は服部剛氏と岡野絵里子氏。山本十四尾担当理事が開会の言葉を述べ、財部鳥子会長の挨拶の後、日本詩人クラブ前会長の清水茂氏の乾杯の音頭で宴が始まった。
懇親を深める語らいの合間に、遠方から出席した会員を代表して、冨長覚梁氏(岐阜)、森三紗氏(岩手)、小笠原茂介氏(青森)、池上耶素子氏(静岡)が近況報告をまじえながら挨拶。新入会員の鎮西貴信氏、山崎ゆめ子氏、多喜百合子3氏らが挨拶をした。
午後8時、金井雄二副理事長の閉会の言葉で「日本の詩祭2015」の幕を閉じた。