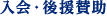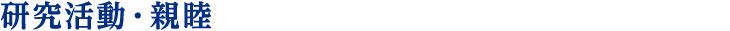各地のイベントから(会報180号から)
各地のイベントから(会報180号から)岐阜県詩人会第十三回総会・講演会
岐阜県詩人会事務局長 白木 憲

講演する佐相憲一氏
岐阜県詩人会第十三回定期総会は、五月九日(金)午後二時よりハートフルスクエアーGにて開催された。質疑応答を経て議案はすべて審議承認され、総会は無事閉会した。
総会終了後午後三時十五分より、詩人・佐相憲一氏を講師に迎え、「詩を書く中で見えてくるもの」と題する講演会が開催された。講師は自作の詩を朗読しながら、その詩が生まれた背景や詩作に込めた想いを語り、詩人としてのまなざしや人生観を聴衆と共有した。
冒頭の詩「ゴマフアザラシさん、こんにちは」では、野生動物との偶然の出会いから生命の尊厳を見出した体験が語られ、会場は静かな感動に包まれた。「あおそこひ」では緑内障の妻との日々から生まれた祈りのような作品が紹介され、「眼球は地球に似ている」という詩的直観が印象深く語られた。また「クモのグラブ」では、精神を病みながらも幼い自分にやさしさを注いでくれた叔父の姿を、芸術的な喩えで描いた。
さらに、「鬼の舞い」「統計学」「汽笛」などの作品では、社会や歴史の裏側にある痛みや連帯、死者との対話といったテーマが詩の言葉で掘り下げられた。詩とは、傷ついた人々の深層を照らし、時代や国境、命の境界を越えてつながる力を持つものであることが、講師の語りからにじみ出ていた。
講演後、参加者からは「言葉の力を再認識した」「死者が詩によって生き続けるという思想に打たれた」との声も聞かれ、詩人会にふさわしい、深く心に残るひとときとなった。
詩人の肖像――藤子じんしろう、その人と作品——
講演 藤子じんしろう氏「画かきとして詩人であることの朦朧」をきいて
二〇二五・五・一八 熊本市中央公民館
熊本県詩人会 担当:甲斐ゆみこ

講演する藤子じんしろう氏
わたしたちは普段、家庭や職場に身を置きながら日々を暮らしている。それは当然のことのようにも思われるが、しかしそれなら、詩を書く時はどこにいるのだろう。「詩人は永遠の漂泊者」と云ったのは萩原朔太郎だけでなく、芭蕉や山頭火、西脇順三郎など枚挙にいとまがない。実際に書く場所が台所の一隅であったり、机の前であったり、喫茶店のテーブルであったりすることは物理的なもの。精神は常にことばというゆくえ定めぬ旅路のうえ、つまり作品自体のなかに在るのではないか。藤子さんという創作家は画家であり詩人。しかし私(筆者)は思う。そのことばのなかに家をもつ画家とちがって詩人は人に属する。そう考えると幼少から藤子さんの精神には言葉に対する信頼(魂のよりどころ)がまずあって、表現の選択肢は人生の出会いのなかで育まれた夢のように思われる。私(筆者)自身、なぜ今に至るまで詩をつくることをやめなかったか、と考えるともはやそれしか生きる道がなかったと今は云える。
生きているうちにおこりうるあらゆる事態ことを思い巡らすと、今生きてある日々、享受している平安が実は偶然の産物であって、その背後には常にそれらの崩壊を孕んでいると思わざるを得ない。筆者はずっと若いころから殆ど何の根拠もなく「詩を書く人は自分のなかに何か闇のようなものをかかえている」と思っていた(例外はあろうが)。ながいおつきあいのなか、知りあって間がないころ、藤子さんの印象は、私にとっては温厚で優しく、バランスのとれたよい美術教師で詩も書く、こんな人に教えられる生徒たちは安心だろうなどと思っていたものだ。その考えはやがて少しずつ変化し、逆に変わらぬものもあると気づく。絵と詩、それぞれ、逆立ちしてもかなわぬ奥の深さを持つ世界。藤子さんにとって、それらは流れるふたつの川のようであり、よりそい、離れ、あるいは交わりながら同じ芸術の海に注ぐ。「自分は特別ではない」(藤子)。ただ自分である。作品は発表されたとたんに作者をはなれ、独立した存在となる。詩集は読者に届いてからも、動きをやめない生きもの。生命である。作者をはなれた、時間も空間も遠いところから、詩集自身が読者に語りかける。語りかけることをやめない。永遠に読者を待っている。どの分野にもいえることかもしれないが、多くのその人の刊行詩集のなかで、デビュー作に最も色濃くその人、その作品価値が凝縮されている。それまでのながい時間、かかえてきたゆきどころのない何ものかが一気に噴出するから。藤子さんの処女詩集「病根」(一九八一、もぐら書房)を送っていただいた時、私(筆者)はまだ若く、勿論面識もなく、あまりいい読者ではなかったかもしれない。しかし時経て、もはや人生の終わりに近くなってはじめて、詩集から語りかけられることになる。こういうことがあるから人生は面白く、油断がならない。聖書にもある。〝すべてのことに時がある〟知るにも時がある、ということだろうか。家族のなかの軋轢、葛藤、因襲。その後、現段階で十一冊という詩集を上梓してこられたその原点である。
いつだったか、藤子さんの絵の前に立った時、これは〝自画像〟だと思った記憶がある。そして、筆者自身にも作品から深く語りかけてくるものがあった。絵で描ききれずこぼれおちたものが詩ではない。人間とは不可解で深淵、当の作者にもはかりしれないものを秘めている。絵と詩とその作者自身と、互いに語りあい、影響しあう。自らうみ出した作品によって、更に発見を得ることもあれば、逆に殺されることもある。壮絶な闘いが作品の背後にあったろうに、藤子さんはいつも水のように静かだ。苦悩は作品となって昇華される。
広島県詩人協会
二〇二五年度総会及び記念講演会
岡馬重充

講演する江口節氏
広島県詩人協会では二〇二五年六月十四日、広島市中区の地域福祉センター大会議室で「総会及び記念講演会」を開きました。講師には、日本現代詩人会会員で広島県三原市出身でもある、江口節さん=神戸市在住=をお招きしました。江口さんは「詩を書いていくということ」と題し、俳句が身近にあった子どものころのお話から、青春期の詩が書けなくなった時期、阪神・淡路大震災後の「詩のことばがあふれ出るような体験」など、日常生活の中から生み出された詩について語られました。十一冊の詩集の中の詩を引用し朗読しながら、とても意義深いお話でした。
その中で江口さんは、「現実感覚と宇宙感覚が奇跡的に融合したのが、私の震災詩だった。あふれ出るように書いてしまう。たくさんの人が亡くなり、理不尽な死もあったけれど、直接見ていない。詩をああしたい、こうしたいではない。直接、命の現場を見るしかないと思った」と述べられました。
そして、災害だけでなく、平凡な日々でも、命自身が味わうような思いがある。「なぜ、やむにやまれず詩を書くのか」問い続け、「生でも死でもない命あるそのもの、存在そのものから詩が発生する。存在の可能性を開くものが詩の根本である」と、オクタビオ・パスの本から読み取った。その後は、何でもない日々にでも、生きていることそのものを味わいたい、と思うようになったと話されました。
命があること、触れること、目で直接見ることから存在の実感、命のつながりを実感し、それが宇宙とつながっている。観念ではなく、触れること、体感でないと存在の実感は味わえない。自分が抱えてきたこと全部が済んで思い返すと、すべて時代を抜きに語ることはできない。バブルがあって、不景気があって、貫いているのは日々の生活。当たり前のことが分かるのに五十年かかった――と振り返られました。
ポエトリー岡山

講演する一色真理氏
詩の裾野を拡げたいという願いから岡山県詩人協会では、朗読会「聞いてください岡山の現代詩」や「詩を楽しむ会」などを開催してきた。「ポエトリー岡山」も総会行事の後に、一般市民向けに開かれた催しとして誰でも気軽に現代詩の風に吹かれてほしいと無料で実施している。
今年は、一色真理氏をお招きして、6月28日に岡山国際交流センターにて「詩と無意識」という演題で講演をしていただいた。次のような貴重なお話を聞くことができた。
岡山では四十五年前、一九八〇年にH氏賞を頂いた時に話したことがあり永瀬清子さんも来られ「こういう話が聞きたかった」と言われ嬉しかった。
今日は、「詩と無意識」について。
無意識とは何なのか。たとえば三歳のころは憶えていないが、まぎれもなく無意識は続き今の自分と繋がっている。夢は無意識が見るが、無意識を意識化する練習をすれば詩を書くのに役立つだろう。
以前、パソコン通信のニフティサービスで共同夢日記「夢の解放区」を作り、メンバーと短編小説のように書き合い楽しみオフ会もしてきた。本も出した。小柳玲子さんの「夢人館」の閉館記念に「夢の解放区」展をし、解散した。その活動の中で集合的無意識、全部が繋がっているのではないかと思うことがあった。ネットを通じると起きる共振があるのではと。同じ日同じ時に同じ夢を見るという現象があり、夢にも音楽があり、夢で聴いて楽譜に起こすことを私もした。
詩は無意識を意識的に噴き出させて書くためには、いきなりパソコンやスマホで書くとよい。キーボードを打ちながら無意識の水系を掘り当てる。その出てきたものが水か泥か見分ける力を身につければよい。推敲するより、新しく書いたり穴を明けて水を噴出させたりするほうがよい。
一色氏の話は、他にも、親との葛藤を書くのは難しいこと、詩人になる前はUFO研究者だったことなど、興味深い話が続き、参加者からの質問もあり、とても密度の濃い時間となった。
(岡山県詩人協会理事長 中尾一郎)