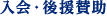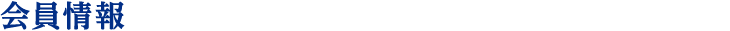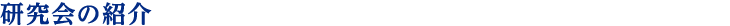各地のイベントから
各地のイベントから福島県現代詩人会
「詩祭 講演と朗読の集い」
岩田武昭

講演する橋浦洋志氏
令和六年十月二十七日(日)に、いわき市生涯学習プラザの大会議室で、今年度の福島県の第45回「詩祭 講演と朗読の集い」(十三時~十六時)を開催した。
第一部は「講演会」。詩祭の実行委員長である天野行雄氏(いわき市)が開会のことばを述べた。その話のなかで、今回の講演会講師の橋浦洋志氏が、かつていわき市で開催された第十六回現代詩ゼミナール「やさしい詩の教室」(平成五年十月実施)でも講師を務めてくださったこと、あれから三十年余りの歳月が過ぎたことを懐かしく紹介した。講師の橋浦洋志氏は、現在は茨城大学名誉教授になられ、「詩を読むということ」という演題で、詩というものがいったいどのような言語的な特徴を持つのか、具体的な詩篇や音韻の特徴などを例示しながら、きわめて興味深い話をしてくださった。
まず、「詩は要約できない」ものであるから、詩を定義することの難しさや詩が「わかる」とはどういうことなのかに言及された。そして、詩のなかの「この一行がいいな」と思えれば、それで十分であり、詩のことばに共鳴し共感することがもっとも必要で大切なことではないかとも。また、言語の文法的規律を破ることが、いわば「比喩」という詩に特有の表現方法にほかならないのだが、その規律違反に自由さを感じることが、詩を読み味わう喜びの基本にあるのではないか、とも話した。
中原中也の詩「月夜の浜辺」、萩原朔太郎の詩「竹」、山村暮鳥の詩「岬」などを例に挙げて、わたしたちがなかなか気づけない拍数や反復、リズムといった詩の形式面の論理にも踏み込んだ内容であり、とても興味深い講話であった。
講演の後は、第二部の「朗読の集い」。県内五地区の代表者による朗読を行った。
詩祭最後のアトラクションは、フォーク者イサジ式によるフォーク歌唱。楽しく有意義な時間であった。終了後は、詩祭開催地区であるいわき地区の会員の皆さんの労をねぎらいながら、さらに講師にも参加していただいて懇親と親睦を重ねた。
ポエム・イン静岡2025
さとう三千魚

講演する廿楽順治氏
2025年1月26日(日)に「ポエム・イン静岡2025」は静岡市の「あざれあ」特別会議室で、詩人、廿楽順治さんに「老いて、詩を生きるということ」というご講演をしていただきました。
東京や横浜、名古屋、神戸からご参加いただいた方もあり会場満席の状態で、高齢の方も多くご講演の内容は身に沁みました。
ご講演のタイトルと小見出しだけを列記いたしますと以下のようになります。
「老いて、詩を生きるということ」 「老い」とは 「老い」は時代で変わる? 「老い」のイメージ 「老い」対「若さ」 詩の業界の「若さ」 「若さ」の風俗と詩 「修辞的現在」と「若さ」対「老い」の図式 天野忠とずれ 粕谷栄市と迷宮 岩佐なをと「老い」のパロディ 「老い」の一人称 岡崎清一郎と破天荒 西脇順三郎と語りの器 石原吉郎と極限値 結語 現代詩の洗脳
タイトルと小見出しだけを見ただけでも鳥肌が立つような感覚をおぼえます。各々の詩人の詩を引用されながら岡崎清一郎さんの詩に言及して「老い」と「詩」の関係性の先に『詩人格』というタームを置いた廿楽順治さんの詩の把握に驚きました。廿楽順治さんが『詩人格』や『ハビトゥス』という言葉で詩人を語るとき私はなにか腑に落ちたようで詩を書いて生きてきてよかったと思えたのでした。ありがとうございました。
また、ご講演の後に八人の会員が自作詩を朗読し廿楽順治さんにご感想をいただけたことも、とても嬉しいことでした。
ご講演原稿は廿楽順治さんの許可をいただき以下サイトに公開してあります。宜しければ、ご覧ください。
「浜風文庫」https://beachwind-lib.net/?cat=69
詩を楽しむ会
岡山県詩人協会 上岡弓人

講演する斎藤恵子氏
2025年3月16日(日)14時、日本現代詩人会の賛助をいただき岡山県詩人協会では「詩を楽しむ会」を岡山市のオリエント美術館地下講堂を会場に開催しました。10回目の今回はあいにくの冷たい雨の中での開催となりましたが約50名の来場者がありました。当日は岡山市主催のおかやま文学フェスティバルが旧小学校校舎を会場に開かれ当詩人協会も協賛で「おかやま文芸小学校 美しい詩をあなたにⅡ」のタイトルで朗読や詩の教室にも参加しました。
詩を楽しむ会では、上岡会長が開会挨拶の後、郷土岡山出身の詩人安東次男氏の略歴を紹介し次いで中川貴夫会員、下田チマリ両会員による安東次男の詩『六月のみどりの夜は』から「佐渡」、『蘭』からは「残雪譜」などを朗読の後、メインテーマの「郷土の詩人 安東次男」と題した講演を斎藤恵子岡山県詩人協会副会長が行いました。
安東次男は一九一九年岡山県苫田郡(現在の津山市)で生まれ、小学校四年まで過ごし以後は神戸に移住。旧第三高等学校、東京帝国大学卒業、第二次世界大戦後は教職に就き最後は東京外語大学教授。最初は俳句を学び、戦後に詩作に転じた。一九四九年に詩集『六月のみどりの夜は』を発表、翌年には第二詩集『蘭』を刊行して埴谷雄高、中村稔、飯島耕一らと交流。以後教職の傍ら詩、評論、随想の他にフランス文学の翻訳フランソワーズ・サガン『悲しみよこんにちは』などに多くの足跡を残し二〇〇二年四月に逝去しました。居住した期間が短く、郷里ではあまりなじみがなかったのですがこの機会に学び顕彰しようとこの講演が企画されました。
「佐渡」という詩では流人の悲しみに触れ、佐渡の地に染み込んだ伝説の悲しみと日本海の怒濤の昏い歌を詠った。また、「残雪譜」では高麗末南鮮古窯の茶碗の感触や表に浮かぶ景色から、早春の実感を、残雪の深さで知った幼少の頃の郷里での自分を思い出し、小鳥の死骸を石のように握りしめたまま暮れてゆく風景の中に茫然と立ち尽くしている情景を詩にしたもの。いずれの作品も独特の鋭い感性が表れています。